人間学の現在(26)
今回は、これまで何度か言及してきた「ホモ・シグニフィカンスの人間観」について、わたしの立場からの要約と評価を行いたいと思います。
前回の講座で、わたしは、菅野盾樹氏が提起したこの概念には、光の部分と影の部分があると言いました。
ここでは、『人間学とは何か』をまだ読んでいない方のために、まずはホモ・シグニフィカンスについての解説を行い、次に、この概念についてのわたしなりの評価を行い、最後に、この概念が抱えている「影の部分」についても若干、言及してみたいと思います(その部分についてのまとまった考察は次回の講座で行う予定です)。
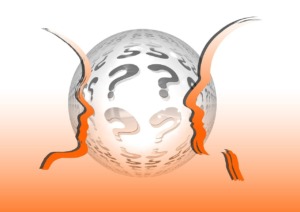
ミニマム人間学という発想
はじめに、ホモ・シグニフィカンスについてまとめておきましょう。
『人間学とは何か』の第3章のタイトルは、「人間観の類型学からミニマム人間学へ」というものです。
人間観の類型学とは、マックス・シェーラーが人間を五つの類型に分類したところからはじまったもので、平俗な言い方をするなら、人間のタイプ分けとでもいうべきものです。
類型学についての解説はこの講座の第3講で行っているので、ここでは繰り返しません。
菅野氏は、シェーラーの類型学について批判的に検討しながら、その結論として、ミニマム人間学という概念を提示しています。
人間の存在構造についての必要最小限の定義とは何か、という問題意識から氏はこの概念に到達したようですが、その答えとして、ホモ・シグニフィカンスという人間観が導びかれています。
一流の学者だけあって、氏がホモ・シグニフィカンスという概念を打ち出すまでの論議の道筋は至って論理的で、読者を納得させるだけの力があります。
人間の代名詞として巷でよく言われるのは、ホモ・サピエンスというものですが、この「理性を持った動物」という呼称は、たしかにとてもわかりやすくて便利なものです。
「わかりやすくて便利」なので広く世の中に流布したわけですが、欲を言うなら、人間学としてはもう少し学問としての厳密さがほしいところです。
そこで、菅野氏は、ホモ・サピエンスを始点としながら、「ホモ・ロクエンス」と「アニマル・シンボリクム」を経由し、そのうえで、ホモ・シグニフィカンスなるものを提示するに至ったのでした。
そのため、ホモ・シグニフィカンスを理解するためには、ホモ・ロクエンスとアニマル・シンボリクムを見ておく必要があります。
ホモ・ロクエンスと、アニマル・シンボリクム。耳慣れない用語なので何やら難しそうですが、その意味するところのものは、ある意味、当たり前のものです。
ホモ・ロクエンスとは、「言葉を話す人」という人間観のこと。
なんだ、当たり前じゃないか、と思いますよね。
菅野氏の説明を読んでみましょう。
ミニマム人間学の構想は、次の二つのタイプの人間観から多大の示唆を汲み取ることができる。ひとつには〈ホモ・ロクエンス〉、すなわち〈言葉を話す人〉という人間観である。ホモ・サピエンスの人間類型によれば、人間の本質は「理性」であった。そしてこの語の原語ロゴスが示すように、理性の具体的で有効な現実形態はなによりも「言語」にほかならない。それゆえ、まだ言葉を解さない幼児や言語能力に重大な支障をきたした人間に「理性」はないと判定されることになる。理性は広い意味の知性の能力であるが、ただしその精確ななかみをどう考えるかについては人によって違っていた。たとえばカントは、感性的所与を概念化する認識能力を「悟性」と呼び、これとは区別して悟性的認識を体系化する高次の能力を「理性」と呼んだ。このように「理性」が必ずしも一義的でも明確でもないのに対して、人間が互いにやり取りする相互行為としての「言語」には比較的に意義の紛れがないように思える。人間は孤立した個人としては生きられない。個々人が相互関係のただなかでしか人間としての存在様態をまっとうしえないかぎり、ミニマム人間学の優先順位としては、理性より言語に人間性の証しを見るホモ・ロクエンスの人間観のほうが他の人間観に先立つ。人間は、神の信仰者、理性の人、政治的動物、遊ぶ人間、経済人、ものを制作する人・・・・などであるより先に「言葉を話す人」だといえよう。逆にもし人間が言語能力を有していなかったら、たとえばキリスト教の信仰がおこなわれただろうか、あるいは共同体の政治的運営ができただろうか、と問うてみよう。答えは明らかではないだろうか。(p46~47)
次に、アニマル・シンボリクムについての説明を読んでみましょう。
もう一つ参考とすべきものは、カッシーラーが提唱した人間観である。新カント派としてのカッシーラーは、人間の概念作用が単に世界を写し取るのではなくむしろ世界を形態化する働きだと考えた。概念はシンボル(記号、表象)によって表現されるが、彼は理性ないし悟性だけではなく、直感、知覚、想像力などの心の働きのすべてがシンボルによって媒介されるとした。したがって、悟性が形態化する科学的世界のみならず、直感と知覚がもたらす自然的世界や想像力がもたらす神話的世界にもシンボルの形態化の働きが及ぶと見なくてはならない。言い換えれば、科学、芸術、宗教、神話などあらゆる精神の所産は、人間のシンボル機能の所産なのである。この意味で、人間はまさに〈アニマル・シンボリクム〉すなわち〈シンボルを操る動物〉である。
二十世紀の自然科学や数学の新たな進展に深い関心と造詣を有していたからであろうか、カッシーラーは、世紀の比較的早い時期に認識にとっての〈記号〉の意義を重視し、記号機能と人間性との本質的絆を基礎に哲学体系を構想した、ほとんどただ一人の哲学者であった。その仕事の意義はいくら強調しても強調しすぎるということはない。彼の本国ドイツにおいて直接その仕事を継承する研究者は出現しなかったが、現在、ドイツ内外で様々な再評価の試みがなされつつある。
「言語」に代えて「シンボル」を正面にもちだしたことで、彼はホモ・ロクエンスの人間観のある意味の「狭さ」を打破したということができる。後に触れることになるが、カッシーラーはシンボル機能の一種の進化論を考えた。もっとも原初的なのは〈表情〉機能であり、次に〈記述〉機能、最後は〈意味〉機能へとシンボル機能は展開していく。字義的な意味での「言語」の働きは記述機能以降に属することに注意しなくてはならない。「シンボル」は言語を含むと同時に言語以前の身体的表出や表情そしていわば言語以後の論理計算などを含んだ広範囲の領域を覆う概念なのである。このかぎりで、ミニマム人間学としての優先順位はアニマル・シンボリクムがホモ・ロクエンスに先行するといわなくてはならない。(p47~48)
ホモ・ロクエンスとアニマル・シンボリクムについての説明を終えたあと、菅野氏は、ホモ・シグニフィカンスという新しい概念を提示することになります。
該当箇所を読んでみましょう。
以上二つのタイプの人間観から学びながら、私たちとしては〈ホモ・シグニフィカンス〉すなわち〈記号機能を営む人〉という類型を基礎的でミニマムな人間の概念として提案したいと思う。問題となるのは単に言葉の争いではない。ことがらは、ミニマム人間学の内容と資質そのものに関わるのである。(ちなみにこの用語自体は、文化記号論者のバルトが使用しているが、私たちの用語法とは異なっている点に注意を促したい。)(p48〜p49)
そしてこのあと、菅野氏は、人間についての従来の概念をなぜ「ホモ・シグニフィカンス」に更新すべきなのか、という点について説明しています。
しかしながら、詳説するスペースはないので結論だけを述べることにするが、彼の見地はたしかに多大な示唆に富むが、やはりミニマム人間学の見地からすると「狭すぎる」と言わなくてはならない。現代の科学は、生体としての人間が生物学的・生理学的な水準ですでに記号機能(遺伝、免疫など)を営むことを教えているが、カッシーラーがシンボル(記号、表象)というとき、このミクロの水準は彼の視野にはまったくなかった。さらに重大なこととして、彼の考え方の基本には古典的な理性主義がやはり抜きがたく存在している。記号機能の一種の進化論はそのあらわれの一つである。
私たちは、よき伝統に学びながら人間観を新たに建て直す課題をになっている。新たな人間には新たな命名が必要であろう。ホモ・シグニフィカンス―これが新しき人間の呼び名である。(p50)
『人間学とは何か』の第3章はここで終わっています。そして4章からは、3章にわたって「ホモ・シグニフィカンス」についての論議が展開されています。
ではまず、この概念の定義となる部分を読んでおきましょう。
このテクストで私たちが「人間の存在論」と呼ぶのは、人間の存在構造への問いに答えようとする知的探求である。すなわち、人間とはいったい何だろうか、どのような性質や成り立ちをしているのかといった問いへ、経験科学の知見からできるかぎり学びつつ、しかも客観主義や実在論の形而上学に捉われることなく、合理的でバランスのとれた人間像を描写しようとする試みにほかならない。心と身体の古典的二元論を括弧に入れた私たちがその代わりに用意している新たな枠組みは、人間存在を、身体・言語・心という三つの秩序の統合体と捉える人間観である。(p58)
人間の存在構造を、身体・言語・心という三つの秩序の統合体として捉えること。これがすなわち、「ホモ・シグニフィカンス」の基本的な考え方にほかなりません。
三つの秩序の統合体としての人間
では、この「三つの秩序」のそれぞれの要素について菅野氏が語っていることがらを見ていきましょう。
『人間学とは何か』の第4章は、「ホモ・シグニフィカンス」の「身体」についての論議になっています。
カッシーラーの人間観においては、人間の身体におけるミクロレベルの「記号機能の営み」の認識がありませんでした。
無理もありません。エルンスト・カッシーラーは1874年生まれの人で、彼が活躍した時代は二十世紀の前半でしたから。
(彼の著作には『人間:シンボルを操るもの』などがあり、この書物は岩波文庫からも出版されています。)
ところがその後、分子生物学などの著しい発展により、人間の身体においても「自己」をうちに宿した記号機能の営みのあることがわかってきました。その典型的な例となるのは、わたしたちの免疫の能力です。
菅野氏の説明を読んでみましょう。
ところで近年、分子生物学の著しい発展にともない、ミクロな水準における生命現象が単なる機械的な化学反応としては理解できないこと、情報の伝達や受容を基礎とした記号論的現象であることがますます明らかにされつつある。ここでは免疫の仕組みがどのようになされるのか、専門研究の一端を紹介しながら、ミクロな身体的過程がやはり記号過程であることを明らかにしよう。
人間は誰でも顔かたちの相違はともかく身体はほとんど同じ素材からできている。ところがある個人から身体の組織や臓器を別の個人に移植すると、はじめのうちその組織は機能しているが、数日後には組織は破壊され血流は途絶え異物として排除されてしまう。なぜ人間同士の間での臓器の移植が不可能なのだろうか。
生物学者は、免疫系がそれぞれの個体の微妙な差を見分けて、「自己」と異なったところのある細胞や組織を厳格に識別し、「非自己」として拒絶する仕組みを明らかにした。識別の標識となるのは組織適合抗原と呼ばれる一群のタンパク質で、人間ではHLA抗原と呼ばれる。この抗原にはすべての細胞の表面にまるで旗印のように現れているものと、白血球の一部や皮膚細胞の一部など、限られた細胞にのみ現れるものとがある。移植の拒絶反応は、このHLA分子のどれかひとつが異なっても起こる。T細胞と呼ばれる免疫細胞は、このHLAの微妙な違いを認識して、移植組織を排除しようとする。自分と異なるHLA抗原を持つ細胞を発見すると、T細胞はさまざまな手段で攻撃する。直接にとりついて破壊する場合もあり、特殊な物質を分泌して他の細胞を動員し、自己以外の細胞を排除する場合もある。このように、拒絶反応は、「自己」と「非自己」の識別を基礎とする反応なのである。―この記述中の「認識」、「発見」、「排除」、「拒絶」などの用語は、部分的に擬人法が混じった一種の省略語法にほかならないが、問題の本質は擬人法にあるのではなくて、生体の免疫反応が「意味を媒介とした反応」であるという点にある。移植された組織は「非自己」という標識をそなえているために排除される。このかぎりで、免疫は単なる化学反応ではなくて意味が介在する記号過程なのである。(p67〜p68)
言われてみればたしかにそのとおり、という内容ですね。人間のからだにはミクロのレベル、すなわち細胞の次元においても、代替不能の個性なるものがあるというわけです。
個性がある、ということは、互換性がない、ということでもあり、たとえば、Aさんの臓器をBさんに移植しようとしても、Bさんのからだはそれを受け付けない、という事態が起こります。
菅野氏はこうした事実を指摘しながら、人間の身体もまた、「ホモ・シグニフィカンス」にほかならないことを主張します。

では、次にいきましょう。
『人間学とは何か』の第5章は、「ホモ・シグニフィカンス」における「言語」の説明です。
人間と言語の関わりについては古くから多くのことが言われているし、わたしもこの講座のなかで何度か言及しているので、ここでは、菅野氏の論議の要点だけを述べておきましょう。
これまでの人間学になかった論点として、菅野氏は、人間の「表情」について踏み込んだ話をしています。
人間がもつ「表情」機能について改めて考えてみると、たしかに、真摯に向き合うべき哲学的なテーマがそこにあることに気づきます。
たとえば、ヒトの顔からすべての表情を消してしまうと、ヒトはヒトではなくなってしまいます。まったく表情のない人間たちの世界は奇怪というほかなく、考えただけでもぞっとしますね。
言語と表情の関係についての菅野氏の論議も秀逸で、一読に値します。
これらの言説は、新しい世界をわたしたちに見せてくれたという点で「ホモ・シグニフィカンス」の「光の部分」と考えてよいでしょう。
菅野氏は、「言語」の存在を人間の「身体」と「心」から独立させたことで、現代を生きるわたしたちによりフィットする世界観を描き出すことに成功しているように思えます。
「はじめに言葉ありき」というのは聖書の思想でもあるし(ヨハネによる福音書の冒頭部分を参照)、菅野氏が指摘したように、東洋の哲学においてもそれと重なるような世界観が説かれています。
また、言語学の創始者であり構造主義の火付け役となったソシュールに対する評価と批判も、菅野氏ならではの卓見です。
「言語」は、人間の発明品でありながら人間に先立って存在しているものでもあり(この点については文法の成立過程について考えてみるとよいでしょう)、「文は人なり」と言われるように、単に意見の表明や意思疎通のためのツールというわけでもありません。
つねに何かしらそれ以上の役割を担っているものが言語ではないかと、わたしも常日頃感じています。
では、次にいきましょう。
『人間学とは何か』の第6章は、「ホモ・シグニフィカンス」における「心」の考察です。
心の中心部分につねにあるのは、やはり「自己」というものではないかとわたしは思います。
「自己」の何たるかについて考えてみると、話はすぐにややこしくなってしまいますが、この章の小見出しは、事物の「自己」、人間の「自己」、心の「自己」となっており、そのあとに、機能主義、心と言語の類比説、という小見出しが続いています。
この章は上記の5つの小見出し(セクション)によって構成されていますが、そのなかで、わたしが最も重要だと思う箇所のみを引用しておきましょう。
私たちはすでに古典的な心身の二元論を放棄した。かわりに身体・言語・心という三重の構造として人間を捉えようとするのが、私たちが選んだ見地である。身体がすでに記号機能をおこない言語と切り離しがたく結ばれ、逆に言語が基本的には身体の所作であり表情であったように、人間存在の三重構造はそれぞれの位相の構造が他の構造を先取りしかつ後者が前者を強化するような構成を備えるように見える。したがって、言語がすでに意味を表すとすれば、心はそれにもまして意味作用の器官だといえよう。逆に心が言語の意味機能を強化するのは明らかである。人はしばしば心に思うことを言葉にだすからである。心へのこうしたアプローチを「心と言語の類比説」と呼ぼう。心は一種の言語のようなものだ、というのがその基本的洞察である。(p103)
ではそろそろ、今回の講座のまとめに入りましょう。
「ホモ・シグニフィカンス」の限界点
「ホモ・シグニフィカンス」の「光の部分」についてまとめてみると、それは、最新の経験科学の成果を取り込んで人間観の更新に成功したこと、ということになるでしょう。
その意味で、菅野氏が『人間学とは何か』において設定した目的は、みごとに達成したと言えます。
「あとがき」のなかで、たとえば菅野氏は次のように述べています。
ここ二〇年ほどに限っても、「人間学」と銘打たれたテクストがいくつも出版されていることは承知している。そのすべてを参照できたわけではなく、すべてがそうだと言うのでもないが、それらのテクストには「未完の企てとしての人間学」という問題意識が乏しいように思われた。それらのテクストのように、人間に関係するさまざまなテーマを適宜選択し、それらに関する著名な哲学者ないし思想家の見解を公平に紹介し若干のコメントを綴って一書を成すというやり方だけは避けよう。これが筆者がこのテクストを執筆するにさいして自身に課したルールだった。何よりも人間学の〈構想〉が問題であった。筆者の脳裏で〈人間学〉のイメージが明確な輪郭をとるまでかなりの紆余曲折があり、結果として執筆に予想外の時間がかかってしまったというわけである。(p202〜p203)
非常に共感のできる発言であり、このような優れたテクストによってわたしもまた、人間学研究に対するモチベーションを高めることができたわけです。
では、ひるがえって、「ホモ・シグニフィカンス」の「影の部分」とはどのようなものでしょうか。
詳細については次回の講座で話しますが、わたしの見るかぎり、『人間学とは何か』の7章から11章(最終章)までの内容は、この著作の1章から6章までの内容ほどには充実していません。
もちろん、これは菅野氏の力量が不足しているからというわけではなく、また、7章以降のテーマの設定が不適切だったからというわけでもありません。
事実、7章から11章にかけても、菅野氏は、人間学にとって最重要ともいえるテーマについて独自の視点から論議を展開しています。
ですからそういう意味においては、『人間学とは何か』は十分に充実した書物であるともいえます。
このテクストが大学の授業で教科書として使われることにも、わたしにはまったく異論がありません。
にもかかわらず、この書物の後半には、わたしを唸らせるほどの「斬新なもの」がありませんでした。
なぜかというと、「ホモ・シグニフィカンス」の「光の部分」が、7章以降の論議のなかでは影をひそめてしまったからです。
そのため、「ホモ・シグニフィカンス」としての人間はいかに生きるべきか、ということがらが十分に語りきれない状態で、この本は終わっています。
このあたりの問題が、わたしには「影の部分」として感じられているのです。
次回の講座では、この問題についてもう少し詳しく話してみたいと思います。
では、今回の話はこのへんで。
(関根均 せきねひとし)
1960年生まれ。慶応大学卒業。専攻は国文学。2010年日本人間学会に入会。現在、研究会員として人間学の研究に取り組んでいる。






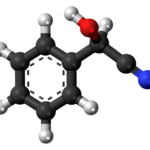


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません