人間学の現在(23)
今回は『情然の哲学』第8章の解説です。
この章のタイトルは、日本の使命と役割。サブタイトルは、「和」と「道」が織り成す日本文化、というもの。
一見してわかるように、この章もまた前章と同じく、とても大きなテーマについての論議になっています。
ただし、この章は、この著作の核心的なテーマからはやや外れるため、章のページ数も9ページと少なく、日本文化の特質についての簡単な叙述にとどまっています。
とはいえ、わたしが思うに、この章の内容はとても重要なもので、日本文化の特異性については、やはりこの章においてどうしても語られるべきものであったと思われます。
「情然の哲学」のような大きな思想は、決して個人の力だけによって生まれるものではなく、そのような思想を可能にした文化的な土壌というものがあるはずだからです。
そのため、今回は、このあたりの問題について少し掘り下げて考えてみることにしましょう。

「和」と「道」の文化
近年の日本はおおむね、この国を訪れる外国人からさまざまな賞賛を受けることが多いようですが、かれら外国人が異口同音に言うのは、日本には伝統的な文化と先進的な文明が矛盾なく共存している、という点です。
たとえば、新幹線などがそのよい例かもしれません。
高速鉄道はほかの国にももちろんありますが、外国人からすると、新幹線はそのなかでも抜きん出た存在であるようです。
かつては、先進国といえばアメリカやヨーロッパの国々でしたが、最近では、欧米諸国の人たちがこの列車に乗っても驚くというのです。
速度が出るというだけではありません。高速でありながら静かで乗り心地がいいし、車内はいたって清潔。運行時間も正確で、トイレなどの設備も、使いやすくて快適。また、駅や車内で販売されているお弁当なども、種類が豊富でとてもおいしい。
至れり尽くせりというわけですね。
しかも、日本人はみなマナーが良く、列車の到着を待つときもプラットフォームに整然と並んで人に迷惑をかけることがない。
それから、これは笑い話ですが、電車の走行が静かすぎるため、「この列車、いつまで停車してるの?」と怒り出す外国人もいるとのこと。
「われわれは、いつの間にこれほど差をつけられてしまったのか」
かれらの称賛のなかにはこんな羨望の思いも混じっているようですが、日本人がこんな日本の状態を(すなわち現在の日本の文化と文明を)「当たり前」と思っているところにも、外国人は衝撃を受けるようです。
とりわけ、中国や韓国を旅行したあとで日本を訪問すると、ほとんどの人は想定外のカルチャーショックを受けるといいます。
「同じアジアなのに、なぜ?」という驚きですね。
また、中国や韓国の人たちは若い頃から反日教育を受けていますから、「日本は悪い国・劣った国」という先入観をもっている人も多く、そんな人であればあるほど、現実の日本を見たときのカルチャーショックは劇的なものになります。
YouTubeなどの投稿動画により、日本の風景や人々の暮らしぶりなどが世界に紹介されるようになったおかげで、「ぜひ実物に触れてみたい」という熱い思いで、最近は世界中の人々が日本を訪れるようになりました。
そうすると、ユーチューバーたちは、「日本のどんなところが気に入りましたか」とか、「どんなところに驚きましたか」などといった質問をかれらに投げかけます。
かれらの答えは、みなほぼ同じです。
日本は治安がいい。日本は清潔だ。日本の都会はまるで未来都市のようだ。日本の古都はおもむき深い。日本人は礼儀正しくて親切だ。日本の食べ物はとてもおいしい。日本のアニメは最高だ。日本のコンビニはすごい。などなど。
どうやら日本の文化は、その魅力によっていまや世界の人々を巻き込みつつあるようです。
たしかに、わたしたち日本人は、現在、外国人に驚かれるような文化と文明のなかに生きています。
そのことは実際、たとえば東京や京都の街を歩いてみるだけでもよくわかります。
『情然の哲学』では、このような日本の文化に対し、「和」と「道」の観点から分析を試みていますが、「和」を横軸、「道」を縦軸と捉えるあたり、わたしたち日本人にもある種の驚きを与えるような内容になっています。
分析というとなんだか冷たい響きがありますが、そこには実際に日本で暮らしてみないとわからないような洞察もあり、実感に富んだ日本文化論になっているところも見逃せません。
では、本文を少し読んでみましょう。
「和」と「道」という二つの軸と共に、「つながり」と「ゆらぎ」も、日本文化の根底に流れる特徴的な言葉である。これは情然の哲学をつらぬく重要な概念「関係性」と「ゆらぎ」にそのまま直結している。著名な日本文化研究家・松岡正剛(1944〜)は、著書『日本という方法 ― おもかげ・うつろいの文化』の中で、日本的なるものを括るキーワードとして「おもかげ」と「うつろい」を挙げている。これもまた「つながり」「ゆらぎ」と深い関係にあるように思える。
「おもかげ」は、「私」と、「あなた(あるいは誰か)」や「ふるさと」などの対象との間(つながり・関係性)に立ち現れるイメージのようなもの ― いや、イメージは自分の心の中の「像」であるのに対して、「おもかげ」は、どことなく「私とあなた(対象)との間」にゆらぐ実体的な存在であるかのようなニュアンスがある。イメージは「慕う」ことができないけれど、「おもかげ」は慕うことができる。孫を見て「おじいちゃんの面影が残っている」という場合も、「おもかげ」は、「私の中」だけにあるのではなく、その孫の中にこそあるものとして捉えられている。さらに深く考えれば「祖父と私と孫(あるいは親族一同)」の関係性の中で共有されている「心的存在」のようなものであるともいえる。
イメージは「慕う」ことができないけれど、「おもかげ」は慕うことができる。
じつにみごとな洞察です。この一文があることによって、『情然の哲学』の日本文化論は、他の凡百の文化論とは一線を画したものになっているように思えます。
また、「慕う」ということば自体、ラブということばとは置き換えることのできない、何かしら深く実存的な情の世界を含意した概念であるように思えます。
「イメージ」と「おもかげ」の違い、あるいは「ラブ」と「慕う」の違いなどは、西洋文化と日本文化の違いを端的に照射するものとして注目すべきでしょう。

日本語の構造と存在の構造
日本語は、人称代名詞や敬語などが非常に発達している言語ですが、ここで少し、ことばの問題について考えてみることにしましょう。
『情然の哲学』第8章の最後の小見出しは、「日本語に表れる日本人の感性」というものです。
「おかげさま」「おたがいさま」「いただきます」「ごちそうさま」などは、日本人にとってはごく当たり前のことばですが、これらを外国語に翻訳することはとても難しいとされています。
これらのことばは、日本文化のなかから生まれてきたものだからです。
たしかに、日本語は難しい、という声はよく聞きますね。
日本語のなかには、漢字とひらがなとカタカナがあります。そして、漢字には音読みと訓読みがあります。和語と漢語と外来語が入り混じって調和し、一つの文章を形成しているため、外国人にとっては難解な言語のように思えるのでしょう。
たとえば、中国語には漢字しかないし、韓国語にはハングル文字しかありません。また、英語にはアルファベットしかありません。ですから、漢字やひらがなという異種の文字体系が一つの文章のなかに共存しているのは、それだけでも不思議な言語のように思われるわけです。
不思議なのは、それだけではありません。
これはわたしたち日本人もあまり気づいていない事柄のようですが、実のところ、日本語の構造は「存在の構造」ととてもよく似ているのです。
存在の構造とは、「情然の哲学」が明らかにしたように、「家族的四位構造」のことです。
わたしたち人間は、親子軸と男女軸が垂直に交差する場所のなかに存在していますが(男女の親から生まれてこない人間はいないし男でも女でもない人間はいないということです)、「情然の哲学」によれば、次元の違いはあるにせよ、この「家族的四位構造」の存在法則と無関係に存在している存在物はひとつもありません。
では、果たして、わたしたちの母語である日本語のなかにも、「家族的四位構造」はあるのでしょうか。
当然、あることになります。
では、日本語における親子軸と男女軸とはいったい何なのでしょうか。
それは、漢字とひらがながつくり出している縦軸と横軸の関係です。
ご存知のように、ひらがなは漢字から生まれています。古くから音声言語として存在していた日本語を表記するために、日本人は漢字、すなわち中国から輸入した文字を素材として日本独特の文字を発明しています。
そのため、漢字とひらがなは「親子軸」を形成しているのです。
親子軸を「縦軸」とすれば、それと一体不可分のものとして「横軸」がなければなりません。なぜなら、「縦」という概念が成立するためには「横」という概念が必要だからです。
では、漢字とひらがなは、親子軸であると同時に男女軸でもあるのでしょうか。
平安時代の日本において、ひらがなの担い手はおもに女性でした。そのため、娘を失った悲しみを吐露するためにひらがなを用いた日記を書こうとした紀貫之(871?〜946?)は、その日記のなかで自身を女性に仮託しました。
土佐日記(935?)の冒頭にある次の一文は、有名ですね。
「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとて、するなり」
(男の書くという日記というものを、女である私も書いてみようと思って、書くのである)
当時はまだ日記文学というものは存在せず、日記と言えば、男性貴族が漢文で綴った公的な日記(業務日誌のようなもの)がほとんどでした(私的な日記もあるにはありましたが、それもやはり漢文体でした)。しかし漢文の日記では、自分の心のうちを表白することができません。そこで貫之は、当時としてはまだできたての和文で日記を書こうとしたわけです。
このような歴史の事実を振り返ってみるだけでも、漢字は男性格、ひらがなは女性格であることがわかります。したがって、漢字とひらがなは男女軸をも形成しているのです。
日本の文化のなかにも「道」と「和」という縦横の軸があり、また日本語のなかにも漢字とひらがなという縦横の軸がある。
『情然の哲学』が日本文化の土壌のなかから生まれ、その原著が日本語によって書かれているというのも、決して偶然のことではないようにわたしには思えます。
もしかすると「情然」という概念は、悠久なる日本文化の土壌のなかから芽生え、幾人かの気鋭の研究者たちの努力によって花を咲かせることになった、大いなる福音なのかもしれません。
この一輪の美しい花がやがて実を結び、それが地に落ちて種となり繁殖をはじめるとき、日本の思想界にも黎明の季節が訪れるようになるでしょう。
そして、人間の価値を最高度に高めてくれるこのような思想が(伝統性と先進性を兼ね備えたメイド・イン・ジャパンの思想が)、やがて世界に影響を与え、世界を席巻するようになっていくことでしょう。
この国産思想のブランド価値は、今後ますます高まっていくのではないでしょうか。
わたしには、そのように思えてなりません。
では、今回の話はこのへんで。
(関根 均 せきねひとし)
1960年生まれ。慶応大学卒業。日本人間学会には2010年に入会。現在、当会の研究会員として人間学の研究に取り組んでいる。





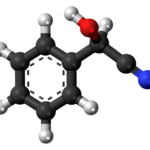





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません