人間学の現在(17)
わたしたちはここ数回の講座で、「アルケー=情然」という世界認識の妥当性について考えてきましたが、今回からしばらくのあいだ、「情然」以後の世界について考えてみたいと思います。
原初の世界が「情然」の状態であったとしても、「情然」が永遠に「情然」のままであったとすれば、今もってこの世界は、老子の言うような混沌の世界であるはずです。
ところが、今から138億年前にビッグバンが起こり(これは今では科学的な事実ということになっています)、何もないところから広大な宇宙空間が生まれ、わたしたちのような知的生命体まで出現するようになりました。
宇宙の歴史に関しては、わたしたちはすでに多くのことを知っているので、わたしがここであらためて述べるまでもありません。そのため、この講座では、宇宙の歴史の部分はすべてバイパスし、「情然」とこの世界との関係に焦点を絞り、「情然」からビッグバンに至るまでの世界について考えてみることにしましょう。
ただ、その前に、ここでもう一度、『情然の哲学』の全体の構成を確認しておきたいと思います。わたしの話はもうしばらくのあいだ、「情然の哲学」の内容をベースにしながら展開することになるからです。

『情然の哲学』の核心部分
『情然の哲学』は8章からなっていますが(序章と終章を入れると10章になります)、このなかで最も重要な章は、私見によれば、3章と4章と5章です。なかでも存在論の問題を正面から扱った第3章は際立って独創的であり、わたしのこれまでの話もおおむね、この章の内容をベースにしたものでした。
この章のタイトルは「存在の構造」というものですが、小見出しが21あり、やや入り組んだ論理構造になっています。
それでもいま振り返ってみると、前回までの講座で、わたしは結果的に、この章のちょうど10番目の小見出しのところまで話を進めてきたようです。
念のため、これら10個の小見出しを以下に列挙しておきましょう。
● 点は実在できない
● 観測されることを意識するかのような粒子たち
● 存在するためには量的な広がり(場)が必要
● 絶えずゆらいでいる関係性の場
● 「流れない時間」と「無ではない真空」
● 宇宙誕生の歴史
● 原初の卵・プランク時代と不確定性原理
● 哲学・科学・神学上の根本問題が一元的につながる場
● 永遠のゆらぎ ーー 情然の場
● 情然の場と相似形にある諸思想
わたしの見るところ、「情然の哲学」の核心部分はこの章のなかにあるので、11番目以降の小見出しの内容、すなわちこの章の後半の部分も重点的に扱う必要があります。
そこで早速、今回は、第3章の11番目(「ゆらぎから流れへ」)と12番目(「クオリアと情感性」)の内容をベースにしながら、「情然」以後の世界の様相について考えてみることにしましょう。
「偶然」を担保する「必然」
話をわかりやすくするために、「すごろく」のようなサイコロ遊びを例にとりたいと思います。
すごろく遊びの楽しさは、結果がどうなるかわからないところにあります。サイコロを振っても偶然の事象しかそこには存在しないため、ゲームの結果は最後までわかりません。そのため(狙った結果が意図的に再現できないため)、それは「遊び」になるわけです。
ところが、サイコロの目の出方は、じつは「偶然」だけではありません。目の出方はどれも一様に「確からしい」(中学で学ぶ数学用語)わけですから、確率計算ができます。言うまでもなく、それぞれの目はみな6分の1の確率で出ることになっています。
ただし、すごろく遊びの場合はサイコロを何百回も振るわけではないので、必然よりも偶然の支配が圧倒的です。そのため、この遊びは偶然の連鎖によって進行することになるわけです。
しかしながら、もしもサイコロを6万回ころがすとすれば、それぞれの目はみなほぼ1万回出ることになるでしょう。たとえば、3の目だけが2万回も出てしまう、ということはありえません。同じ理由で、5の目は3千回しか出なかった、ということもありえないわけですね。
つまり、毎回のサイコロの目の出方は完全に「偶然」ですが、サイコロを転がすという試行を6万回繰り返すと、それぞれの目はほぼ1万回に揃うという「必然」が、どこからともなく立ちあらわれてくるわけです。
「情然」の世界について考える場合も、この「サイコロの目の出方」の例は有効です。
「はじめにあったもの」が「情然」の世界であるならば、その世界のなかには偶然の事象しかなかったはずです。なぜなら、「情然」とは「情が情のままにある状態」のことであり、そこにはいかなる「理性」もなければ、いかなる「意志」もないからです。
ではここで、理性も意志ももたない「純粋な感情」とでもいうべきものをイメージしてみましょう。
そのような無垢なる感情が、世界以前の世界に存在していたと仮定します。世界以前の世界とは「情然の世界」ですが、その世界のなかに「情」を本体とする、「物」でも「霊」でも「魂」でもない生命体が存在していたとイメージするわけです。
もちろんこの生命体は、「神」ではありません。また、スピリチュアルの書物などに出てくるような「宇宙意識」でもありません。老子はそれを、「名づけようのないもの」と言い、必要に迫られて「タオ」と名づけましたが、わたしたちはここで、このような原初的な生命のことを「純粋感情」と呼ぶことにしましょう。
ただ、「純粋感情」ではいまひとつイメージがしづらいので、ここではこれを、姿のないアメーバのようなものと考えることにします。
このアメーバに、「親」はいません。この生命体は「はじめにあったもの」ですから、はじめから「いた」のです。聖書の言葉を借りて言うなら、これは「あってあるもの」とでもいうべき存在で、「なぜいるのか」ということを問うことはできません。
ここで、この生命体の存在を哲学的に考えてみましょう。
はたしてこの生命体は「存在している」と言えるのかというと、じつは言えません。その理由は、わたしが思うに二つあります。
一つは、その生命体が存在していることを認識し得るほかの存在がないからであり、もう一つは、その生命体自身も自分の存在をまだ自覚していないからです。
このように考えてみると、この一匹の姿のないアメーバは、必ずしも「存在している」わけではありません。しかしながら、この生命体はのちのち、堂々たる存在者(もしかすると「神」)に成長するわけですから、「存在していない」と言うこともできません。
そこでわたしは、このような原初の生命体のことを、「有と無の未分化の状態にある存在」と考えることにしています。
このアメーバは、今の時点では、存在とは言えない存在形式で存在している存在ですが、その本体が「情」であるため、「情然の海」のなかで、ただじっとしているわけではありません。
「動かない情」というものは、そもそも情ではないので、この一匹のアメーバは、時間も空間もない世界以前の世界を、あたかもクラゲが泳ぐように、ゆらゆらと泳いでいたのです。情の揺らぎのままに、ただゆらゆらと揺らいでいたのです。
そこにはただ、「偶然」だけがありました。
しかしながら、このアメーバが泳いでいた「偶然」の世界は、じつは「必然」によって担保されていた世界でもありました。あたかもサイコロが、必然によって担保された偶然の世界を転がっているように。
「情」がもっている普遍的な性質
偶然と必然の問題は、『情然の哲学』のなかでも重要なテーマとして扱われていますが、ここでは思弁的な議論を避けて、アメーバの「身の上話」を続けることにしましょう。
情然の海のなかを「純粋感情」が揺らいでいると仮定した場合、どのような事象が生起することになるでしょうか。
「情」がもっている本来の性質から推し量ってみると、この原初のアメーバは、揺らぎながら何かを感じていたと考えられます。なぜなら、情の働きとは本来、「感じる」ところにあるからです。「感」と「情」は非常に近い関係にあるため、わたしたちも日ごろの生活のなかで、感情という言葉を頻繁に使っています。感情という言葉もあるし、情感という言葉もありますね。
では、そのアメーバはいったい、揺らぎながら何を感じていたのでしょうか。
答えは簡単です。
自分自身の「ゆらぎ」を感じていたのです。
その時点においてアメーバの「外」の世界がない以上、それ以外に感じるものはありませんから。
ここで、このアメーバの「スペック」について考えてみましょう。
わたしたちの心をエーテルのように満たしているものは、おそらく、純粋感情というべきものです。
だとすれば、自分の心を標本にして考えてみれば、このアメーバの性質もおのずから導き出せることになります。
私見によれば、どうやらこのアメーバには、あらかじめ次の四つの性能が備わっていたようです。
● 自発性
● 受容性
● 指向性
● 結合性
上記の四つの性質について、簡単に説明しておきましょう。
「自発性」については、あまりにも自明なので説明の必要はないでしょう。「純粋感情」を束縛する外部の何者も存在しないわけですから、このアメーバは、自由気ままに「情然の海」を漂っていたのです。
「受容性」については、「感じる」という働きの性質について考えてみれば、おのずからわかりますね。
わたしたち人間は、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚を持っていますが、たとえば、目はつねに何かを見ているし、耳はつねに何かを聞いています。見たり聞いたりする意思がなくても、何かが見えているし、何かが聞こえています。人間の感覚器官には受容性が備わっているため、とくに意識しなくても、外部の世界の情報を認識することができるわけです。
「感じる」ということはかならず、「何か」を感じるわけですから、わたしたちはその時点ですでに、対象物から何かしらの情報(より直接的には「クオリア」)を受けとっていることになります。たとえば、人間の肌は触覚の受容器ですが、何もさわっていないときにも空気には触れており、空気の温度や湿度を感じています。暑さや寒さを感じているのは肌そのものではなく「情」なので、「情」には本来、対象物に対する「受容性」があると考えられるわけです。
「指向性」については、「不快を避けて快を求める性質」と捉えれば、すぐに理解することができるでしょう。
わたしたち人間の幸福の指標の一つに、「快適な暮らし」というものがあります。「情」にはもともと「快」を指向する性質があるため、わたしたちも常日頃、大きなことから小さなことに至るまで、不快を避けて快を求める行動をとっているのです。
「結合性」については、この性質を「関心」や「欲求」ということばに置き換えて考えてみると、わかりやすくなるでしょう。関心や欲求という心の働きのなかには、もちろん理性や意志も含まれますが、その原因的な要素が「情」のなかにあると考えるわけです。
「快」を求める「情」は、自分に「快」を与えてくれる対象物と関係をもつことを欲するようになります。簡単にいうと、それが「欲しくなる」ということです。
たとえば、欲しいと思っている高級車を購入すれば、自分はその車に乗れるようになります。対価を払うことで、自分と車との独占的(排他的)な関係が自分の権利として成立するわけです。
「なぜあなたはその車を買ったのですか」と、誰かがその人に聞いたとすれば、その人はきっと、「欲しかったから」と答えるでしょう(移動のために車が必要だったのであれば、わざわざ高級車を買う必要はありませんね)。
なぜ欲しくなったのかというと、その車が自分に特別な「快」を与えてくれそうに思ったからです。そのため、この人はその車に関心を持ち、その関心が深まるにつれてそれは欲求となり、ついには購入に至ったわけです。
もちろん、車に限らず、市場に出回っているすべての商品において、人は自分に「快」を与えてくれそうなものに関心を持ち、それがやがて欲求となり、購入に至ります。すでに述べたように、「情」は「感」とも深い関係がありますが、「欲」とも深い関係があります。では、感情や情感と同じように、欲情や情欲ということばがあるでしょうか。
もちろん、ありますね。
「人間は感情の動物だ」とよく言われるし、「世の中は色と欲だ」ともよく言われます。
「情」のなかに「結合性」があるからこそ、わたしたち人間は自分に「快」をもたらしてくれるものに関心をもち、所有したいと思うのです。所有こそ、欲求の充足であり、結合願望の実現ですから。
「情」の性質としての「結合性」については、もう一つ例を挙げておきましょう。
「情」がもっている結合性の最も端的な例は、若い男女の恋愛かもしれません。
「恋は盲目」と言いますが、「情」のもっている結合性があまりにも強くなると、理性のブレーキすら効かなくなってしまいます。
近松門左衛門(1653年~1725年)の『曽根崎心中』など、江戸時代には若い男女の心中劇がはやりましたが、「かなわぬ恋ならばいっそ心中を」というところが、人々の涙を誘ったわけです。
また、突然別れ話を切り出されて逆上し、恋人を殺害してしまうという事件もあとをたちません。これなども、「情」のもっている結合欲求がいかに強いかということを証左する事例でしょう。
以上、「情」がもっている普遍的な性質について考えてきましたが、「情然の海」のなかを揺らいでいる「純粋感情」もまた、上記のような性質を持ち合わせていたと考えられます。
ゆらぎから流れへ
まだ「心」をもたないアメーバが「情然の海」のなかを揺らいでいるとき、この生命体は完全な眠りの状態にあったわけではありません。
アメーバは揺らぎながら、自分自身の揺らぎを感じていたわけですから、少なくとも自分の揺らぎの緩急は感じ取っていたと考えられます。
そうなると、このアメーバのなかには、さまざまな質感の記憶が蓄積されることになります。
「純粋感情」のなかに多様な質感の記憶が蓄積されると、似たような質感はたがいに結びつき(「情」には結合性がありますから)、最終的には一つのテリトリーを形成するようになります。
「類は友を呼ぶ」ということばがあるように、同類のものは自然に集まるようになるわけです。
このあたりの事柄については、色彩を例にして考えてみるとわかりやすいかもしれません。
たとえば、白と黒をイメージしてみましょう。
白と黒の間には、灰色があります。
灰色は無段階に存在していて、白と黒をつないでいます。グラデーションというやつですね。
「純粋感情」が受容していた自身の揺らぎの質感も無段階のものであったはずですが、このグラデーションを一つの数直線として考えてみると、左の端には白があり、右の端には黒があったはずです。
もちろん、白も黒も灰色も、すべて「自分」です。
すべて「自分」なのですが、あるときは「白」が「快」に感じられるので「白」のところに行ってみると、「あなた」(「遠方」を意味する古語)には「黒」があります。また、あるときは「黒」が「快」に感じられるので「黒」のところに行ってみると、今度はいまの自分とは対極の場所に「白」があります。
「白」と「黒」は無段階の灰色でつながっているため、アメーバは両極の間を自由に移動するようになり、「揺らぎ」はやがて、「泳ぎ」に進化するようになったと考えられます。
「情然の海」のなかに白と黒の極性が生まれたため、「揺らぎ」のなかから「泳ぎ」が生まれてきたわけです(揺らぎも揺らぎのまま存在し続けます)。
もちろん、ここでいう「泳ぎ」は一つのたとえですから、これを普遍的なことばに置き換えると、「流れ」ということになります。
「揺らぎ」のなかには「偶然」しかなかったのですが、そこから「流れ」が生まれたのは、じつは「必然」でした。
「偶然」と「必然」は相互補完的な概念ですから、どちらかしか存在しないということはありません。原初の世界においても、やはり事情は同じだったと考えられます。
サイコロが転がるときと同じように、この姿のないアメーバも、必然によって担保された偶然の世界を揺らいでいたのです。
以上のわたしの話を念頭において『情然の哲学』(とりわけ第3章の前半部分)を読んでみると、この哲学の奥の深さがより明快に理解できるようになるかもしれません。
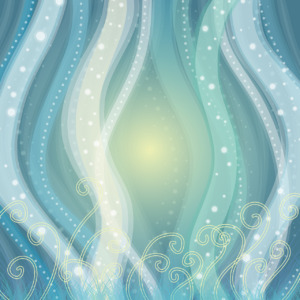
情然の場にあらわれた陽陰の極性
最後に今回の話をまとめつつ、次回の予告をしておきましょう。
わたしたちが日ごろ当たり前のように思っていることも、その成立の根拠について考えてみると、途端にわからなくなってしまう事柄があります。
たとえば、磁石のN極とS極は引き合います。また、正しい配線の回路に電池をセットすると、その回路には電流が発生し、豆電球が点灯したりします。
これらの例は、小学校で行う理科の実験でお馴染みのものです。
ところが、小学校の理科の授業で、「そもそもプラスとマイナスはなぜ引き合うのだろうか」という問題が立てられたとすると、生徒はもちろん、教師ですら答えることができません。教師どころか、物理学の専門家ですら答えることができないでしょう。
なぜかというと、物理学の世界のなかに「なぜ」を問う発想がないからです。
ところが、「情然の哲学」の見地に立つと、このような問題にも答えが出せるようになります(正解かどうかは別として、少なくとも答案が書けるようになるということです)。 たとえば次のように。
「先生、その問題、僕にはわかります。プラスとマイナスはなぜ引き合うのか。それは、世界の根源が情然だからです。情には受容性や指向性や結合性があるので、プラスとマイナスは必然的に引き合うのです」
こんな小学生はもちろん実在しませんが、わたしがもしも数十年前の世界にタイムトラベルすることができれば、そのように答えることでしょう。もっとも、「プラスとマイナスはなぜ引き合うのか」などという哲学的な問題を小学校の教師が話題にすることはありませんが。
わたしは今し方、白と黒のたとえを使ってアメーバの成長について語りましたが、これは要するに、東洋哲学で昔から語り継がれてきた、世界の根源としての「陽と陰」の話と同じです。
ただし、これまでの哲学は、「陽陰」の発生の原因までは解き明かしていないので、「情然の哲学」の登場は、今後、人類の思想史に起こった大きな事件として扱われるようになるかもしれません。
「情然の場」に「陽」と「陰」の極性が発生したことは、わたしたちにとって、「どこか遠い世界の出来事」ではありません。
陽と陰の分極現象は、いまでも実際にこの世界の原理として機能しているからです。
たとえば、分子の世界においては、プラスイオンとマイナスイオンのやりとりがあるし、植物の世界においては、おしべとめしべのやりとりがあります。動物においてはオスとメス、人間においては男と女のやりとりがありますね。「男と女のやりとり」がなければ人類は存続できませんから、「陽と陰が分極したうえで相互作用をする」という現象は、この世界の一つの原理であると考えてよいでしょう。
先にも述べたように、「あなた」という古語は「遠方」を意味することばです。
広く知られている一編の詩を紹介しましょう。
山のあなたの空遠く
幸い住むとひとのいう
ああ、われひとと尋(と)めゆきて
涙さしぐみかえり来(き)ぬ
山のあなたになおとおく
幸い住むとひとのいう
(上田敏 訳 出典は「海潮音」)
これは、カール・ブッセ(1872年~1918年)の有名な詩の一節ですが、「陽」にとっては「陰」が「あなた」であり、「陰」にとっては「陽」が「あなた」になります。
もしかすると、妻が夫のことを「あなた」と呼ぶのも、このようなことがらが背景にあるのかもしれません。
今回の話は、このあたりにしておきましょう。
なお、次回の講座は、2ヶ月後の9月初旬に掲載する予定です。
わたし個人の都合で更新を1ヵ月お休みすることになりますが、あらかじめご了承ください。
次回も、アメーバの成長の話を続けます。
陽陰の極性をもった姿のないアメーバは、その後どのように成長したのかという話です。
では、今回の話はこのへんで。





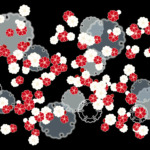
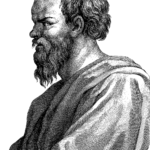


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません