人間学の現在(2)
では、人間学の入門講座に入りましょう。
人間学についてひととおりのことを学ぶためには、やはり初心者向けのテキストを読むことが最適でしょう。どの分野の学問にも、たいていは定番の入門書がありますが、人間学の場合はどうでしょうか。
この件に関してわたしが皆さんに紹介したいのは、菅野盾樹氏(大阪大学名誉教授)の書かれた、「人間学とは何か」(産業図書)という書物です。

この著作は人間学の問題について正面から取り組んでいるもので、この書物が読破できれば、人間学の基本がすべておさえられると考えていいでしょう。
ただし、わたしが思うに、この書物は内容的にかなり高度なものです。
おそらく、すいすい読んでサクっとわかる、ということにはならないでしょう。(学術書としての水準を保持しながら書かれた入門書なので、そんなに簡単なものではありません)。
そこで、この書物のなかで論議されていることを紹介しながら、わたし自身の見解をそれに加えて語ることで、当面、「人間学のわかりやすい話」をすることができたらと考えています。(もちろん、この書物を購入して読んでみるのもお勧めです。機会があったら是非そうしてください)。
人間の類型
ではさっそく、本題に入りましょう。
人間学の論議のなかでよく話題になるのは、人間の類型という問題です。
これは、マックス・シェーラーが提出した問題なのですが、かれによると、人間は五つのタイプに分けられるというのです。
煩雑になるので、その五つのタイプについてここで説明することはしませんが、少し批判的に言うなら、このような問題提起によって、人間学は当初から複雑な問題を抱え込んでしまいました。
たしかに人間にはいろんなタイプがありますが、それを五つの類型に分けるというのはどうなのでしょうか。
もちろん、20世紀の初頭においてはこのような問題提起も意味のあるものでした。何よりも、形而上学が主流だった西洋の哲学の伝統のなかに「人間とは何か」という新しい問題意識を持ち込んだのは、かれの大きな功績ですから。
人間をいくつかの類型に分けて考えることで新たに見えてくる部分ももちろんありましたが、見失ってしまうものもありました。
それで、ここではそのあたりの問題について少し掘り下げてみたいと思います。
人間を類型に分類する意義
まず、人間をいくつかの類型に分類する学説の今日的な意義について。
「ホモ・サピエンス」という言葉は、おそらく読者の皆さんもご存知でしょう。
‟人間の人間たるゆえんはその理性にある”、という考え方です。
これは実は、シェーラーが人間を五つの類型に分類したときの最初のタイプにあたるものです。
人類は一般に猿から進化した種であると考えられていますが、二足歩行と言語の使用が人間を人間たらしめているといわれます。
ただし、言語を操るためには人間の脳のなかに理性がなければなりません。猿は言語を操ることができませんから、理性というほどの理性(抽象思考ができるレベルの理性)はないことになります。そのため、厳密に言うと、人間の脳は猿の脳が「進化したもの」ではないのですが、ここではこのあたりの問題は不問に付すことにしましょう。
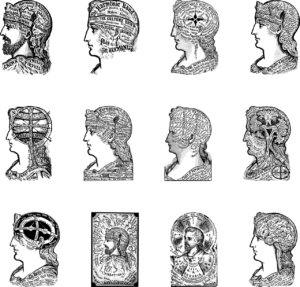
さて、人間には理性があるので言語を生み出すことができました。ですから、人間は理性的な存在であり、ホモ・サピエンスであるというわけです。
言うまでもなく、人類の存続と繁栄にとって「理性」は重要です。実際、西洋の文化的な伝統のなかには常に理性中心主義というものがありました。とりわけ、近代において哲学が神学から分離してからは、西洋の哲学はひたすら人間の理性を信頼してきたと言ってもいいでしょう。イマヌエル・カントの「純粋理性批判」などは、人間の理性の中身を探究した古典的業績であるといえます。
その点において、シェーラーの類型学は人間についての探求をはじめるにあたっての格好の契機となりました。これが、シェーラーの仕事の今日的な意義の一つだといえるでしょう。
「実存」の概念の目覚め
ところが、人類は20世紀に二つの大きな戦争を経験しています。この歴史的な事実が暗に語っているのは、人間は理性的な存在であるとともに非理性的な存在でもあるということです。アルベール・カミュは、歴史の重大な局面において非理性的な決断をする人類を「不条理」という概念で考察しましたが、カミュによれば、人間は理性的な存在であるとともに不条理の存在でもあるのです。
西洋の哲学は、19世紀に入ってから「実存」の概念に目覚めます。ひとはそれぞれ独自の存在ですから、人間に関する抽象的な思考には限界があるというわけです。ちなみに、実存主義の先駆者としてはキルケゴールとニーチェが有名ですが、この二人の著作は生前はあまり注目されませんでした。
われわれ人間はそれぞれ、とりかえのきかない個人として世界に対峙しています。人間のこのような存在のあり方を鋭く意識した実存主義は、サルトルに至って簡潔な定義を獲得します。「実存は本質に先立つ」という定義ですね。人間学は人間の本質について模索してきましたが、サルトルによれば、本質の前に実存がある、というわけです。哲学的人間学は実存主義と遭遇することで、その根底に揺さぶりをかけられ、またそれによって大きく飛躍することができたといえます。
サルトルの死去とともに実存主義の流行は退潮しますが、20世紀の後半にあらわれた構造主義は、実存主義の流行を凌駕するものとなりました。
こちらはひとつの思想というよりも、広い分野に応用することのできる方法論です。ソシュールの構造言語学が発端となって多くの人に知られるようになりましたが、人間学の研究者たちもこの思想と無縁であったはずはありません。さすがに「構造人間学」といったものはあらわれませんでしたが、西洋哲学が暗に前提としていた人間中心主義が批判されることで、人間学の根底が再び揺さぶられ、人間に対する概念を更新させられることになったわけです。
こうして、実存主義と構造主義を通過したあと、人間学は独自の領域を形成することになります。
当学会が研究しているのもそのような「現代の人間学」ですが(これに対し20世紀までの人間学は古典的人間学と考えてよいかもしれません)、「現代の人間学」を把握するための代表的なテキストとして、前述の「人間学とは何か」があるといっていいでしょう。
では、菅野氏は、シェーラーの提起した「人間の類型」についてどのような見解をもっているのでしょうか。
次回の講座では、このあたりのことについて話してみましょう。







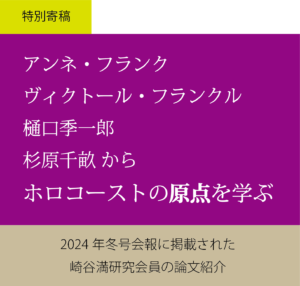






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません