文学と人間学 第4回
前回の講座では、前期三部作の『三四郎』に注目し、「自我と他我」、「男と女」という二つのテーマが漱石文学の根幹にあることを確認しました。若者の自我が目覚める瞬間、そこには必ず他者の存在が影を落とし、往々にして男女関係が決定的な役割を担う。こうした構図は漱石文学全体を貫くものでした。
今回はその続きとして、三部作の次の二作(『それから』と『門』)を取り上げます。いずれも「愛と責任」を正面から描いた作品であり、近代的自我が避けて通れない倫理問題が鮮明に浮かび上がります。
『三四郎』では、「これからの人生をどう生きるか」という問いが前景化しましたが、『それから』と『門』では、「選択した人生をどう引き受けるか」という問いが中心になります。つまり、「自我の目覚め」から「自我の帰結」へと作品の主題は深まっていくのです。
生涯を通じて作品の主題を深めることのできた作家はむしろ珍しいので、このようなところにも漱石文学の魅力があるといえます。
本稿では、『それから』と『門』の二つの小説を比較しながら、漱石が提示した「愛の倫理」や「責任の重み」といった主題を読み解き、そこに描かれる人間関係の葛藤をさらに掘り下げてみたいと思います。
『それから』/愛と責任の交差点
『三四郎』が、近代的な自我に目覚めつつある若者の、初々しくもどこか危うい青春を描いた作品だとすれば、『それから』は、その延長線上にあるより深刻な「愛」の問題を描いた作品です。
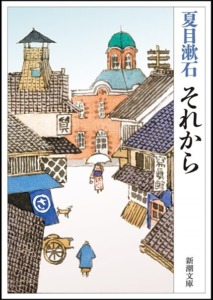
主人公の長井代助は、裕福な実家からの仕送りに頼り、定職を持たず、気ままな生活を送るインテリ青年。彼は旧友である平岡の妻、三千代に密かに想いを寄せていました。三千代はかつて代助の妹の同級生で、代助自身も彼女に特別な感情を抱いていましたが、平岡に譲るかたちで二人の結婚を許してしまった過去があります。
この設定自体、すでに「自我」と「他我」の葛藤、そして「男と女」の複雑な関係を予感させます。代助は自分の本当の気持ちを抑えて社会的な体裁を保とうとするのですが、三千代と再会し彼女が夫との関係に苦しんでいることを知ると、彼の心中の葛藤は一気に噴き出します。
そして、代助は三千代に愛の告白をし、彼女もまたそれを受け入れます。しかしながら、この愛は社会的に許されないものです(なぜなら三千代は人妻、しかも友人の妻ですから)。そのため二人の関係は、彼らの家族や周囲の人々との間に大きな波紋を広げることになります。
そしてその結果代助は、実家からの経済援助を打ち切られ、社会的な立場も失うことになったのでした。
この作品で漱石が描きたかったのは、単なる恋愛物語ではありません。それは、「真実の愛」が社会の倫理や秩序とぶつかったとき人はどう行動するのかという、より根源的な問いがそこにあるのです。
代助は、自分の内なる声に従い、社会的な立場を捨ててまで三千代との愛を選びます。ところがその先に待っていたのは、幸福な未来ではなく、経済的な困窮と周囲からの孤立でした。
第三者の立場からすれば、「やめときゃいいのに」と思うところですが、男女の愛はときとしてこんなかたちでわたしたちの人生に訪れるものです。
そのため、わたしたちは二人の愛のゆく末を安易に傍観することはできないでしょう。
この物語の結末は、決してハッピーなものではありません。代助は三千代を連れて街を歩きながら、打開策の見つからない無力感にさいなまれます。父親に勘当され援助を断たれた彼は生活の不安と向き合うことになったからです。
彼の選択は、みずからの信念を貫いた結果でもあります。社会的な規範よりも自分の心の真実に従うこと。これはこれで、勇気ある一つの生き方だといえます。ところがその代償として、彼は大きな苦悩を背負うことになってしまったのでした。
人間学の観点から見ると、この作品には、「個人の自由と共同体の倫理の相剋」というテーマが見てとれます。漱石は、「真実を求めて生きた青年の苦悩」という近代のアイロニーを追求したわけです。
そしてこのアイロニーは、現代を生きるわたしたちにとっても無縁のものではありません。たとえば、「自分らしく生きる」というスローガンは魅力的ですが、それが他者や社会への責任とどう折り合うのかという問題に関しては、今の時代においても答えはありません。
そうした意味で、『それから』は、個人と社会の相克の典型劇をわたしたちに示してくれているといえるでしょう。
『門』/愛の結末と救済への希求
次に、前期三部作の最終作である『門』について見ていきましょう。
この作品では、『それから』で描かれた愛の結末がより深い苦悩として描かれます。
主人公の宗助は、『それから』の代助と同じように、友人の妻であったお米を奪って結婚します。
彼らの愛は成就しましたが、その代償として、宗助は友人との友情、そして社会的な地位を失いました。
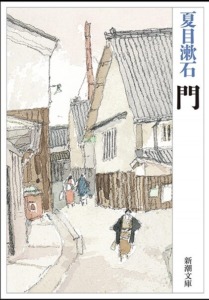
宗助とお米は二人だけの世界で静かに暮らしていますが、その愛はどこか閉塞的で、重苦しい空気に包まれています。
彼らは過去の罪から逃れることができず、常に罪の意識に苛まれているのです。
この作品では、すでに「愛」が成就した状態から物語がはじまりますが、その愛が彼らに幸福をもたらしたかというと、そうとは言えません。むしろその愛こそが、彼らを世間から孤立させ、精神的に追いつめる原因となっているのです。
この苦しみから逃れるために、宗助は禅寺を訪れ、参禅の修行に励んだりもします。そこで彼は僧と会話を交わしますが、明確な救いは与えられません。むしろ、静寂と沈黙のなかに彼の苦悩は深まるだけです。厳しい修行の末に彼が得たのは悟りでも救済でもなく、自身の罪と向き合うことの厳しさでした。
物語の末尾では、修行に見切りをつけた宗助が山を下り、日常の生活に戻る場面が描かれます。彼は宗教的な救済を断念し、お米と共に苦悩を抱えながら生きていくことを再び選んだのでした。
漱石は、愛によって生じた苦悩は愛によってしか解決できないという、人生の厳しい一面をわたしたちに示そうとしたのかもしれません。
宗助は温厚で誠実な人物ですが、心の奥には拭えぬ不安があります。その不安が「門」という象徴的なモチーフを生み出します。門は閉ざされ、彼はその内側で苦悩し続けるのです。
『それから』と『門』/それぞれの愛と責任
ここで二作を比較しながら、この時期の漱石文学の主題について考えてみたいと思いますが、その前に、それぞれの作品のあらすじを把握しておきましょう。
まずは、『それから』のあらすじです。
主人公の長井代助は、30歳になっても定職に就かず、実業家である父や兄からの援助で生活を送る、いわゆる高等遊民です。彼は自身の肉体や感性に誇りを持ち、労働や社会活動を「堕落」と見なす独自の哲学を持つ人物でした。
ある日、代助のもとに中学時代からの旧友である平岡常次郎が、3年ぶりに東京へ戻ってきたという知らせが届きます。平岡は銀行を辞職し、妻の三千代と共に新たな職を探している状態でした。三千代は、かつて代助と平岡の共通の友人であった亡き菅沼の妹であり、代助自身が平岡との結婚を斡旋した過去がありました。
再会した代助は、生活に苦しみ、精神的にも追いつめられている平岡夫婦、特に心臓を患いはかなげな三千代の姿に心を痛めます。三千代が一人で代助のもとを訪れ、借金返済のための金の工面を頼んだことをきっかけに、代助は彼女への特別な感情を自覚しはじめます。
一方で、代助は父から、家のために恩義のある佐川家の娘との縁談を強く迫られていました。父や兄、嫂は、代助の生き方を案じ、結婚によって彼を社会的な安定へと導こうとしますが、代助は家族の価値観との間に深い溝を感じ、苦悩します。
三千代への抑えがたい愛情と、家族や社会からの圧力との間で引き裂かれた代助は、ついに三千代を自室に呼び、自身の想いを告白します。「僕の存在には貴方が必要だ」という代助の言葉に、三千代もまた涙ながらに彼への想いを打ち明け、二人は「覚悟を極めましょう」と、社会の道徳に背くことを決意するのでした。
この決断の結末として、代助は父に縁談を正式に断り、勘当を言い渡され、一切の経済的援助を絶たれます。さらに、この関係を知った平岡は代助の父に手紙で事実を告発し、代助と絶縁します。社会的にも経済的にも完全に孤立した代助は、「職業を探して来る」と言い残して炎暑の街へ飛び出します。彼の精神は極度の緊張から平衡を失い、街中の赤いものが頭の中で渦を巻く幻覚を見ながら、狂気の世界へと足を踏み入れていくところで物語は終わります。
なかなか興味深いストーリーですね。
次に、『門』のあらすじを見てみましょう。
この作品は、役所勤めの野中宗助とその妻・御米が、世間から身を引くように静かに暮らす日常と、彼らが抱える過去の影を描いた物語です。
穏やかながらもどこか停滞した夫婦の生活は、宗助の弟・小六(ころく)が学資の援助を叔母から打ち切られ、彼らのもとを頼ってきたことから動きはじめます。宗助は、亡父の財産処理を巡って不信感を抱く佐伯の叔母一家と対峙しますが、問題は解決せず、結局小六を家に引き取ることになります。これにより、二人きりだった夫婦の静かな生活に波紋が広がります。
そんななか、崖の上に住む裕福な家主・坂井の家に泥棒が入った事件をきっかけに、宗助はこれまで没交渉だった坂井と親しくなります。しかしある晩、坂井との会話のなかで、宗助と御米の過去を決定づけた人物である「安井」が、坂井の弟の友人として満洲から来ており、近々訪問するという話を偶然耳にしてしまいます。宗助は、かつて安井を裏切る形で御米と結ばれ、その結果として学校や社会から追われたという過去を持っており、予期せぬ再会の可能性に激しく動揺します。
精神的に追いつめられた宗助は、救いを求めて鎌倉の禅寺へ赴き、坐禅に打ち込みます。しかし、「父母未生以前本来の面目」という公案に苦しみ、心の安らぎを得ることはできません。結局、自分は悟りの「門」の前で立ちすくむしかない不幸な人間だと自覚しただけで、山を下りることになります。幸い、東京に戻ると安井はすでに満洲へ帰っており、当面の危機は回避されていました。小六の身の振り方も決まり、宗助の給料もわずかに上がるなど、夫婦の生活には束の間の平穏が訪れます。
しかし、物語は、うららかな春の日差しのなかで宗助が「またじき冬になるよ」と呟く場面で締めくくられ、根本的な問題が解決されないまま、彼らの静かな不安が続くことを暗示しています。
以上、二つの作品のあらすじを見てきましたが、どちらの作品も読んでみたくなるような話ですね。
『それから』と『門』を比べてみると、どちらも、男同士の友情と男女の愛、それに社会の規範と金銭の問題が絡みながら物語が展開しています。
しかしこうした共通点を持ちながらも、二つの作品は対照的であるともいえます。
漱石は、この二作のそれぞれの主人公の性格を巧みに書き分けているのです。
『それから』の主人公は、友人から女を奪うという行動には出ますが、妻を扶養する責任は果たしていません。また『門』の主人公は、友人から奪った妻を扶養する責任は果たしていますが、罪責に囚われ続ける男として描かれています。
愛で結ばれたものの責任が果たせない、というのが『それから』の世界であり、責任は果たしているが罪の意識から逃れられない、というのが『門』の世界なのです。
愛は常に責任を呼び込み、責任は愛を試練にかける。漱石文学は、こうした人間世界の実相を精緻に描いた点で、まさに人間学の第一級の資料に値するといえます。
実際、漱石が作品のなかで追求したこのような問題は、いまの社会においてもさまざまなかたちで再現されています。
『三四郎』と『それから』と『門』は、三部作と言われるだけあって、書かれた順に読んでいくと作品世界の深まりがよくわかり、充実した読書体験を得ることができます。
人物の配置や会話のやりとりなども適切で、飽きずに読み進められるプロットが仕組まれているのも、漱石作品の魅力の一つでしょう。
前期三部作から後期三部作へ
今回は、『それから』と『門』を通して「愛と責任」、「自我と共同体」、「罪責と日常」といったテーマについて考察してみました。
個人の自由を追求するだけでは幸福に至れないこと。また、責任を受け入れるだけでは救済が得られないこと。
こうした人間の不完全さをリアルに描くことで、漱石はわたしたちに人生の根本問題を開示してくれているのです。
では、「前期三部作」を書き終えた漱石は、そこからさらにどのような作品を書いていったのでしょうか。
ご存知の方も多いかと思いますが、「前期三部作」のあとには「後期三部作」が続きます。
後期三部作とは、『彼岸過迄』、『行人』、『こころ』の三つの作品です。
これらの作品において、漱石は、『それから』と『門』で展開した「自我と他我」の問題をさらに深めていきます。
ただし、このあたりのことについては次回、あらためて話すことにしましょう。
また、後期三部作の擱筆以後、漱石はさらに二つの作品(『道草』と『明暗』)を書いているので、『こころ』から『明暗』に至るまでの道のりも、次回の講座で概観してみたいと思います。
とくに、『こころ』と『明暗』は漱石文学の集大成であると同時に、日本の近代文学全体を代表する名作です。そのため、次回の講座では、この二つの作品に注目してその文学の核心に迫ってみたいと思います。
では、今回の話はこのへんで。
 関根 均 (せきね ひとし)
関根 均 (せきね ひとし)
1960年生まれ。 慶応大学卒業。専攻は国文学。2010年日本人間学会に入会。現在、研究会員として人間学の研究に取り組んでいる。
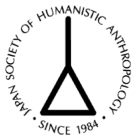



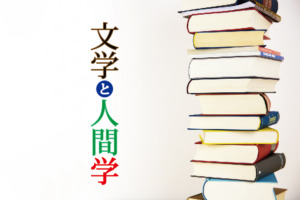

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません