人間学の現在(7)
前回は人間学を学ぶ意義について考えてみましたが、今回は「人間学に公理はあるか」という問題について考えてみましょう。
人間の初期設定
わたしたちは普段、自分が人間であることを意識しているわけではありません。また、人間にはいくつかの「初期設定」があるということにも、とくに意を払って暮らしているわけでもありません。
それらのこと(たとえば自分が日本人であり男性であること)は自分にとって当たり前のことですから、あらためて意識することなどないわけです。
しかし、人間の存在について少し丁寧に考えてみると、人はそれぞれいくつかの初期設定を経たうえで生まれていることがわかります。
私見によれば、それは次のようなものです。
-
- 特定の個性が与えられていること
- 特定の名前が与えられていること
- 男性、女性のいずれかの性が与えられていること
- 特定の家庭のなかに生まれていること
- 特定の国のなかに生まれていること
- 特定の地域(自然環境)に生まれていること
- 特定の時代(歴史環境)に生まれていること
- 誕生と死によって人生が明確に区切られていること
これらの条件は、自分がこの世に生を享けたときにすでに確定しているものであり、自分の力で変更できるものではありません。
しかし、たとえばパスカルが「人間は考える葦である」と言ったように、これらの条件について思索することはできます。どうして(何のために)このような初期設定があるのだろうか、と考えてみることはできるわけです。
この場合、考え方は大きく分けて二つあります。ひとつは、「偶然そうなっている」というものであり、もう一つは、神(もしくは神のごとき超越的な存在)が人間をしてそのような存在にあらしめている、というものです。
ただし、「偶然そうなった」と考えると、その先は思索のしようがありません。人類の誕生に偶然以外の因子が働いていないとするならば、わたしたちは今後も永遠に偶然性のなかをさまよう以外にないからです。
では、人間の初期設定というものは、何がしかの超越的な存在が世界の創造の際に定めたものなのでしょうか。
こちらの考え方は「神の創造論」として古くから存在し、今もなお多くの人々に支持され、信じられています。
神の創造論を最も厳密に考えてきた宗教といえば、やはりキリスト教でしょう。
この宗教には千数百年におよぶ神学の歴史があり、多くの優れた神学者たちが「神の創造」について考察を重ねてきました。
人間というものが結果的な存在である以上、人間学としても「神の創造説」を否定することはできません。ただ、だからといって人間学が神学の枠の中に入らなければならないこともないわけですから(中世のスコラ哲学は哲学の上に神学をおいて世界について考えました)、神の存在を想定しつつも、従来の神学とは別の立場で人間の存在について考える必要があるのではないかと思います。
人間学に公理はあるか
では、人間の初期設定の考察から一歩進めて、人間学の公理の問題について考えてみましょう。
人がそれぞれの人生を出発するに際し、誕生の時点でいくつかの「初期設定」を経ていることについては、今しがた確認しました。
では、そのような人間の存在に「公理」と言うべきものはあるのでしょうか。
人間存在の公理(誰にでも当てはまる普遍的な事実)と言えば、次の三点はすぐに考えられるでしょう。
-
- 直立二足歩行
- 言語の使用
- 道具の使用
ただし、上記の三点について研究するのはむしろ人類学なので、ここでは人間学の立場から、人間存在の公理について考えてみたいと思います。
私見によれば、わたしたち人間の世界には、いくつかの公理が存在しています。それはたとえば、次のようなものです。
-
- 個人として生きる存在であること
- 社会との関わりのなかで生きる存在であること
- 二性のうちの一性として生きる存在であること
- 哺乳類として生きる存在であること
- 理性を持つ存在であること
- 喜怒哀楽の感情を持つ存在であること
- 自由意志を持つ存在であること
- 言語や記号を操る存在であること
- 文化・文明を持つ存在であること
- 闘争の歴史を持つ存在であること
- 幸福な境遇を希求する存在であること
- 神についての思考を有する存在であること
これらの項目はみな、わたしたちにとって当たり前のものですから、解説は不要でしょう。
ただ、「哺乳類として生きる存在であること」については、ここで若干掘り下げておく必要があるかもしれません。
特別な哺乳類としての人間
人類が最後の哺乳類(いちばん新しい哺乳類)として地上に出現したのは、生物学的な事実ですね。
人間以外の哺乳類といえば、身近なところでは犬や猫などがいますが、海のなかを泳いでいるクジラやイルカも哺乳類であり、また、近年のコロナ騒動でにわかに注目を浴びることになったコウモリも哺乳類です。
海にも陸にも空にも哺乳類は存在し、その生存の形態も様々ですが、胎生という点では共通しています。
では、わたしたち人間が哺乳類でなければならない理由はあるのでしょうか。それとも、わたしたちは「たまたま」哺乳類として存在しているだけなのでしょうか。
先にも述べたように、人間存在に普遍的にあてはまる公理というものが生物の進化の過程で「たまたま」成立したものであるならば、これ以上何を考えても意味がありません。物事の原因を追求する論議のなかで、「偶然そうなった」という見解が出されれば、話はそこで終わるからです。
人間学は人間についての哲学的な論究ですから、ここではひとまず、「何かしらの意味があって人間は哺乳類として存在している」と仮定することにしましょう。
動物学において、人間は哺乳類のカテゴリーに分類されますが、じつはこのカテゴリーのなかには、さらに小さなカテゴリーが存在しています。それは、霊長類というものです。

霊長類というと、サルをイメージする人が多いかと思いますが、すでに絶滅している類人猿などもそうです。わたしたち「現生人類」は、猿人、原人、新人のステップを経てこの地球に出現していることになっていますが、サルとヒトの間に存在するはずの「中間種」は、今では化石としてしか存在していません(たとえば中国の山奥に北京原人の末裔がそのままのかたちでひっそりと生きていたというニュースがあれば衝撃的ですが、そのようなことはまず起こらないでしょう)。
猿よりも進化しているはずの類人猿がなぜ絶滅したのかという問題はダーウィンの進化論では説明ができず、新しいパラダイムの進化論の登場が期待されるところですが、この点についてはここでは不問としましょう。
さて、猿と人間の中間的存在が消滅してしまったため、現在の霊長類はサルとヒトということになりますが、ヒトはサルに比べても何かしら特別な存在のような印象を受けます(ひとくちに進化といっても、人間の場合、進化の次元がほかのものとは異なるような印象を受けます)。
では、サルとヒトではどこがどう違うのでしょうか。
ここでも、人類学的な見地からの考察は省略しましょう。
人間学的な見地(というよりもわたし個人の見地)から見た場合、「人間は一人前の存在になるまでに長期にわたる成長期間を必要とする」という際立った特徴があります。
これには人類の歴史の問題も絡んでおり、たとえば「大化の改新」の頃の日本では、人は六歳になると口分田を与えられ、一人前の大人として扱われていました。とはいえ、人類が今後そのような状態(生まれて数年で大人になる状態)に逆戻りすることは考えられませんから、「十数年におよぶ成長期間」という条件も人間学の公理のひとつに数えてよいと思われます。
ほかの動物たちと比べた場合、わたしたち人間に「特別に長い成長期間」があるというのは、自明の事実ですね。
同じ哺乳類でも馬や鹿などは、生まれてからいくらもしないうちに立って歩けるようになりますが、人間の場合はそうはいきません。生まれたばかりの人間は、歩けないばかりか、生存のすべてを親(または親代わりの人)に依存するしかない存在なのです。
ところが、これまでの人間学では、このような人間に固有の「公理」(人間には長い養育期間が必要だということ)がほとんど考察の対象になってきませんでした。
そのため、本講座では、これまでになかった新しい視点から、「人間」についてあらためて考えてみようと思っています。
とはいえ、その新しい視点というものも、わたしたち人間にとって別段目新しいものではありません。
わたしが現在構想を練っているのは、「家庭という視点から見た新しい人間学の構築」というものであり、ことさらに新奇さを狙ったものではありません。
ただ、これまでの西洋の思想史を振り返ってみると、歴代の思想家が想定していた「人間」は、おおむね個人(しかも成人男性)を標本とした人間のイメージであり、家庭はおろか、人間が「男女」として存在しているという事実もほとんど顧みられることがありませんでした。
多少余談になりますが、この点についてはわが国にも似たような事例があります。
日本の歴史を調べてみると、女性には長い間、参政権が与えられてこなかったことが分かります。
大正時代にはいわゆる大正デモクラシーの風潮が高まり、政府も治安維持法と抱き合わせにしながら普通選挙法を成立させましたが、現在のわたしたちの常識からすると、あれはまったく「普通選挙」といえるものではありませんでした。なぜなら、そこにおいてもやはり女性には選挙権が与えられていないからです。
1925年に成立した普通選挙法は、「25歳以上の全ての男子に選挙権を与える」というものであり、当時においてそれは最大限に民主的な法律でした。しかも、女性の存在を度外視したそのような選挙制度を「普通選挙」と呼んで誰も怪しまなかったわけですから、当時の為政者たちの頭のなかには、男尊女卑の価値観が自明のものとしてあったことが分かります。
わが国において完全な普通選挙が実現したのは戦後になってからで、これには当然のことながら、世界に先駆けて民主主義国家を実現していたアメリカの影響が強くありました。
男女平等の理念は今のわたしたちには当たり前のものですが、人類の長い歴史の尺度から見るならば、この理念もつい最近わたしたちの世界観のなかに入り込んできたものに過ぎないのです。
新しい人間学の構想
家庭の役割を軸に人間存在についての抜本的な考察を行う「新しい人間学」の話は次回からはじまりますが(ただしあと三回はそこに至るまでの予備的な話になります)、わたしたちにとってきわめて身近な「家庭」という言葉も、考えてみると人間に特有な構成の単位であることがわかります。

たとえば、「サルの家族」という言い方はできても、「サルの家庭」という言い方はできませんね。もちろん、何かの物語のなかでこのような言葉が出てくるのであれば、それはサルを擬人化していることになります(たとえばサルの夫婦が会話をするといった擬人化です)。擬人化されたサルは、サルの姿をした人間にほかならないので、やはり「家庭」といえば、わたしたち人間に特有の生活様式と考えられるわけです。
では、「家庭」とはそもそも何なのでしょうか。
これはすぐれて人間学的な問いかけですが、この論題の考察に入る前に、わたしたちは、菅野盾樹氏の『人間学とは何か』に対するひととおりの学びを済ませておく必要があります。
氏の『人間学とは何か』のなかで最も力点が置かれている内容は、「ホモ・シグニフィカンス」という人間観の提示ですが、これは今の時代にふさわしい人間観であるとわたしは思います。
ただし、「ホモ・シグニフィカンス」という用語の意味内容が把握できれば「人間」についての理解が完了するかというと、もちろんそういうものでもありません。
そこで、次回では、『人間学とは何か』の全般的な解説を行い、その次の回では「ホモ・シグニフィカンス」に焦点を絞った解説を行い、最後に全体のまとめとして、菅野盾樹氏の提示した「ミニマム人間学」の功績とそこから新たに生まれる課題について話してみることにしましょう。
そして、そこまでの考察を土台として、「家庭という視点からの新しい人間学」の話をはじめたいと思います。
以上の予定を箇条書きに整理すると、次のようになります。
-
- 8回 『人間学とは何か』について
- 9回 「ホモ・シグニフィカンス」について
- 10回 「ミニマム人間学」について
- 11回 「新しい人間学」の構想について
12回以降は、「新しい人間学」についての具体的な話になります。
更新の頻度は、これまでと同じく月に一度を予定しています。また、月の初旬の更新を予定しています。
日本人間学会がこれまで研究を重ねてきた「新しい人間学」の話がはじまることで、この講座も、そろそろ佳境に入ることになります。
では、今回の話はこのへんで。
次回をお楽しみに。








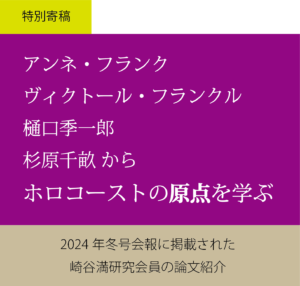





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません