人間学の現在(27)
前回の講座で予告したとおり、今回はおもに、「人間学とは何か」の「影」の部分について話してみたいと思います。
ホモ・サピエンスからホモ・ロクエンス、ホモ・ロクエンスからアニマル・シンボリクム、アニマル・シンボリクムからホモ・シグニフィカンスへと、菅野氏の「ミニマム人間学」の話は進んできました。
そして、菅野氏が3章を割いてホモ・シグニフィカンスの人間観について論じたとき、わたしには、「ここに人間学研究の新しい地平が開かれている」といった思いがありました。
その思いは今も変わっていませんが、この新しい人間の捉え方には、光の部分とともに影の部分もあることが、わたしには当初から漠然とながら感じられていました。
いまのわたしに、その部分を過不足なく語れるかどうか分かりませんが、以下、『人間学とは何か』に見られるいくつかの「脆弱性」について話してみることにしましょう。
ただ、その前に、この書物の周辺的なことがらについて簡単に確認しておきたいと思います。

『人間学とは何か』とその周辺
菅野氏は長年大学の教授職にあったひとですから、当然、いくつかのまとまった著作を執筆しています。
そのうち、出版物として手に入るものには、『人間学とは何か』を含め以下のものがあります。
『我、ものに遭う――世に住むことの解釈学』新曜社 1983年
『メタファーの記号論』勁草書房 1985年
『いじめ=<学級>の人間学』新曜社 1986年
『いのちの遠近法――意味と非意味の哲学』新曜社 1995年
『増補版・いじめ』新曜社 1997年
『人間学とは何か』産業図書 1999年
『恣意性の神話――記号論を新たに構想する』勁草書房 1999年
『新修辞学――反<哲学的>考察』世織書房 2003年
『示しの記号 再帰的構造と機能の存在論のために』産業図書 2015年
ここに紹介した著作リストを眺めてみると、菅野氏は、『人間学とは何か』以外には、人間学を直接のテーマとした著作をほとんど世に問うていないことがわかります。
菅野氏の専門分野は「記号論」ですから、記号論に関する著作が多いのは当然としても、『人間学とは何か』の出版のあと、その著作の続編と言うべきものが見当たらないのは、奇妙といえば奇妙です。
もしかすると、人間学の研究に関しては、その後、捗々しい(はかばかしい)進展がなかったのかもしれません。
また、『人間学とは何か』の反響なり影響なりについて調べてみても、これといったものは見当たりません。
これは笑い話ですが、ためしにホモ・シグニフィカンスという用語を検索してみても、わたしのこのブログが上位表示されてしまうくらいですから。
結局、日本における人間学の研究に関しては、菅野氏の業績を継承した人はいないし、また菅野氏自身も、人間学の研究を生涯のライフワークとして進めてきてはいないことがわかります。
以上のことを念頭におきながら、『人間学とは何か』の「影」の部分について見ていくことにしましょう。
『人間学とは何か』の脆弱性
『人間学とは何か』は十分に立派な書物ですが、この書物を読んでみても、わたしたちのいわゆる「人間了解」が根底から揺さぶられるわけではありません。
そのなかで提起されたホモ・シグニフィカンスなる人間観も、「これで決まりだ」というほどに人間の基本構造を捉えているようには思えません。
たしかに、人間は「記号活動を営む存在」であり、それはそれとして有効な視座ではあるものの、この視座からでは、人間存在のデジタル的な側面しか光が当てられないのではないか、というのが、当初からのわたしの疑問でした。
人間存在の記号的な側面をいくら研究しても、そこから、たとえばクオリアの問題などは解き明かすことができないからです。
わたしは現代の科学には不案内ですが、多くの人が語るように、この世界を量子の集積、あるいは波動の束と捉えることもできるでしょう。
しかしながら、たとえそれが事実であったとしても、量子の集積によって成立しているこの世界にひとはなぜクオリアを感じるのか、という疑問は残ります。
わたしたちは生まれてから死ぬまで、そして朝起きてから夜寝るまで、この世界にさまざまなクオリアを感じつつ生きている存在だからです。
(裏を返すと、わたしたちは日頃の生活のなかで、この世界を量子の集積や波動の束として意識することはありません。)
わたしたちにとってクオリアの問題が瑣末なものであるならば、この問題を丸ごと無視してしまっても差し支えないでしょう。
ところが、ものごとに高いクオリアを求める欲求は、人間が持つさまざまな欲求のなかでもとくに人間らしい欲求のようにわたしには思えます。そのため、人間学としても、この「クオリアの問題」を無視するわけにはいかないのです。
この点に関して身近な例を挙げるならば、たとえば、ある人がレストランに入って食事をし、美味な料理を堪能してしあわせを感じたとします。この場合、その人は、高いクオリアの味覚に満足したことで幸福感を得たわけですから、クオリアの問題は、よりよい人生を求めるひとにとって避けては通れないテーマとして現にあるといえます。
人間の存在を「ホモ・シグニフィカンス」と定義した途端、このクオリアの問題が影の領域に押し込まれてしまうため、わたしの率直な感想を述べるならば、人間はホモ・シグニフィカンスであるとともに何かしらそれ以上の存在である、と言うほかないように思えます。
簡単に言うと、ホモ・シグニフィカンスという定義では、人間存在の基本構造を十分にカバーできないのではないか、ということですね。
これが、わたしが思うところの『人間学とは何か』の脆弱性の一点です。
二点目の脆弱性としては、ホモ・シグニフィカンスの概念が、この書物の後半の各章において十分に生かされていない、ということが挙げられます。
念のため、第7章以降の『人間学とは何か』の各章のタイトルを確認しておきましょう。
第7章 〈人格〉としての人間
第8章 子供と大人
第9章 性を生きる人間
第10章 人生の意味と無意味
第11章 死
たしかに、人間学にとって非常に重要なテーマがここには並んでいます。わたしたちは何よりも「人格」として生きているし、子供から大人へと成長していく存在であるし、男または女として生きる存在であるし、自分の人生に「意味」を感じたり「無意味」を感じたりする存在であるし、また、例外なく死すべき存在でもあります。
ですから、この書物の目次はとても魅力的で、わたしなどは、「どんなことが書いてあるんだろう」という好奇心を大いにそそられたものです。
おまけに、第1章から第6章までは人間学の諸問題に関するスリリングな論議が展開されており、「もしかするとこのなかに人間に関する大いなる真理があるかもしれない」という期待すら抱いてしまうほどのものでした。
ところが、これは実際に読んでみれば分かりますが、ホモ・シグニフィカンスという新しい人間観は、第7章以降の論述に必ずしも役立っているわけではありません。
いや、というよりも、ほとんど役立っていません。
わたしとしては、人間にはなぜ男女の二性があるのか、人間はなぜ子供から大人へと成長する存在なのか、人間にはなぜ死があるのか、といった人間学の根本問題がホモ・シグニフィカンスの視座から明快に解き明かされることを期待していたのですが、結果として、さすがにそれは「期待のし過ぎ」であり「ないものねだり」というものでした。
人間存在の根本問題がホモ・シグニフィカンスの視座から解き明かされるどころか、ホモ・シグニフィカンスとの関連付けすらなされていない状態で7章以降の論議は展開されていたのです。
これが、わたしが思うところの、『人間学とは何か』の二点目の脆弱性です。
しかしながら、わたしはこのことに失望したわけではありません。
ある哲学の脆弱性が認知できるということは新たな研究課題が見つかるということですから、それはそれで意味のあることだからです。
また、菅野氏の「ホモ・シグニフィカンスの人間観」に対しては、「人間の類型学の現代化に寄与した」という評価があるように、それはそれとして、人間学の研究を一歩前に進めたものになっているからです。
ただし、それはあくまでも「一歩」であって、それがすなわち究極の人間観であるとはいえないところに、わたしの「気付き」や「学び」があったことになります。
そのためわたしの人間学研究は、「ホモ・シグニフィカンスの人間観」を踏襲することなく、別のパラダイムを探し求める方向に進むことになったわけです。
とはいえ、わたしたちに新しいパラダイムを提示してくれる包括的な哲学などというものは、そう簡単に世の中にあらわれるものではありません。
それは確かにそうなのですが、わたしの場合には幸運にも、きわめて例外的な事態が起こることになりました。
そこで、少し個人的な話になってしまいますが、ここでちょっと話題を変え、わたしのこれまでの人間学研究の足取りを簡単に振り返ってみたいと思います。

「新しい哲学」との遭遇
思い起こすと、わたしが『人間学とは何か』を熱心に読んでいたのは、2010年から2013年のころまでの期間でした。わたしはこの学会、すなわち日本人間学会に2010年の春に入会していますが、その当時、ある研究会員の方から『人間学とは何か』を勧められ、その書物を手がかりに人間学の学びをはじめたのです。
もちろん、それはそれで有意義な学びでしたが、一方で、「人間についての思索」と「人間学の学び」のあいだには何ほどかの隔たりがあることもわたしは感じていました。
人間学とは本来、人間について深く考えるための学問であるはずのものですから、既存の書物の学び自体が目的となってしまっては意味がありません。ですからわたしは、既存の人間学を学ぶ以上に人間について自ら考えることを心がけていたのですが、そんなわたしに大きな壁となっていたのは、やはり「世界とは何か」という問題でした。
もう少し正確に言うと、今のこの世の中に「正しい世界観」と呼べるものがあるのかどうか、という問題でした。
宗教的な世界観や唯物論的な世界観であれば、たしかに今の世の中にも「それなりに包括的な世界観」がありますね。
たとえばそれは、キリスト教やイスラム教や仏教、あるいは、共産主義に代表される「唯物教」などです。
しかしながら、それらの世界観を背景にして人間について考えてみても、そこから大した人間像は出て来ません。
正直なところ、「まったくわくわくしない陳腐な人間像」しか出てこないのです。「人間に生まれてきてよかった」と思えるような人間像がそこにはなく、「この世界はなぜあるのだろう」という根本の疑問は、いろんな書物を読みいろんな世界観に触れてみても依然として疑問のままでした。
ハイデガーの「世界・内・存在」という術語を引き合いに出すまでもなく、わたしたち人間は「世界」のなかに生きる存在です。犬や猫のような動物であれば「自然界のなかに生きる」と言うだけでこと足りるでしょうが、わたしたちが生きているのは自然界のなかだけではありません。そのため、「世界とは何か」という問いかけが必然的に起こることになります。そして、その問いかけに答えを与えてくれるものが、哲学や思想、あるいは宗教や科学ということになるわけです。
ところが、その頼みの綱もいまや混乱状態。
どの分野のどの説を信じればいいのかさっぱりわからない、というのが、大方の人々の現状ではないでしょうか。
わたしもご多分に漏れず、あたかも漱石の小説の登場人物のごとくさまざまな思想遍歴を経験してきましたが、そんなわたしに一筋の光を投げかけてくれたのが、ある哲学書だったのです。
それはほかでもない、2014年の10月に刊行された『情然の哲学』でした。
人間学研究の新たなステージへ
『情然の哲学』については、わたしのこれまでの講座ですでに詳しく解説してきているので、ここでその内容にあらためて立ち入ることは控えましょう。
この哲学が放つ光のおかげで、わたしには『人間学とは何か』の影の部分が見えるようになり、そしてそれによってわたしの研究も新たなステージにたどり着くことができたのでした。
『情然の哲学』では、世界観に関する次のような課題に明瞭な回答が出されています。
⏺ アルケーの問題
⏺ クオリアの問題
⏺ 自己と他者の問題
⏺ 自己と世界の問題
⏺ 人間存在の基本構造の問題
⏺ 人間の死の問題
⏺ 人間の生と愛の問題
そのため、「情然の哲学」をベースにすることで新しい人間学の構想が可能ではないかとわたしは思い、ここ数年はそちらの方面で研究活動を進めてきたのでした。
では、その新しい人間学のコンテンツとはどのようなものなのでしょうか。
これについては、次の次の講座で話してみることにしましょう。
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
わたしのこの講座は30回をもって終了する予定ですが、次回、すなわち28回の講座では、これまでのわたしの話の総まとめをしようと思います。
そして、29回の講座において「新しい人間学」の構想について話し、最後の講座では、新たな連載の内容について話そうと思っています。
このブログは二カ月に一度の更新なので、28回の掲載が5月の初旬、29回の掲載が7月の初旬、そして最終回の掲載が9月の初旬になります。
11月からはまた新しい講座をはじめる予定なので、どうぞご期待ください。
ちなみに、新しい講座については、そのタイトルだけをいまここでお知らせすることにしましょう。
それは、文学と人間学、というものです。
では、今回の話はこのへんで。
関根 均 せきね ひとし
1960年生まれ。慶応大学卒業。専攻は国文学。2010年日本人間学会に入会。現在、研究会員として人間学の研究に取り組んでいる。






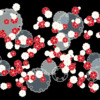



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません