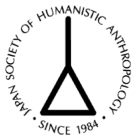日本人間学会の目的と特徴
目的
🔶当学会は、「人間学」の研究の推進とその研究成果の普及を目的とします。
🔶当学会は、人文科学系列、自然科学系列、社会科学系列など、それぞれの専門分野を基礎としながら「人間学」へアプローチする学際的研究を推進します。
🔶当学会は、研究者相互の協力を促進するとともに、国内外の学会および目的を同じくする諸団体と連携しながら、研究成果の普及をもって積極的な社会貢献を目指します。
特徴
日本人間学会は、その名が示す通り人間学を研究している学術団体です。学問というものはそもそも、一朝一夕にして成り立つものではありません。わたしたちの研究においても当然のことながら、永きに渡る学統が存在し、ときには先人の業績に依拠し、またときにはそれを批判的に考察しながら日々の研究が進められています。
では、その先人とは誰であり、当会の学統とはどのようなものでしょうか。
人間を総合的に理解しようとする営み自体は古代ギリシアの哲学、ルネサンスの人文主義、カントの『人間学』など、長い知の系譜に根ざしています。また、「人間学」という語は近年、学問以外の領域でも多義的に用いられています。しかし学術的な文脈でいえば、その現代的な出発点をマックス・シェーラー(1874–1928)の思想に求めることができます。シェーラーは『人間の位置』において、人間を自然や動物との連関のなかに位置づけつつも、精神的存在としての固有性を明らかにしました。20世紀に「哲学的人間学」という新しい学問分野が成立したのは、まさにこのシェーラーの業績に始まるといえます。
シェーラーは、現象学の祖フッサールの影響を受けつつも、独自の哲学的人間学を展開しました。フッサールからハイデガー、サルトル、メルロ=ポンティへと続く現象学の系譜は広く知られていますが、その一方で、シェーラーの思想は心理学者ヴィクトル・フランクルにも深い影響を与えています。わたしたちの人間学は、このような思想的流れのなかに位置づけられるのです。
もっとも、フランクルは哲学者ではなく心理学者であったため、シェーラーの人間学を哲学的に継承したのではありません。フランクルが受け継いだのは、何よりも人間を価値と意味の次元で理解しようとするシェーラーの世界観でした。同様に、当会の創設者である高島博士も、フランクルの思想を医学の領域において発展させ、実存心身医学という独自の立場を築いたのです。

現在の日本人間学会は、高島博士の学説を踏まえながらも、さらに広範囲な思想研究を推し進めることで、人類の未来に平和と発展をもたらすことのできる人間学の構築を目指しています。人間学の源流は西洋哲学ですが、わたしたち日本人は東洋の思想にも親近性をもっているため、西洋と東洋の思想を重層的に捉える立場から、人間の存在を新しい次元において把握しようと努めているのです。
また、当会は、社会貢献の活動に対しても積極的な姿勢を持っています。人間は個人として生きる存在であるとともに、社会のなかに生きる存在でもあります。社会全体が平和と発展の方向に向かわない限り、個人の幸福というものも存在し得ないでしょう。高島博士が折に触れて力説していたように、望ましい人間学はすぐれた実学であるべきであり、またその学説は、世界の平和に貢献できるグローバルなものであるべきなのです。
日本人間学会は、以上のような基本的立場を持ち、またそのような所信に賛同した学者たちによって日々学際的な研究が積み重ねられています。