人間学の現在(15)
わたしたちは今日、スマートフォンやパソコンを当たり前のように使っていますが、このような社会が到来することは、数十年前には(たとえば白黒テレビの登場が世間の話題になっていたような時代には)想像することすらできませんでした。
そんな事実が象徴するように、決して大げさな言い方ではなく、たしかにここ数十年の間、世界は激変してきたといえるでしょう。
時代が進むにつれてさまざまな分野で大きな変化がありましたが、人間学の分野では、わたしが思うに、抜本的な人間観の更新はなかったようです。たしかに文明は長足の進歩を遂げてきましたが(それが必ずしも平和利用されていないことにも問題はあります)、人間はあいかわらず人間であり、科学技術が進歩し暮らしが豊かになっても、人々の考えることはあまり変わっていないのかもしれません。
わたしは前回の講座で、「情然の哲学」を基軸にすえるとそこから新しい世界像が描き出せる、といった趣旨のことを述べましたが、新しい世界像の提示はやはり、現代における人間学の最も重要な課題ではないかと思います。世界観が更新されることによって、新しい人間観の提示が可能になるからです。
先の例にもあるように、文明のほうは予想以上の速度で進歩しているわけですから、人類にはもともとそれだけの可能性があったことになります。人間学の研究を学問の一領域として取り組むと、ややもすると関心が過去の文献にばかり向かってしまい、「人類の可能性」というテーマを見落としがちになります。
大学などで講じられる人間学の講座は、基本的には過去志向のもの(よくいえばアカデミックなもの)ですから、わたしのこの講座は、そうしたものとは一線を画し、どこまでも未来志向のものでありたいと考えています。

では、新しい人間観を探索するための具体的な方法論とは、どのようなものでしょうか。
これについては、すでに明確な答えがあります。
それは、世界のルーツを可能なかぎりさかのぼって考えてみる、ということです(ただしこれは「過去志向」とはまた別のものです)。
そこでわたしたちは、この講座において、究極の「そもそも論」としての「はじめにあったもの」の問題について考えてきたのでした。そして、「はじめにあったもの」とは「情然」ではないか、という仮説を立て、その仮説の有効性について吟味してきたのでした。
そこで、今回は、その話の続き、すなわち「情然」の概念の吟味の続きとなります。前回の講座で予告したとおり、今回は比較思想の観点から「情然」について考えてみることにしましょう。
ちなみに、今回の話の内容は『情然の哲学』の「情然の場と相似形にある諸思想」(第3章)を踏まえたものとなります。
(本講座において「情然の哲学」と表記されているところは情然の哲学の思想内容を指し、『情然の哲学』と表記されているところは情然の哲学の書物を指します。)
聖書が語る世界の成り立ち
「はじめにあったもの」に関する言説で最も有名なものといえば、やはり聖書でしょう。「創世記」の冒頭には、世界の誕生に関する次のような叙述があります。
初めに神は天と地を創造された。
地は混沌として、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。
神は言われた。「光あれ。」すると光があった。
神は光を見て良しとされた。神は光と闇を分け、
光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった。第一の日である。
(創世記1章1節~5節 聖書協会共同訳)
一読すると、これはひとつの神話であるようにも受け取れます。
まるでひとりの人間であるかのような存在として「神」が登場し(このことを「人格神」といいます)、その神があるとき、世界の創造に着手するというわけですね。話としては面白いし、また、誰もが親しめるようなわかりやすい内容です。
ただ、「情然の哲学」の観点から見ると、どうやらここには単なる神話以上のものが示唆されているようです。
引用した聖句の2行目に注目してみましょう。
地は混沌として、闇が深淵の面にあり、神の霊が水の面を動いていた。
宇宙のなかに水がつくられるのは光の誕生以後のことですから、ここでの「水」は、何かの比喩と捉えてよいでしょう。それから、「神」とは言わず「神の霊」と表記してあることにも注意が必要です。
この一文から感じとれることは、「情然」の状態にあった「神」が自己意識をもたない「霊」として混沌とした闇のなかに揺らいでいた、といったイメージです。
これはそのまま「情然の哲学」における「はじめにあったもの」のイメージなのですが、創世記の冒頭にこの謎めいた一文があることにより、聖書が単なる神話以上のものであることをわたしに確信させるわけです。
それから、創世記の記述によると、わたしたちが住んでいるこの世界は7日間で完成したことになっていますが、「7日間」を「7段階」の比喩として解釈すると、現代の科学が解き明かした宇宙の生成過程と驚くほど一致します。このあたりのことから考えても、聖書には何かしらの啓示性があるのではないかとわたしには思えるのです。
聖書については今後、この講座において主題的に扱うことになるかと思いますが(神学と人間学の接点を模索する論議を予定しています)、ここでは聖書と「情然」の接点についての話題だけにとどめておきましょう。
キリスト教と西洋思想
次に、キリスト教と西洋思想の関係について簡単に確認しておきましょう。
西洋の思想のなかには一般に、ヘレニズムとへブライズムがあるとされています。ヘレニズムとは、ギリシア哲学以来の倫理思想の伝統で、人間に与えられた「理性」を基底に据えながら世界を解釈しようとする態度のことです。
一方、ヘブライズムとは、ユダヤ教とキリスト教の流れのなかにある思想の伝統で、こちらは「信仰」を基底に据えながら世界を解釈し、世界と関わろうとする態度のことです。そして、よく言われることですが、ヘレニズムとヘブライズムは水と油のようなもので、原理的に言ってたがいに親和し、融和することはありません。
したがって西洋の倫理思想史について考える場合、歴史に残っている思想家たちが、ヘレニズムとヘブライズムのどちらにより親和性をもっているかを考慮する必要があります。
もちろん、ひとりの思想家においても、生涯のなかでヘレニズムのほうに心が傾いている時期があったり、ヘブライズムのほうに傾いている時期があったりします。
ですから、単純な決めつけやレッテル張りはよくないのですが、「信仰」と「理性」の問題は、キリスト教信仰の根本的な命題であるばかりでなく、哲学者たちの世界観にも常に影響を及ぼしていた問題であったといえます。簡単には解決できない問題であったからこそ、わたしたちもこの問題に留意する必要があるわけです。
古代ギリシアの地に哲学や数学が隆盛したのは、紀元前数百年ごろのことです。ピタゴラスやアルキメデス、それから、ソクラテスやプラトンやアリストテレスが有名ですね。
一方、ヨーロッパのある地域にはイスラエルという名前の民族がおり(この人たちはのちにユダヤ民族と呼ばれるようになります)、この民族を中心としてヘブライズムの思想が形成されるようになります(ヘブライズムとはヘブライ人たちが共有していた世界観を意味しますが、ヘブライ人はイスラエル人の別名です)。
紀元前2000年頃に現れたアブラハムがその起源であり、ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も、アブラハムを起点にもつという点では同じです。
ちなみに、イスラエルという名前は、アブラハムの孫のヤコブが天使から授かった称号です。ただし、そのあたりのことは旧約聖書のなかだけに書かれている事柄ですから、史実として受け止めてよいかどうかは微妙です。
いずれにしても、ヘブライズムの歴史には、アブラハム・イサク・ヤコブ・ヨセフ・モーセ・ヨシュア・サムエル・サウル・ダビデ・ソロモンといった人物が輩出し、そしてその流れのなかから、誰もがよくその名を知っているイエス・キリストが出現するわけです。
それがちょうど、紀元0年のことです(後世の人たちがイエス・キリストの誕生をもって西暦のはじまりと決めたのですから、これは当然ですね。ただし、実際には4年ほどの誤差があるようです)。
ユダヤ教の指導者たちの策謀のため、イエスが十字架上で死を遂げたあと、初代教会の時代にパウロという人物が現れ、キリスト教の教えがギリシアやローマに伝えられることになります。キリスト教の信徒たちは当初、ローマ帝国によって残虐な迫害を受けましたが、4世紀には国家公認の宗教となり、さらには国教にすらなります。そのころ活躍したのがアウグスティヌスで、キリスト教のいわゆる正統の教義は、かれら教父たちの尽力により確立されることになります。

さて、そのアウグスティヌスですが、彼はギリシアの哲学にも通じており、教義の構築にあたっては、新プラトン主義を援用したといわれています(新プラトン主義の解説はここでは省略します)。
キリスト教が国教となってからは、国王と並んで法王(教皇)が強大な力を持つようになり、キリスト教は中世ヨーロッパを席巻するようになりました。そして、その時代はスコラ哲学が思想界を風靡することになります(ちなみに「法皇」は仏門に入った上皇のことで、こちらは日本の話になります)。
「スコラ」は修道院に付属する学校のことですから、スコラ哲学とは、そこで語られた哲学の総称であり、キリスト教の教義を哲学的に裏付けようとしたものです。
もちろん、あくまでもキリスト教の信仰が前提となるので、「哲学は神学の侍女(じじょ)」とされていました。スコラ哲学の代表的な作品は、トマス・アクィナスの「神学大全」です。かれは、アリストテレスの哲学を援用しながらスコラ哲学を大成しました。ここでもまた、アウグスティヌスのときと同じように、キリスト教と西洋思想の関わり合いが顕著に見出されます。
アリストテレスの哲学の全容がヨーロッパに広まったのは、13世紀のことです。両者は地理的にさほど遠くないはずですが、思想の伝播というものは、いつの時代にも、商品の流通などに比べるとはるかに時間がかかるようです。
ここで留意しておきたいのは、中世において勃発した有名な論争です。「唯名論」と「実在論」のぶつかり合いですが、この論争は「普遍論争」と呼ばれ、当時の思想家たちの頭を悩ませることになります(どんな論争であったのかの説明は省略します)。
事実、ここに端を発した論争は長いあいだ決着がつかず、近代に入ってからも、唯名論の思想は大陸の合理論に影響を与え、実在論の思想はイギリスの経験論に影響を与えています。近代哲学の父といわれるデカルトは、合理論の始発点に位置する人ですが、経験論の始発点にはベーコンがおり、合理論と経験論は、今でもわたしたちが普通に用いている思考法(演繹法と帰納法)の源流となりました。
ベーコンは、人間の「知」にとって「経験」は不可欠であるという哲学を主張したので、このあたりの思想から科学が胚胎します。一方、デカルトは、「理性」を「信仰」から切り離すことで近代哲学の基礎を築きました。かれの代表的な著作は、『方法序説』(ただしこれは略称)です。
ここで、トマス・アクィナスの思想を簡単に紹介しておきましょう。
キリスト教では神が世界を創造したことになっていますから、この宇宙は神の作品です。とするなら、自然界を探索することである程度まで神の神性が推測できることになります(これを自然神学といいますが、キリスト教ではその後、この神学は主流の思想にはなりませんでした)。そして先にも述べたように、こちらの立場から科学が生まれ、さらには、人間の生活に利便性をもたらす科学技術が生まれることになります(産業革命がイギリスではじまったのも科学技術の誕生と密接な関係があります)。
また、神は一方で、ご自身の独り子であるイエス・キリストを人類に送り、人類の救済の摂理をなさったばかりでなく、聖書という「神の啓示の書」を人類に与えました。
そのため、自然界と聖書は矛盾するものではないはずなのですが、実のところ、両者の統合はどうしてもうまくいかないのです(これが要するに信仰と理性の問題です)。
ちなみに、テリトゥリアヌスという神学者は、すでに2世紀において、「不合理なるが故に我信ず」といった意味の発言をしていますが、これなども、キリスト教信仰の非理性的な性格を物語るエピソードとして有名です。
そこで、トマス・アクィナスは、自然界のなかに見出される真理(一般啓示)の上に「聖書」(特別啓示)を置くことで、信仰と理性の問題に一応の決着をつけたのでした(ただし一般啓示・特別啓示という術語は近代に入ってから福音派が使いはじめたもの)。
スコラ学のなかで勃発した普遍論争は、先にも述べたように、イギリスの経験論と大陸の合理論というかたちで継続します。そして、この二つの考え方を統合したのがカントの哲学です(カントについての解説は省略します)。
カントとフィヒテとシェリングとヘーゲルは、しばしば、ドイツ観念論というフィールドのなかにカテゴライズされますが、シェリングの哲学は、カントやヘーゲルほど有名ではないものの、かなりの独自性を持っています。『情然の哲学』では、このシェリングの思想をとりあげて「情然」との類似性について言及しています。
近代の哲学はヘーゲルによって大成されますが、ヘーゲルの存在は「情然の哲学」を理解するうえでも重要です(この点についてはすぐあとで話します)。近代の哲学がヘーゲルによって確立したあと、西洋の哲学史は皮肉にも、ヘーゲル批判をバネにして展開することになります(ヘーゲル哲学の功績と課題についてもここでは省略します)。やや大雑把な言い方になりますが、現象学も実存主義もマルクス主義も、ヘーゲル批判を土台にしている点では同じです。
とはいえ、新しい哲学は前の時代の哲学の批判からはじまるのが通例ですから、現代哲学の誕生は、人類の思想史における正常な発展のプロセスだったといえます。そういう意味では、やはりヘーゲル哲学の功績は大きいのです。
ヘーゲルの哲学とマルクス主義や実存主義との関係もたいへん興味深いものですが、このあたりの事柄についてはまた別の機会に話すことにしましょう。
「情然」と西洋思想
以上見てきたように、西洋の思想は、キリスト教の影響を抜きにして語ることができません。デカルトによって哲学が神学から独立したといっても、西洋の哲学の主流は何といっても観念論(形而上学)であり、その背後には常にキリスト教神学(神の創造と人間の堕罪、そして人類の救済というパラダイム)が存在していたのです。
では、ヘーゲルの哲学は「情然の哲学」とどのようなところに接点があるのでしょうか。
ここから先はやや難しい話になりますが、重要なテーマなので省略はできません。ここでは、「即自と対自」という観点に絞って解説しましょう。
以下に引用するのは、ある学者の、ヘーゲル哲学に登場する「即自」という概念についての解説です。
ドイツの哲学者ヘーゲルが用いた哲学用語。「即自」は物事の直接態、他とのかかわりによって規定される段階にまで達していない未発展の相をさす。したがって、認識する主観に対してまだ発現していない「潜勢態」、また自己自身への反省的関係を欠くという意味で「無自覚態」の意ともなる。たとえば、子供は理性の即自態である。
「即自」は、他と交渉し、そこに自己の自立性を失う「対他」へと発展する。子供が大人の命令に従うのは、自己の内なる理性を、他者の側にもつからである。さらに「対他」から、自己自身と関係することによって、自己を取り戻す段階である「対自」へと発展する。子供は理性を身につけることによって自立する。
理性を身につけるということは、自己の内なる即自的理性を自覚することである。理性を自覚することは、身に即して理性を発揮することである。他人とのかかわり(対他)のなかで、そのかかわりを自分の内に取り込んで自己を普遍化することによって自立する。「対自」には「自立」と「自覚」という意味が含まれる。
『R・ハイス著、加藤尚武訳『弁証法の本質と諸形態』(1970・未来社)』
また、ブリタニカ国際大百科事典には、「即自」について次のような説明があります。
現象から独立に実在に一致して、あるいはそのものの定義に一致して、という意。
ヘーゲルにおいては、概念 (一般者、絶対者) が自己のうちにとどまり潜勢的に弁証法的発展の萌芽を含みながらも、なお抽象的自己同一を保つ状態をいう。
サルトルにおいては自己充足的に存在し、自身のうちにいかなる否定も含まないようなもののあり方を示す。サルトルはこれを「あるところのものであり、あらぬところのものであらぬ」と表現する。
ヘーゲルやサルトルが用いていた「即自/対自」という用語を使うならば、「情然とは原初の心の即自的状態である」と定義することができるでしょう(「原初の心」についてはのちほどあらためて説明します)。
では、「情然」とはそのまま「即自」のことかというと、もちろんそうではありません。「情然」は「即自」の単なる言い換えではないし、類似の概念でもありません。「即自/対自」は関係概念ですが、「情然」は実体概念です。そこのところは大きく違います(ただし「心」が「実体」であるかどうかは別途論議が必要です)。
「情然」の概念は世界が「即自/対自」の構造になっている理由を解き明かす鍵となるものなので、「情然の哲学」は、ヘーゲルやサルトルの思想をさらに一歩進めたものといえるのです。
ただ、このあたりの問題はとても一回の講座で語りきれるものではないので、のちほどまたとりあげることにしましょう。

「情然」と東洋思想
ヘーゲルやサルトルの思想を振り返ることで、「情然」の概念と西洋思想のあいだには、意外なところに接点のあることがわかりました。
では、東洋のほうはどうでしょうか。
『情然の哲学』は、「情然」の概念と、華厳経、マンダラ、般若心経、易経、そして理気説(朱子学)との関連について言及しています。
東洋には上記の思想のほかにも、たとえば道教や神道などがありますが、もしかすると、この二つの思想にも「情然」と何かしらの接点があるかもしれません。
ここでは、この点について考えてみましょう。
まずは、道教について。
道教は、仏教・儒教とならぶ中国の三大宗教として、古来、人々のあいだに広く信じられてきました。「無為自然」の理念で知られるこの思想は、文明の力で自然を支配しようとする西洋の思想とは対極の位置にあり、東洋思想の最右翼ともいうべき性格を持っています。
源流にあるのは道家の思想ですが、その中心的な存在は老子と荘子であり、この二人の思想を合わせて、老荘思想と呼んでいます。
ここまではわりと常識的な事柄なので、ご存知の方も多いことでしょう。
老荘思想の中身に関する説明はここでは省略しますが(紙数の関係で、調べればすぐにわかるようなことは省略します)、老子は、万物を生み出す根源(すなわち「はじめにあったもの」)は「道」であると説いています。
この「道」は、もちろん道路を意味する「道」ではなく、独特の含意をもつものですが、別名をタオ、ともいいます(むしろこのことばのほうが有名ですね)。
老子によると、宇宙以前の存在としての「道」は、人間の感覚では捉えられず、また言葉で説明することもできないものです。
このあたりのところは重要なので、『老子』という書物から、該当の部分を現代語訳で引用しましょう。
誰もが道だとするようなものは、恒常不変の真の道ではない。名付けることができるようなものは真の名ではない。名付け得ないことが万物のはじめであり、名付けることこそ万物を生み出す母なのである。(第一章)
混沌たる何物かが天地よりも先に存在していた。音もなくひっそりと、ただ一人で変わることなく、あらゆるところをめぐって疲れることもなく、天下の母といってよい。私はその名を知らない。仮の名を「道」というのである。私は強いてこれに名付けて「大」というのである。(第二十五章)
この二つの箇所からもわかるように、どうやら老子もまた、今から二千数百年も昔に、「はじめにあったもの」が「情然の場」であったことをほぼ正確に洞察していたようです。
道教は「道」の「教え」と書きますが、「道」は「情然」ときわめて近い概念であるため、すでにこの時代に「情然の教え」が存在していたことになります。
このように考えると、東洋思想の観点から見た場合にも、「情然」はかなり有効な概念であるように思えてきますね。
ちなみに、道教というと、仏教や儒教ほどにはわたしたちと関わりのないもののように思えるかもしれませんが、じつはそうではありません。
「タオ」は、現代においても、スピリチュアルの分野(大型の書店に行くとやや奥まったところに「精神世界」のコーナーがありますが、そこに並べられている書物の内容を総称して「スピリチュアル」と呼んでいます)のキーワードになっているし、「気功」や、「風水」や、「漢方」や、「鍼灸」や、「丹田呼吸」などもみな、道教由来のものであるからです。
次に、「情然」と神道の関わり合いについて考えてみましょう。
神道について理解するためには、やはり、その背景にある日本文化全般に対する知識が必要です。
そして、日本の文化を理解するためには、古事記、日本書紀、万葉集、古今和歌集、源氏物語などの古典について知っておく必要があります。
また、ひとくちに神道といっても、古神道と復古神道と垂加神道と国家神道などがあるため、それらの区別がつかなければ話の入り口に立つこともできません。
戦後の日本の学校教育は、戦前までの日本文化に対する系統的な学習をすべて削除してしまったため(これにはアメリカの圧力や左翼勢力の影響があります)、「日本人の日本知らず」という状況が戦後の日本において顕著にあらわれてしまいました。
そのため、わたしたちのような中高年の世代においてすら、日本についての正しい見識を持ち合わせていない人が多いように思われます。いまの若者たちにおいては、なおさらです(神社とお寺の違いが説明できないような青年もたくさんいます)。
神道は、江戸時代に国学が隆盛したおかげで、いまのわたしたちにも引き継がれるようになりましたが、賀茂真淵(1697~1769)や本居宣長(1730~1801)や平田篤胤(1776~1843)などの仕事(国学)や、柳田国男(1875~1962)や折口信夫(1887~1953)などの仕事(新国学)についての知識がないと、神道の何たるかを把握することは難しいでしょう。
もちろん、それらの内容をこの場で語ることはできません。
そのため、「情然」と神道、「情然」と日本文化の関わり合いについては、のちほどあらためて話すことにしたいと思います。
ただ、ここで一つだけ結論的なことを言っておくと、「情然の哲学」は、メイド・イン・ジャパンの思想であり、日本の歴史や風土と深い結び付きをもっているということです。
「情然」という発想を生み出したこの学会が、たとえば、「パキスタン人間学会」や「オランダ人間学会」や「マレーシア人間学会」(いずれも架空の名称)などではなく「日本人間学会」であるのは、「たまたまそうなった」ということではないのです。
ただ、このあたりのことも一から説明すると長くなってしまうので、また別の機会に話すことにしましょう。『情然の哲学』は、第8章が日本の文化をテーマとする話になっているので、その章の解説のときにあらためて話すことになるかと思います。
「神の愛」と「情然」
最後に、「神の愛」と「情然」の関係について簡単に話しておきましょう。
キリスト教の根幹をなすものは、いうまでもなく「神の愛」です。キリスト教が神の愛を説かず、またイエスという人物が人類の前に神の愛の模範を示さなかったとすれば、キリスト教が今日のような世界宗教に発展することはなかったことでしょう。
では、そもそもなぜ神は「愛」なのでしょうか。
このあたりの問題については、当のキリスト教も「そうだからそうなのだ」といったトートロジーの答えしか持ち合わせていないようです。
しかしながら、キリスト教文化圏の外側にいるわたしたち日本人にとっては、「そうだからそうなのだ」と言われても、「はいそうですか」と簡単に納得するわけにいきません。
そのため、神が愛であることの哲学的な論証をわたしたち現代人は必要としているわけです。
もちろん、神が愛であることの論証などそう簡単にできるものではありません。このあたりのことをテーマにしているのは宗教哲学ですが、近代哲学においては、いわゆるドイツ観念論(カントに始まりヘーゲルによって大成された一連の哲学体系)の思想家たちがこの問題に取り組んできました。そして言うまでもないことですが、「なぜ神は愛なのか」という問題に関しては、わたしたち人類に未だ十分な答えは与えられていません。
ところが、驚くべきことに、「情然の哲学」は、このような究極的な難問にも問題解決の糸口をわたしたちに与えてくれているのです。
神の愛について明確な理解を得るためには、「神の誕生」と「神の成長」の問題を解き明かす必要があります。
ところが、神の誕生の問題を解き明かすためには、「はじめにあったもの」が「情然」であったという洞察が必要となります。逆に言うと、「アルケー=情然」と定義することによって、神の誕生と成長の問題にも解決の糸口が与えられることになるのです。
「神の愛」の問題が、神学のみならず、哲学と科学の統一的課題として解き明かされるようになるならば、この世界を一元的に解釈することのできる理論構築が可能となります。
もしも「愛の哲学」による世界の一元的解釈が可能になるなら、そのときこそ、希望に満ちた新しい世界像がそこから立ち現れてくることでしょう。
わたしたち人類はこれまで、神についてたくさんの議論をしてきましたが、神の誕生や神の成長といったテーマについては、ほとんど何も語らなかったし、また考えることすらありませんでした。「情然の哲学」では、今後、そのあたりのところまで哲学のメスを入れていくことになるので、どうぞご期待ください。
これまでの考察から、「情然」の概念は、古今東西の宗教・思想との比較においても驚くほど有効なものであることがわかりました。
では、現代科学の観点から見た場合にも、「情然」の概念にはやはり顕著な有効性が認められるのでしょうか。
次回はいよいよ、そのあたりのことについて話すことになります。
では、今回の話はこのへんで。



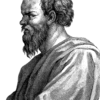







ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません