人間学の現在(20)
あけましておめでとうございます。
2023年になりましたね。
早いもので、本講座の連載も今回で第20回になります。
二ヶ月に一度の更新のペースで今後もこの講座を続けていく所存ですので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、今回のわたしの話は、『情然の哲学』第5章に関するものです。
章のタイトルは、「概念から物質そして人間へ」というものですが、全部で14の小見出しがあり、サブタイトルは、「三次にわたるビッグバン」というもの。
この章も斬新な発想に富んだスリリングな展開となっており、人間学の研究にとっても見過ごせない内容になっています。
ただ、そこに語られているトピックスを逐次解説するとかなりの分量になってしまいますから、ここでは、わたしがこの章を読んでとくに印象に残ったことがらについて話してみることにしましょう。
「愛」と「物質」の意外な関係
『情然の哲学』は、存在論の根本問題についてこれまでになかった視点から切り込んでいる書物ですが、なかでも、「愛」と「物質」の関係についての見解は注目に値します。
わたしたちの常識からすると、愛は愛であり、物質は物質です。どちらも人間にとって重要なものであることは言うまでもありませんが、この二つを強引に結びつけようとすると、どこかしら(悪い意味での)スピリチュアルな匂いのする話になってしまいます。
わたしが思うに、『情然の哲学』の魅力のひとつは、この書物が大型書店の「精神世界」の棚にカテゴライズされないものである点にあります。
この書物の著者は現代科学の知見を十分に踏まえつつ、愛と物質の関係についての論理を「論理的」に展開しているため、「哲学臭」(小難しい理屈を延々と語るような書物がこれに該当します)も「宗教臭」(何かあるものを無条件に神聖なものとする書物がこれに該当します)も感じさせないものになっているのです。もちろん、この書物には文章を過度に飾り立てるような「文学臭」もありません。
「ちょっと臭いけどなかなかの本だよね」という書物は世の中にたくさんありますが、『情然の哲学』にはそのような瑕疵はなく、それどころか、たとえば森鴎外の晩年の作品にみられるような香気すら感じられます。
ですからこの書物には、読者の側からすると、話の論理を追う楽しみと、文章を読む楽しみ(整理整頓されたことばの配列に心地よく身をゆだねる楽しみ)があるわけです。
では、「愛」とは何であり、また「物質」とは何なのでしょうか。
『情然の哲学』第5章の論理を追いながら、この問題について一緒に考えていきましょう。
まずは、次の箇所を読んでみてください。
宇宙は情然のゆらぎから生じたクオリアと、それが凝固した情感、そしてそこから生まれ、ゆらぎにベクトルを与え規定する働きを持つようになった理性との相互作用によって成り立っている。(「第3章 存在の構造」参照)そしてその宇宙を支える根源的な力は情然のエネルギー場がベクトルをもった「愛」であった。さらにその方向性を決めているのは、愛が本来的に志向する理想である。第4章の「愛は理想に向かう力」で述べたように、愛は常に理想を内包している。理想のない愛はない。愛の理想とは何か。それは、なぜ物質世界が必要だったのかという問いと同じ答えになる。(『情然の哲学』p199〜p200)
この短い一節を読むだけでも、読者のみなさまは、「愛」と「物質」の関係について正しく認識することができるのではないでしょうか。
わたしのこの講座でもこれまで述べてきたように、「愛」は、「情然」から生まれた知情意をともなう自発的な心の状態です。これが「原初格」において発現したため、原初格(この概念が難解であればさしあたり「神」と置き換えてよいでしょう)は物理法則によって維持される世界、すなわち物質世界を必要としたのです。もちろん、ご自身が思い描いた愛の理想を実体世界として外在化するためです。
というのは、「原初格」のなかには「概念としての愛」しかないため、それ自身においては本当の意味での愛のよろこびを体験することができないからです。
「神」がいくら愛の気持ちを抱いていても、自分ひとりしかいないのであれば、「自分が自分を愛する」という状態しかつくり出すことができません。しかし本来、愛とは他者との関係があってはじめて成り立つものですから、神はどうしても、子供を産んで子供を愛する(その子供はもちろん神とは別個の自由意志をもった存在です)という状態をつくり出したかったわけです。
いうまでもなく、ここでいう「子供」とはわたしたち人間のことです。
ここに、わたしたち人間が心(非物質的なもの)と体(物質的なもの)の二重構造になっている理由があるといえます。
また、わたしたちが肉身をまとい、生まれてから死ぬまでこの物質世界に生存する理由もここにあるといえます。
さらに言うなら、人間がおのおの唯一無二の個性をもった「個」として存在する理由もここにあるといえます。
この世界は、偶然いまあるようなかたちになったというよりも、「原初格」のかたちどおりにつくられたものではないかとわたしたちは考えているわけです。
この点については、やはり聖書の次の聖句が参考になるでしょう。
神は言われた。「我々のかたちに、我々の姿に人を造ろう。そして、海の魚、空の鳥、家畜、地のあらゆるもの、地を這うあらゆるものを治めさせよう。」
神は人を自分のかたちに創造された。神のかたちにこれを創造し、男と女に創造された。
(創世記 1章 26~27節)

「愛」と「存在」は同じもの
では、次の考察に進みましょう。
『情然の哲学』第5章の後半は、「家族的四位構造」に関するものです。
わたしが先に引用した聖句では、「神のかたち=男女(夫婦)」ということでしたが、「情然の哲学」ではその思想をさらに一歩進めて、「神のかたち=家族的四位構造」ととらえています。
ここでいう「四位」とは四つの位置のことで、それはすなわち、「親・子・男・女」の各位を意味しています。
このあたりのところは存在論のみならず、人間の存在に直接関わる重要な視点となるため、『情然の哲学』の次の箇所をおさえておきましょう。
これまで述べてきたように「存在」はすべて関係性の中にある。あらゆるものから完全に独立した「個」は存在できない。人間はもちろん一個の素粒子でさえ、その原則は変わらない。物質の最小単位とされるクォークは現在六個見つかっているが、そのどれも単独で取り出すことはできない。必ず他のクォークとの関係性の中でしか捉えられない。
その関係性の原型として確立されたのは、時間軸上に展開された「因果(親子)」と、空間軸上に展開された「陽陰(男女・夫婦)」が交差する「家族的四位構造」であった。(「第3章 存在の原型としての四位構造」)ここで「家族的」という言葉を使うことには、どことなく非科学的なニュアンスが感じられ抵抗を覚える人もいるかもしれない。しかし、この四位を結ぶのは方向性をもった情感性の力(情の流れ)であり即ち愛の力である。それゆえ「因果・陽陰」という無機的な言葉よりも、あえて「親子・男女」という有機的関係性としての意味をもった言葉で表現していると考えていただきたい。
存在は、それが概念世界であれ物質世界であれ、なんらかの時空的関係性の中に凝固されたものである。時空的関係性とは、存在そのものの内部構造として、時間と空間の差異、広がりがあるということだ。その時空的広がりを端的な言葉で表現すると「家族」になる。もちろん必ずしも一つの物質の中に実際の家族関係があるという意味ではないが、しかし構造的には相似形にあるということだ。
(『情然の哲学』p208〜p209)
かつてシャープという会社は、「目の付けどころがシャープでしょ」というフレーズをスローガンにしていましたが、『情然の哲学』を読むたびにわたしは、「目の付けどころがエグいほどシャープじゃないか」と、いつも舌を巻いてしまいます。
この箇所においても、もちろん然りです。
そして、『情然の哲学』はこのあとハニカム構造の話に移ります。
ハニカム構造とは、六角形の、ちょうど蜂の巣のようなかたちをとる構造のことですが、この構造は一般に、最も大きな強度を維持できるものとされています。
家族的四位構造は、そのなかに実はこのハニカム構造が隠れているというのが「情然の哲学」の見解です。
なぜかというと、家族はやがて氏族を形成し、家長の家(本家や実家と呼ばれるもの)においては通常、祖父母を含めた三世代が共に暮らす家庭になっているからです。
このあたりのことについては、『情然の哲学』の次の箇所が参考になります。
三世代家族が配置されたハニカム構造は家族的四位構造をより詳細に見たものであって、基本的には同じものである。それは原初格の構造であり、私たち一人ひとりの人格から、人類・宇宙全体、そして一個の素粒子内にも見られる存在の基本的な原型でもある。存在は、部分も全体もすべてこの基本構造を元に展開しているため、個と全体が共鳴関係にあるフラクタル構造をもつホロン的存在となる。
(『情然の哲学』p214)
「情然の哲学」における存在論の問題は、わたしが思うに、この箇所が結論となります。
結局、第3章からはじまる存在論の論議は、この第5章において明確な結論に到達することができたわけです。
それにしても、この書物に見られる論理の骨組みは見事なものです。一つ一つの小見出し(意味段落)が有機的につながりあい、必要に応じて具体例を交えながら、「存在」に先立つものとしての(そして「存在」を「存在」たらしめるものとしての)関係性のあり方をものの見事に描破しています。
そして、その関係性の基本単位となっているのはわたしたち人間の存在基盤である「家族的四位構造」だというのですから、驚きです。
これは言うならば、「ねずみの嫁入り」のような話で、存在論の真理を求めて果てしなく遠い旅に出ていたつもりが、結局、「答えは自分のいちばん身近なところにあった」というわけです。
最近は三世代家族というものが少なくなっていますが、わたしたち人間は本来的に、祖父母、父母、子供、という三世代構成の家庭のなかで十分な愛のやりとりをすることができる存在だというわけです。
わかりやすい例で言うと、サザエさんやちびまる子ちゃんのような家族ですね。
だとすれば、少なくとも根源的な次元においては、「愛」と「存在」は同じものであったと考えることができ、現代の科学的探求が「情然の哲学」を媒介として、「神は愛なり」というキリスト教の本質にまでつながり得ることになるわけです。

物質世界の謎を解く鍵
『情然の哲学』ではこのあと、「愛」と「力」についてのユニークな考察に入ります。
小見出しのタイトルは、家族的四位構造の愛と「四つの力」の相関関係、というもの。
家族的四位構造の愛という概念も、悠久なる哲学の歴史のなかで初めて出てきたものですが(そもそも西洋の哲学には「家族」を視点に置いた思想がほとんどありません)、この概念は、単に形而上のものではなく物理的な「四つの力」と相関関係にある、というわけです。
ここに出てきた「四つの力」については、高校の物理の教科書で簡単におさらいしておくとよいでしょう。
自然界には、4つの基本的な力が存在する。それらは、強い力、電磁気力、弱い力と重力である。一方、空気の抵抗力や摩擦力などは分子の衝突や分子間の静電気力によって説明できるので基本的な力とは考えない。
(東京書籍版『改訂物理』p438)
わたしたちが暮らしているこの自然界は四つの力によって成立していますが、「家族的四位構造の愛」という視点からこの世界を眺めてみると、「四つの力」はそれぞれ次のように読み解くことができます。
1. 強い力は、夫婦のあいだに働く愛の力(男女愛・夫婦愛)。
2. 電磁気力は、父母と子供たちのあいだに働く愛の力(父母愛・子女愛)。
3. 弱い力は、兄弟姉妹や友人たちのあいだに働く愛の力(兄弟愛・友愛)。
4. 重力は、人と人とのあいだに働く愛の力(隣人愛・人類愛)。
このような観点から世界について考えてみると、「愛」と「存在」の本質的同源性についての理解がより深まってきますね。
もしかすると、わたしたち人類が所与の前提としているこの自然界そのものが、実は「神のかたち」なのかもしれません。
とするなら、「情然の哲学」は「愛の哲学」と呼んでもよいことになります。
ここで少し個人的な発言をさせていただくと、わたしは若いころから、「世の中にもしも愛の哲学というものがあるのなら、世界は平和になるし、人々もしあわせになれるのになあ」と考えていました。
ところがわたしが長いあいだ求めていた「愛の哲学」は、ほかならぬこの「情然の哲学」のなかにあったわけです。
これは、わたしの人生にとってのまさに僥倖でした。
なお、「愛の力」と「物理の力」の相関関係については『情然の哲学』のなかに詳しい説明がありますので(p216~p218)、ご興味のある方はそちらをお読みください。
愛と物質の関係についてのいちおうの結論が出たところで、今回の話はこのあたりにしておきましょう。
次回は、『情然の哲学』の第6章について解説します。
お楽しみに。
(関根均 せきねひとし)
1960年生まれ。慶応大学卒業後、民間企業勤務を経て塾業界へ。40歳のときに独立。日本人間学会の研究会員として2010年から人間学の研究に取り組み、現在に至る。







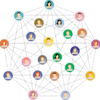



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません