人間学の現在(19)
今回は、前回の講座で予告したとおり『情然の哲学』第4章の内容を解説します。
第4章のタイトルは、「愛と自由と生命と理想」というもの。
愛、自由、生命、理想ということばは、いずれも抽象的な概念でありながら、わたしたち人間にとってとても大切なものです。
そのため、愛についても、自由についても、生命についても、また理想についても、これまで多くの人によってさまざまなことが語られてきました。
ところが、これら四つの概念の相互関係について明瞭に解き明かした哲学というものは、意外にも見当たらないのです。
愛についての定義からはじまり、自由、生命、理想というものが、その「愛」との関係においてどのような意味をもつのか、という点について、『情然の哲学』は明快な論議を展開しているので、今回はそのあたりの問題について掘り下げてみることにしましょう。

「情然」から生まれた「愛」
情然ということばはわたしたちの造語ですから、当然のことながら、今のところほとんど知名度がありません。それに対して、愛ということばを知らない人はいないわけですから、知名度という点でこの二つを比べてみるなら、雲泥の差があることになります。
ところが、わたしたちの見解によれば、「愛」の理解のためには「情然」の概念がどうしても必要なのです。
愛という概念だけを見つめていても「愛」の正体はつかめないのですが、情然という概念を入り口にして愛について考えてみると、驚くほど明快な愛の定義ができるようになります。
情然と愛の関係については、すでに『情然の哲学』が明晰な論議を展開しているので、まずそこのところを読んでみることにしましょう。
情然の場は、偶然性が支配する世界であり、そこには目的や理想に向かうベクトルはない。偶然何らかの構造が見られても、それを維持する力はなくすぐに混沌の闇へと戻ってしまう。偶然性とは無秩序化への圧力でもあり、それはつまりエントロピー増大の法則そのものだ。情然の場のエネルギーこそ、まさにエントロピー増大の力でもあるのだ。
それは宇宙始源の状態のみならず、星と星との間の空間、プランク領域内のミクロ空間など、宇宙全体に広がっている真空エネルギーの場でもある。当然、空気や水や鉱物の中にも、動植物の中にも、そしてもちろん私たちの体の中にも情然の場があり偶然のゆらぎを続けている。「第3章 存在の構造」で詳述したように、情感も理性も心も概念も根源的には情然の場のゆらぎ、クオリアが凝固したものである。概念的ビッグバンを経て物理的ビッグバンが起こり、そこで光や原子、天体、そして人間やすべての生命が生じる原動力となり、またその原材料となったのもやはり情然である。ゆえに存在はすべて情然のエネルギー・エントロピー増大の法則の影響を受けることになる。
しかしそのエントロピー増大に抗する愛の力があるがゆえに、宇宙は混沌に戻らずに秩序を維持できている。愛の力はベクトルを持ち、対象との間で関係性(秩序)を維持しようと作用する。目的や理想 ―より幸福な状態― に向かおうとする発展的推進力がある。愛は宇宙に必然性をもたらし、それによって宇宙は混沌から秩序へと向かうことができたのだ。
第3章の「愛の始まり・自由と規定性」では、愛の力が「現れた力」であるのに対して、情然の力は「現れていない」潜在的なエネルギーの場であると述べた。しかし、愛の力によって秩序が生まれ宇宙が構成されようとする段階では、常に混沌へといざなおうとする力として相対的に発現しているということもできる。それは動こうとすることで初めて抵抗力を感じる(発現する)のと似ている。愛の力と情然の力(エントロピー増大の力)は、まさに表裏一体であり、局所的には対立関係のように見られることがあっても、より大きな流れや本質的なレベルにおいては相補関係にあるのだ。もともと愛の力そのものが情然の場から生み出されたのだから、それは当然のことでもある。すべては一なる情然の場から生じたという観点に立てば、宇宙全体、全存在において本質的に対立するものは一つもない、ということになる。
情然の場は、規定性のない自由の場でもある。情然が愛を目指して発展してきたように、自由の目的も愛の実現のためにあるのだ。偶然性の支配する情然の場が心地よさを求めて自ら規定性を生み出したように、自由は真実の愛に拘束されることを欲しているということもできる。
(『情然の哲学』p167-169)
ここで語られている愛とは、より具体的には「原初格」において発現した愛のことですが、原初格ということばも造語であり、ほとんど知られていない概念であるため、ここではさしあたり「神の愛」と考えてもらって差し支えありません。
わたしたち人間と同じように、「神」もまた、愛と自由と生命と理想によって自らの存在を成立せしめていると考えるわけです。
ここで留意しておきたいのは、「情然の場」から愛が生まれたからといって、「情然」がすべて「愛」におきかわってしまったわけではないということです。
「情然」とは、この世界のあらゆる存在に先立って存在していた「情のゆらぎの場」のことですから、このなかから「愛」が生まれ「神」が生まれ(両者は存在論的に同義のものだと考えられます)その「神」から世界が創造されたとしても、もともとあった「情然」がそのためになくなってしまうわけではないのです。
物理的な側面から見た場合、「情然」はいまでもエントロピー増大の法則として存在しているので、わたしたちは、初めから最後までずっと情然の世界のなかにいることになります。
ここでは深く立ち入ることはしませんが、情然と愛の関係がわかると、「偶然と必然」の問題もすんなりと理解できるようになります。わたしたちは常に、偶然と必然の事象が複雑に連鎖する時空間のなかに生きていますが、なぜそうなっているのかという根本的な問題に対しても、一つの合理的な解釈の道が与えられるわけです。
『情然の哲学』では、「偶然と必然」の問題のほかにも、「ゆらぎと流れ」、「クオリアと概念」、「情感性と理性」などのことがらが重要なテーマとしてあつかわれています。
これらは一見すると多様な問題群のように思われますが、実はそうではありません。
偶然から必然が生まれ、ゆらぎから流れが生まれ、クオリアから概念が生まれ、情感性から理性が生まれた、と考えてみると、やはりおおもとにあったのは情然だった、ということがあらためて合点できます。
そして、これら「生んだものと生まれたもの」が相互補完的な関係を形成することによって、この世界は一つのまとまりのある「実体」として出現することが可能になったわけです。
実際、この地球上に生存しているいきものたちを観察しても、そこには驚くべき多様性がありながら、全体として一つの生態系を形成しています。自然界において「生物多様性」はこれまで一度として破綻したことがなく、わたしたちの星はすでに、46億年もの生命を維持しているのです。
宇宙のはじまりを「偶然」とする思想も今なお健在ですが、単なる偶然からこうした「多様性のまとまり」が数十億年にもわたって維持されているとは、わたしにはとうてい思えません。
この宇宙が偶然によって出現したのであれば、偶然によって消滅してしまってもいいはずですが、たとえば、「最近太陽が偶然にも小さくなり消滅の方向に向かっているので、わたしたち人類もまもなく消滅することになります」などという事態は、誰も願っていませんね。
愛と自由、愛と生命、愛と理想
次に、愛と自由、愛と生命、愛と理想の関係について整理しておきましょう。
まず、愛と自由の関係ですが、「自由がなければ愛は成立しない」というのは自明のことで、愛する側も愛される側も、ともに自由意志を前提としなければ愛の関係を結ぶことができません。
現行の憲法のなかにも自由権というものがあり、表現の自由や職業選択の自由など、わたしたち国民にはさまざまな自由が保障されています。自由権は基本的人権を構成する一つの重要な権利であり(ほかには社会権や平等権などがあります)、いかなる権力によっても剥奪されることはありません。
そのため、人が誰かを不当に拘束した場合、それは人権侵害の罪に問われることになるわけですね。
ここで、わたしが第17回の講座のなかで提起した「情がもっている普遍的な性質」を再度確認してみましょう。
それは、自発性、受容性、指向性、結合性という四つの性質でした。
「純粋感情」(これはわたしの造語です)のなかに上記の四つの性質があったため、有と無の未分化の世界のなかにいた「姿のないアメーバ」は陽陰の極性をもつことになり、そこから理性が生まれ、自我意識が生まれ、愛が生まれた(愛に目覚めた)、というのがわたしの理解です。
わたしたちの心は今でも情然の状態を基礎としており、情然とは「情」が自由に動くことのできる場のことですから、この点から考えてみても、愛と自由は一体不可分の関係にあることになります。
次に、愛と生命の関係ですが、大枠で考えた場合、こちらも一体不可分のものであるとわたしは捉えています。
『情然の哲学』においても「生命」について瞠目すべき定義が下されているので、以下に引用しておきましょう。
愛によって強く結びついた「我」と「汝」が時空的構造の中で再認識され、もはや壊れることのない四位構造をもった「自我(原初格)」が確立されたのであった。それは概念上の時空的存在の始まりでもある。それはまた「生命」の始まりでもある。
「生命」とは、愛のベクトルによって成立する「存在そのもの」のこと。すべて存在は「個」ではなく関係性として「ある」ということは繰り返し述べてきた。その原則は、存在と存在との関係はもちろん、存在の内部においても変わらない。すべての存在は時空(縦軸×横軸)的に展開された四位構造によって成立している。その関係性を結び付けているのが愛である。ようするに構造として静的に把握された「存在」を、力やエネルギーとして見ればそれは「愛」であるということになる。物質とエネルギーが等価であるというのと同じような相関関係にある。
もちろん、ここでいう「生命」は一般的に生物学的に把握されるものとは同じではない。情然の哲学に基づいて定義される概念である。生物学的に誕生するずっと以前から「生命」はあり、また生物学的に死と判断された後も「生命」の本質は継続する。愛によって結びついた四位構造が「生命」の核であるとするならば、それは「存在」そのものであり、究極的には素粒子一個であっても「生命」として存在しているのだ。動いている(振動している・ゆらいでいる)ものは「生命」であるという観点からも、同じ結論になる。
それは「生も死も空である」という仏教の考えに近い。一般にイメージされる死は、存在様相の変化であり非存在になったわけではない。それは一時的なカオスへの回帰であり、次の生のステージに向けた始まりでもある。「ある」のは「生」だけで、「死」は「無」と同じように存在できない。たとえ生物学的な死が訪れても、そこに愛がある限り「生命(の核)」は続いていく。
(『情然の哲学』p180-181)

唯物論的な発想によれば、生命の誕生は地球が誕生してからおよそ10億年後のことになります。生命体、すなわち実体としての生命の誕生はたしかにそうなのかもしれませんが、個々の生命体にいのちを与えたおおもとの「生命」の誕生は、宇宙の始源のときにまで遡りうると「情然の哲学」では考えるわけです。
このあたりは哲学として非常にすぐれた洞察であるとわたしは思うし、また、そのように考えてみると生命の起源の謎もすっきりと理解できるようになるので、不思議です。
最後に、「愛と理想」の関係について確認しておきましょう。
理想とは何かという問題について考えてみると、とたんにどう考えていいかわからなくなります。
もちろん、辞書を引けば「理想」の意味はわかりますが、「原初の心」においてどうして理想が生まれたのか、という問題については、おそらくこれまで誰も考えてきませんでした。
常識的には、理想とは、まだよく世間を知らない若者たちがもつもの、といったニュアンスがありますね。
理想は現実の対義語であり、大人になって現実の世の中を知れば自然に消えていくものだ、という否定的なニュアンスです。
ところが、『情然の哲学』には「理想」に対する原理的な定義が存在します。そもそも理想とは何なのか、という問題に対する回答です。
次の箇所を読んでみましょう。
引力と斥力のほか、愛にはもう一つ重要な要素がある。それは、より高いステージに向かおうとする理想にほかならない。どんなに深く愛し合っても、ただ二者が向き合うだけであれば発展性がなく、愛も次第に収縮していってしまうだろう。たとえば恋人同士であれば、お互いにより高め合う中でそれぞれが人格的に成長し、より深い愛を築こうとするようになる。一対の愛し合う男女はいずれ夫婦となることを目指し、結婚によって家族の核を構成する。やがてそこに新たな生命が生まれ父母となり、そして祖父母となっていく。二人から始まる愛は、男女の愛から、親の愛、そして人類愛へと広がり発展していく。
親子の愛でも、男女の愛でも、兄弟姉妹の愛でも、友愛であっても、愛はそれ自体の性質として常に理想を目指すようになっている。もし、ただ向き合うだけで理想が失われた関係であれば、もはや愛とはいえない。疑ってかかった方がいいだろう。愛は理想を共有し合うことで成立する。愛し合っているということは、即ち共に理想に向かっているということでもあり、それによって愛が維持され、発展するのである。
愛は相対関係の中を行き交う方向性を持った情の流れでありつつ、その愛によって結ばれた関係それ自体も同じように対象 ― つまり理想に向かうベクトルをもつようになる。そうして愛は、さまざまなステージにおいて常に理想に向かい、無限に展開していくことになる。理想とは「いまここでないどこか」にある世界や状況を指し示すビジョンのようなものではあるが、理想そのものは漠然とではあっても「いまここにある心の中」に描かれている。理想に向かうことは、それ自体すでに理想に包まれて理想の中にいるようなものかもしれない。理想に生きる人は、現状がつらくても勇気や希望を持つことができるのは、それゆえである。
(『情然の哲学』p178-17)
わたしたちは日頃、「こうありたい」という状態をイメージしながら物事を処理しています。
何事においても理想の状態(平たく言うと望ましい状態)を強く思い描けば、その分だけモチベーションも上がりますね。
愛というものはそもそも、望ましい状態を志向する前向きな心の姿勢です。
愛とは逆の感情に、「憎悪」や「怨恨」がありますが、これらのネガティブな感情から「破壊」が引き起こされることはあっても、「建設」が生まれることはありません。
これらの思いのなかには、「理想」がないからです。
したがって、このような常識から考えてみても、「理想」の母体はやはり「愛」だといえるでしょう。
「愛と生命と理想は三位一体である」という「情然の哲学」の見解は、十分に妥当なものであるとわたしは思います。
進化した人権思想
今回の話を簡単にまとめておきましょう。
人間学的な観点から『情然の哲学』を読んでみると、この哲学は「進化した人権思想」ともいうべき側面をもっていることがわかります。
「情然の哲学」は、世界の根源(情然)から愛が生まれ、その「愛」と同時に「生命」と「理想」が生まれたという思想ですから。
この思想を価値論の観点から見てみると、「一人ひとりの人間の価値は宇宙全体の価値に等しい」ということになります。
おそらくこれは、かつてないほど壮大な広さと深さをもったヒューマニズム思想だといえるでしょう。
こうして、新しい次元から人権思想の基礎付けを試みた「情然の哲学」は、混迷を極める現代社会に新たな希望を与えるものとなっています。
わたしが数年前からこの哲学に注目しているのは、そのためです。
今回の話は、これくらいにしておきましょう。
次回の講座は、来年1月の初旬にアップする予定です。
『情然の哲学』第5章の内容について話します。
では、このへんで。
(関根均 せきねひとし)
1960年生まれ。慶応大学卒業後、民間企業勤務を経て塾業界へ。40歳のときに独立。日本人間学会の研究会員として2010年から人間学の研究に取り組み、現在に至る。





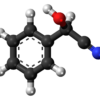





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません