人間学の現在(24)
わたしはこれまで、数回にわたって『情然の哲学』の思想について語ってきましたが、前回までの話でそれにも一区切りがついたので、今回は、この思想についての総まとめの話をしようと思います。
人間学の話をするために、どうして「情然の哲学」の思想を紹介する必要があったのかというと、「人間」について考えるためには、「人間界」のみならず、「自然界」と「超自然界」のありさまについても考えなければならないと思ったからです(超自然界とは何かということについてはのちほど説明します)。
「情然の哲学」は、人間の存在について考える際に、いくつかのとても有効な視点をわたしたちに提供してくれています。
それはたとえば、世界の根源(アルケー)の問題に対する視点であったり、弁証法の問題(発展法則の問題)に対する視点であったり、ハイデガーやサルトルが提起した「即自」と「対自」の問題(人間の実存の問題)に対する視点であったり、人間の心の問題に対する視点であったり、人間の家庭や社会の問題に対する視点であったり、人間が普遍的にもっている幸福への欲求の問題に対する視点であったり、といったものです。
『情然の哲学』はこれらの問題に対し、章ごとにテーマを設定しながら論議を進めているため、わたしもこれまで、おおむね、それぞれの章ごとにその内容を解説してきました。
いまのわたしたちは、『情然の哲学』の全体を俯瞰できるところまで来ていますから、ここで改めて、この思想がわたしたちに与えてくれた「新しい世界観」についてまとめておきましょう。

キリスト教と共産主義
『情然の哲学』を一つの思想書として見た場合、そこには一つの際立った特徴が見て取れます。
これまでにもこの世界を解釈する「大きな物語」はいくつかあらわれており、その良い面だけに目を向けると、それらの思想は人々の心のよりどころとなってきました。
たとえばそれは、キリスト教の思想や共産主義の思想などです。
周知のように、アメリカの建国精神にはキリスト教があるし、中華人民共和国の建国の理念には共産主義があります。
今世紀に入ってから、この二つの国の対立はますます深刻なものになっていますが、それぞれの思想がそもそも統合不能のものですから、当然と言えば当然です。
「アルケー」の観点から見てみると、キリスト教はアルケーを「神」とする思想であり、共産主義はそれを「物質」とする思想です。
キリスト教の思想では、神は「無」から万物を創造したことになっているし、共産主義の思想では、「神」は人間の頭の中にある観念に過ぎない、ということになっています。
そのため、この二つの「大きな物語」は、その始発点と終着点がまったく別のものになっているのです。
ところで、この二つの思想がなぜ「大きな物語」なのかというと、そこには、(それが正しいかどうかはともかく)世界の始まりから終わり(理想的な世界の実現)に至るまでのビジョンが描き出されているからです。
世界はかくあるべきもの、というビジョンを提示した思想は、かならず熱心な支持者、もしくは信奉者を生み出すことになります。
たとえば、キリスト教思想はクリスチャンを生み出しているし、共産主義思想は左翼活動家を生み出していますね。
もちろん、信教・思想の自由は憲法で保障されていますから、そのこと自体は個人の自由の範囲内にあることです。
ところが、世界観の対立の問題は、正義論や平和論の問題にも関わるとても厄介な問題です。
この問題を野放しにしておくと、ひとは往々にして喧嘩をはじめてしまうのです(というよりもすでに長いあいだ喧嘩の状態にあります)。
個人と個人の喧嘩であるならば、まぁ、ほうっておいてもいいでしょう。
ところがそれが、国と国の喧嘩になった場合、世の中はどうなってしまうでしょうか。
わたしがこの二つの思想の対立にこだわるのは、アメリカと中国の関係が現在、非常に危険な状態にあるからです。
戦争など、起こしてもらいたくない。
もちろん、誰もがそう思いますよね。
もしもアメリカと中国が軍事力を行使するようになれば、日本も無傷ではいられないでしょう。
この二つの大国が戦火を交えた場合、それを傍観していられる国などどこにもありません。
ですから、この二つの「大きな物語」の対立の問題は、人類にとって看過できない重大なことがらなのです。
対立に満ちた世界
では、ここでもう少し、イデオロギーの対立という問題に関して考察を深めてみましょう。
現在、アメリカと中国が対立していることは明らかです。それぞれの首脳が会談をするときは、はじめに笑顔で握手をしますが、だからといって、両者の仲がいいわけではありません。
政治という表舞台の裏側で、世界の国々はそれぞれ粛々と軍備を増強しており、その理由はというと、もちろんそれは、万が一の事態、すなわち戦争に備えるためです。自分たちは戦争をするつもりはないが、攻められると困る、という理由で、それぞれの国が防衛のために軍備を増強しているのです。
ということは結局、人類の思想はいまだに「最後はやはり戦争だ」というパラダイムから抜け出せていないのであり、そのことのために、世界の軍事情勢は今もなお緊迫した状況にあるのです。
そして、そのような事態になってしまった根本の原因は、やはり、「対立する二つの大きな物語が閉じられた構造になっているから」と考えるのが妥当でしょう。
簡単に言うと、クリスチャンは共産主義者を容認することができないし、また、共産主義者はクリスチャンを容認することができません。もちろん、かれらが露骨にこうした排他性を公言することはありませんが、本音の部分では、やはり決して容認してはいないのです。
では、国と国の間にどうしてこのような対立が生まれ、あわや世界戦争、というところまで発展してしまったのでしょうか。
そこにはやはり、「アルケーの問題」があるのではないかとわたしは考えています。
たとえば、共産主義においては、世界の根源は「物」なので、物以外のものは物から派生したものであり、物の法則(これは物理法則とは若干ニュアンスが違います)の支配を受けるものとなります。
そうした世界観に立つならば、たとえば、「心」や「精神」や「霊」や「魂」や「神」などは、二次的な派生物になります。つまり、その時点ですでに、物質世界を優位とする排除の論理が働くようになるのです。
また、キリスト教の思想においても、「アルケー」を「神」と定義した途端、宗教に特有の排除の論理が働いてしまいます。
たとえばそれは、「わたしは信者だから救われるけれども、あなたは信者ではないので救われません」という論理です。
とりわけ、キリスト教のような一神教において、こうした排除の論理は顕著です。
もちろん、表立ってこんなことを言うひとはいないけれども、どの宗教にもやはり、「信仰義認」というものはあります。
ですから、宗教間においても、特定の教団に所属する信者のひとたちはおおむね、他教団の信者さんとは仲が悪いのです。

世界は対立に満ちている。
世の中のこのような現状は、大人たちだけでなく、子供たちだって気づいているはずです。
とするならば、「迷路の時代」(価値観が多様化して社会全体が混沌としている時代)に生きているわたしたちが願っているのは、やはり、万人に対して開かれた思想の登場、ということになります。
わたしがこんなことを言うと、「それはそうだが、そんな思想がいったいどこにあるんだ」という声が、どこからか聞こえてきそうです。
そうですよね。
実はわたしも、ずっとそう思っていました。
排他性をまったくもたない思想なんて、ありえない、と。
ところが、です。
幸運にもわたしは、偶然、「排他的な構造をもたない思想」というものに出会ってしまったのです。
しかもそれは、これまでにあらわれた「大きな物語」と比べてみても、遜色のないほど深くて広い思想だったのです。
それが、ほかならぬ、「情然の哲学」というものでした。
「情然の哲学」の特徴
ここで、話を最初の部分に戻しましょう。
今回の講座のはじめの部分で、わたしは、「情然の哲学という思想には一つの大きな特徴がある」と話しました。
その特徴を簡単に言うならば、「世界に向かって開かれた構造をもつ思想」ということです。
キリスト教や共産主義が、「こうでなければならない」という閉じられた構造によって成立しているのに対し、「情然の哲学」には、そのような排他性がないのです。
これは、驚くべきことがらです。
では、どうしてこのような思想が、21世紀になってから出現したのでしょうか。
わたしなりの答えを言いましょう。
それは、日本の文明が、西欧世界のそれを超えてしまったからです。
西洋の哲学は、古代ギリシアにおいて発祥しています。
その地において芽生えた自然哲学は、アルケーとは何かという問題をメインテーマにしていました。
もちろん、その問題は未解決のまま時代が流れ、近代に入ってから、問題の追求は科学者たちの手に委ねられることになりました。
ところが、西洋の歴史において、宗教と哲学と科学はそれぞれ分離しながら発展してきたため、アルケーの問題を探究する知の分野そのものが居場所を失くしてしまい、あたかもそれは、「古い時代の問題」であるかのように扱われるものになってしまいました。
ポストモダンの風潮が、こうした状況を加速させたのは言うまでもありません。
ところが、問題は何一つ解決してはいないのであり、たとえば、今の時代の哲学界の碩学に、「世界の根源は何だと思いますか」と尋ねてみても、納得のいくような答えは返ってこないでしょう。
「アルケー=情然」という等式を発見したのは、わたしたち日本人です。
大げさな言い方のように思われるかもしれませんが、この等式が発見されることで、二千数百年におよぶ哲学の歴史がひっくり返ってしまいました。
なぜなら、この思想によると、世界の根源は「物」でもなく「神」でもないのですから。
『情然の哲学』の中身についての解説は、これまで数回にわたって行ってきたので、ここでそれを繰り返す必要はないでしょう。
念のため、ごく簡単に確認しておくと、共産主義とキリスト教には、アルケーの定義について大きな難点があります。
共産主義では、「アルケー=物」ということになっていますが、今の科学者たちがこの等式を見るならば、かれらはこれを見た瞬間に目を丸くし、そして失笑してしまうでしょう。
なぜならこの等式は、今ではもう時代遅れのものになってしまっているからです。
マルクスが生きていた時代には、この等式はたしかに、多くの人々を納得させるだけの力があったかもしれません。
ところが、それははるか昔、19世紀の頃の話です。
量子力学がすでに100年の歴史を持っている今日において、「世界の根源はモノだと思う」などと真面目な顔で公言することは、少なくともこのわたしには、とてもではありませんが恥ずかしくてできません。
ですからわたしは、唯物論に立脚した共産主義の思想を支持しないのです。
では、キリスト教のほうはどうでしょうか。
「アルケー=神」と定義した場合、当然のことながら、「神って何?」という疑問が心の中に湧いてくることでしょう。
もちろん、その疑問について明確に答えてくれるような神学がもしもあるとすれば、わたしはその教えに帰依してもいいと思います。しかしながら、そのような神学というものは、どうやらこの世界には存在しないようなのです。
ただし、「神がこの世界を創造した」という命題に関しては、わたしはそれを否定するつもりはありません。
なぜなら、「情然の哲学」に登場する「原初格」という概念を「神」と解釈すれば、この命題は正しいことになるからです。
では、「アルケー=情然」と定義した場合、その後の思考はどうなるでしょうか。
当然、「情然とは何か」という疑問が心の中に湧いてくることになりますね。
「情然の哲学」によれば、「情然」とは、「情が情のままにある状態」というものです(もっともこれはわたしの解釈であって『情然の哲学』のなかにこのような説明があるわけではありません)。
「情が情のままにある状態」とは、そのなかに「知」や「意」を含まない「情」の状態を意味しますが(わたしはこれを純粋感情と呼んでいます)、このあたりの話になると、完全に哲学の領域になります。
つまり、「人間界」でも「自然界」でもない、「超自然界」の話になるわけです。
ところが、「超自然界」の話ではあっても、それはわたしたちにとって雲をつかむようなものではありません。
なぜなら、「情が情のままにある状態」から「原初の心」が誕生し、その「心」が成長して「神」になった、とわたしは考えているからです。
ちなみに、「情然の哲学」では、「心」についてのわかりやすい説明があります。「情」と「知」は「心」の両極であり、この二つの極がたがいに作用することで「意」が生まれる、という説明です。
実にシンプルで美しく、そしてわかりやすい命題だと思います。
ですから、結局、「情とは何か」という問題が最後に残ることになるわけですが、「情」はわたしたちにとって、「神」のような漠然とした概念ではありません。
なぜなら、喜怒哀楽の感情を一度も経験したことのない人間は、おそらく一人もいないだろうからです。
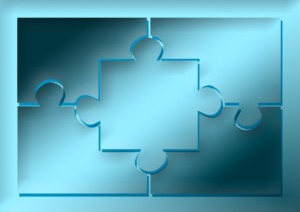
このあたりで、今回の話をまとめておきましょう。
「情然の哲学」を思想的な側面から見た場合、世界の根源には人間の心を誕生せしめた「親」としての「心」があり、その、「神」とも名付けられ得る「原初の心」は「情然」から生まれている、という画期的な世界観が導き出されます。
そのため、「人間界」と「自然界」と「超自然界」は三位一体の関係になるわけですね。
であるとすれば、わたしたち人間は世界の中心に位置する存在なのです。また、人間にとってなくてはならない自然界は、わたしたち人類にその管理を任されたものなのです。
このような卓抜な洞察は、西洋の文明を超えることのできた日本人ならではのものだとわたしは思いますが、読者のみなさんは、どのような感想をお持ちでしょうか。
では、今回の話はこのへんで。


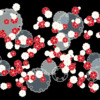


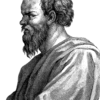





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません