人間学の現在(30)
本講座「人間学の現在」は、今回が最終回になります。前回までの話でわたしがこの講座で語りたいと思っていたことはほぼ語り終えているので、今回は、次回からはじまる新しい講座の内容について話しましょう。
すでにお知らせしたとおり、新しい講座のタイトルは「文学と人間学」というものです。その講座も今のところ30回程度を予定しており、かなりの長丁場になりそうです。建築にたとえるならば、30階建てのビルを建てるようなものかもしれません。となると、はじめにしっかりとした設計図がなければなりません。設計図のないまま着工することはできませんから。
ということで、今回はその設計図の内容について話してみたいと思います。

文学とのリエゾンという方法
本講座で度々話題にしてきた菅野盾樹氏の『人間学とは何か』では、「人間学の方法」について次のような言及があります。
ところで、人間を科学主義で囲い込むことは実際には不可能である。人間の生が特殊な時代や特殊な場所の刻印をおびざるをえないのは当然のことである。また、人間は言語化しえない不合理な要素を抱えているし、数値化とは無縁な側面もそなえている。自然科学を模範とする科学主義には、自然科学的方法だけが妥当であるという含意(方法的一元主義)がともないがちである。学問の方法には文献学的方法や参与観察法、インタヴュー法などもあるが、それらは無視されてしまうか、価値が少ないものと見なされるのである。人間の全体像を解明するためには、明らかに、この方法的一元主義では間に合わない。人間が身体をそなえるかぎりは生理学が、集団として行動する限りでは統計学が不可欠であると同時に、人間の行為の意図や意味を了解することも必要である。人間学がつねに経験科学と協同し連携を保ちながら探究されるべきであるなら、人間学にとって好ましくもあり不可避でもあるのは、方法的多元主義なのである。(p24)
人間学にアプローチする方法にはさまざまなものがあり、それは一元的に決まっているものではない、ということですが、これはまぁ、当然といえば当然ですね。
この講座では、「情然の哲学」という新しい哲学を視野に入れることで、人間学の新しい地平を探ってみることにしました。これも一つの方法としてよかったのではないかと思っていますが、その作業が一段落したので、今度はまた別の角度から人間学にアプローチしてみようと思うわけです。
菅野氏の人間学研究においては、経験科学とのリエゾンの必要性が強調されています。経験科学とは、具体的には人類学や言語学や心理学などですが、わたしは次回からはじまる講座のなかで、人文科学とのリエゾンを試みたいと考えています。
人文科学にもさまざまな分野がありますが、なかでもわたしが関心を持っているのは、文学の分野です。プロフィールにも書いてありますが、わたしの大学時代の専攻は国文学でしたから、その分野において人間学というものを考えてみたいと思っているのです。
これまでのわたしの話のなかでは、「文学」はほとんど登場しませんでした。人間学の基礎づけのためにまずもって必要なのは哲学ですから、わたしは哲学(とりわけ「情然の哲学」)とのリエゾンにおいて人間学について考えてきたわけです。
それがわたしの人間学研究の基礎編であるとするならば、これからは応用編ということになるかもしれません。あるいは、総論に対する各論ということになるかもしれません。いずれにしても、これまでの考察をさらに深掘りしたいという気持ちから新しい講座をはじめることにしたわけです。
では、人間学が文学とリエゾンすることで、どのような成果が期待できるのでしょうか。
近代以後においては小説が文学の主要なジャンルになるので、ここでは小説を書く人間、すなわち小説家というものについて考えてみましょう。
小説家が書いた作品を人間学の見地から見るとき、それは、個人の作品であると同時に人類が生みだした作品であると見ることができます。
もしもどこかの星に人間と同じような知性を持った宇宙人がいるとすれば、彼らはわたしたちが書いた小説を「地球文学」のカテゴリーに入れることでしょう。
そしてもちろん、地球文学を鑑賞するのは地球人です。菅野氏の人間学によれば、わたしたち人類はホモ・シグニフィカンスですから、ホモ・シグニフィカンスがホモ・シグニフィカンスの作品を鑑賞するわけです。
ホモ・シグニフィカンスとしての小説家
ここでホモ・シグニフィカンスという概念を簡単に復習しておきましょう。
菅野盾樹氏は人間の存在をホモ・シグニフィカンスととらえ、その基本構造を「身体・言語・心」の三重構造とみなしました。
この術語を翻訳すると、「記号機能を営む人」(『人間学とは何か』p71)になります。
これは、デカルト以来西洋の哲学を支配してきた「心と体」の二元論では人間の存在は捉えられないという立場から出された新しい概念ですが、この思想は「心と言語の類比説」がベースになっています。
心は言語とほぼイコールであり(もちろん全く同じということではありません)、言語は人間の心にも体にも浸潤している、という考え方ですね。
これはたしかにとても興味深い考え方で、二項対立的な近代哲学のパラダイムを乗り越え、人間存在の真実に一歩近づいたような感があります。
ただし、わたしが思うに、この概念には少なくとも二つのウィークポイントがあります。
一つは、「記号機能を営む人」という定義では、わたしたち人間がその五感において日々感受しているクオリアの問題が説明できない、ということ。
もう一つは、わたしたちがそれぞれの個性において存在しているという事実が説明できない、ということです。人間の個性によってもクオリアの感じ方は異なりますから、やはり「個性」を無視して人間を論ずることはできないでしょう。
このあたりの問題を論ずると話が難解になるので深入りは避けますが、要するに、「ホモ・シグニフィカンス」は人間を哲学のフィルターを通して見た場合にそう見える、ということなのです。
そうした意味で、哲学の研究に従事する人たちは典型的なホモ・シグニフィカンスと言えるかもしれません。
彼らは、「記号機能」の代表格である「言語」を駆使して世界について考えようとしている人たちです。したがってもちろん、哲学には哲学としての意義があり、人間学の研究を進めるうえで哲学的な思考はまずもって必要なものだといえるでしょう。
しかしながら、哲学には哲学としての限界もあります。
それは、わたしたち人間が日々感じている「クオリアの実相」を言語によって究明することができない、という点です。
そこで登場するのが、小説家という存在なのです。
哲学者も文学者も、ともに言語を用いて著作活動をする点は同じですが、両者の言語の用い方には大きな違いがあります。
哲学者は抽象的な概念を用いて世界の本質について思考するのに対し、文学者はその作品のなかに具体的な人間を登場させます。
哲学者が描き出すのは抽象の世界であり、文学者が描き出すのは具体の世界です。
これは、概念の世界とクオリアの世界と言い換えてもいいかもしれません。
わたしたちは優れた音楽作品によって音のクオリアを堪能し、また優れた美術作品によって色彩のクオリアを堪能します。それと同じような意味で、わたしたちは優れた文学作品によって「人間世界のクオリア」を堪能するのです。
では小説家は、言語という「記号機能」を使ってどのようにして「人間世界のクオリア」を表現するのでしょうか。
それは、描写という方法です。
小説のなかには、風景描写や人物描写や心理描写があります。あるいは、人と人との会話があります。小説のなかの会話は現実の会話をそのまま写したものではないので(そこには必ず小説的な処理が施されています)、小説のなかの会話も作者による一種の描写だと考えてよいでしょう。
この描写という方法を駆使して作家はクオリアの世界を創り上げ、わたしたちはその世界を小宇宙として認識することになるわけです。
とするならば、文学者もまた哲学者と並んで典型的な「ホモ・シグニフィカンス」であると考えてよいでしょう。
では、文学と人間学のリエゾンの問題についてもう少し考えてみましょう。

人間学のテーマと小説のテーマ
『人間学とは何か』では、第7章以降、人間学にとって重要な五つのテーマが扱われています。すなわち、「〈人格〉としての人間」(第7章)、「子供と大人」(第8章)、「性を生きる人間」(第9章)、「人生の意味と無意味」(第10章)、そして「死」(第11章)です。
これらのテーマは人間学にとって欠かせないものですが、同時に文学の主要テーマであることも自明のことですね。
たとえば、小説のなかに登場する人物はみな個性ある人格を持っており、多様な個性が融和したりぶつかりあったりして物語が進んでいきます。
また、「子供と大人」というテーマも文学にとって重要です。日本の近代文学のなかにも「子供の成長」や「青年から大人への成長」をテーマとする作品は多く、一例として世間によく知られているものを挙げるなら、夏目漱石の『三四郎』(1908年)や、森鴎外の『青年』(1910年~1911年)や、志賀直哉の『暗夜行路』(1921年~1937年)や、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』(1934年)や、下村湖人の『次郎物語』(1937年~1946年)や、山本有三の『路傍の石』(1937年~1938年)や、井上靖の『しろばんば』(1956年)などがすぐに思い浮かぶでしょう。
それから、「性を生きる人間」というテーマも長らく文学のテーマとして扱われてきたものです。たとえば、大江健三郎(1935〜2023)には『性的人間』(1963年)という小説があるし、吉行淳之介(1924〜1994)は生涯を通じて人間の性の問題を小説のなかで扱っています。
というより、日本の現代作家のなかで性の問題を扱わなかった人のほうがむしろ少数派でしょう。
では、「人生の意味と無意味」というテーマはどうでしょうか。
こちらも言うまでもなく、文学のなかでよく扱われるテーマです。主人公が人生の意味を模索する小説などは無数にあるし、また、「人生これ無意味なり」と断じて自ら命を立つ事件なども小説のなかに多くあります(もちろん現実の世界にも多くあるでしょう)。
また、人間の「死」の問題についても同様です。死はわたしたちにとって避けられないものですから、これが文学のテーマにならないはずはありません。
いくつか例を挙げておきましょう。
森鴎外の『舞姫』(1890年)や、夏目漱石の『こころ』(1914年)や、有島武郎の『或る女』(1919年)や、武者小路実篤の『愛と死』(1922年)や、芥川龍之介の『歯車』(1927年)や、太宰治の『人間失格』(1948年)や、野間広の『崩壊感覚』(1948年)や、川端康成の『千羽鶴』(1949年)や、大江健三郎の『万延元年のフットボール』(1967年)や、村上春樹の『ノルウェイの森』(1987年)などです。
話をまとめてみましょう。
次回からはじまる新しい講座のなかでわたしが作家の業績に注目するのは、彼らが哲学者とはまた別の意味で典型的なホモ・シグニフィカンスとして活動しているからです。
しかも、作家たちは哲学者とは違って、わたしたちが日々感受しているクオリアの世界を作品のなかに描き出そうとしています。これは、物事をいちど抽象的な概念に還元してから思考を展開する哲学者にはできないことなので、わたしは哲学者よりもむしろ文学者に注目しているのです。
新しい講座の概要
最後に、次回からの講座で具体的にどの作家を取り上げるのか、あるいはどのようなテーマを扱うのか、ということについて話しておきましょう。
これはあくまで現時点での予定ですが、はじめに何回か日本の近代文学の諸問題をとりあげ、それから日本の古典文学の話へと移行したいと考えています。
ただし、時代の順に語るというわけではなく、話のテーマはその時々の判断で決めることになります。
ちなみに、わたしが今とりあげてみたいと思っている作家は、以下の人たちです。
夏目漱石・森鴎外・芥川龍之介・谷崎潤一郎・三島由紀夫・川端康成・大江健三郎・安部公房・小林秀雄・江藤淳・村上春樹など。
(おもしろいことに、夏目漱石から小林秀雄までの九人が東大出身であり、江藤淳が慶應、村上春樹が早稲田の出身です。また、現在生存しているのは村上春樹のみです。)
小林秀雄と江藤淳は文芸評論家ですが、近代文学の歴史に大きな足跡を残した人であるため、その功績を称えるという意味も含め、この二人の文人をわたしなりの視点から扱ってみたいと考えています。
また、古典文学においては、紫式部と清少納言、それから鴨長明と吉田兼好、和歌の分野では藤原定家、江戸文芸では井原西鶴と松尾芭蕉などをとりあげるつもりです。
(ただし、これらの人たちの作品をすべてとりあげると30回を優に超えてしまいますから、そのあたりは適宜調整することになると思います。)
考えてみると、人間学の研究において方法的な多元主義が打ち出されていながら、文学とのリエゾンのなかで人間学を語るといった試みはこれまでなかったように思います。
そういう意味では、「文学と人間学」には、人間学研究の新しい試みとしての意義もあるかもしれません。
結局、次回からの講座に何らかの独自性があるとすれば、それは、「文学談義と人間学談義の融合」ということになるでしょうか。

では、そういうことで。
次回、すなわち「文学と人間学」の第1回は、「作家たちの文明批評」というテーマで話してみようと思います。
そこでとりあげるのは、漱石や鴎外をはじめとする日本の近代作家たちですが、彼らは自分たちに与えられた時代をどのように受け止め、そしてどのように生きたのか、という点について考えてみたいと思います。
では、これをもって「人間学の現在」の講座をすべて終了したいと思います。
三年数ヶ月にわたってわたしの話におつきあいいただき、ありがとうございました。
次回からの新しい講座をお楽しみに。
(関根均 せきねひとし)
1960年生まれ。慶応大学卒業。専攻は国文学。2010年日本人間学会に入会。現在、研究会員として人間学の研究に取り組んでいる。





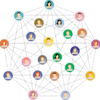




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません