人間学の現在(12)
今回から数回にわたって、『情然の哲学』について解説します。
わたしなりの視点からの解説なので、至らない点があるかもしれませんが、その点はあらかじめご了承ください。
この書籍は、入手してもらえればそれに越したことはありませんが、なければないで結構です。
わたしのこの講座は、不特定多数の方々を対象としたウェブ講座ですから、これまでどおり、お時間のあるとき、そして気が向いたときにご訪問ください。
ちなみに、この講座は当分の間、月に一度の頻度で更新していく予定です。

『情然の哲学』の魅力
『情然の哲学』はわたしにとって身近な書物ですから、書斎の本棚の手の取りやすい場所に保管してあります。
「読書百遍意自ずから通ず」という格言があるように、書物というものは、何度か読んでいるうちに、その書物ならではの持ち味が自然とわかるようになるものです。
わたしたちは日頃、いろんな機会にいろんな人と知り合いますが、何度か交流しているうちに、その人と親しくなれるかどうかは自然にわかってくるものですね。
書物とのつきあいも、それに似ています。
長く愛読する書物もあれば、あるタイミングで古本屋に売ってしまうような書物もあります。
『情然の哲学』はわたしの愛読書のひとつですが、この書物の魅力についてあらためて考えてみると、およそ次のようなものになります。
● 一流の発想力
● 一流の学識
● 一流の叙述力
● 一流の構想力
● 一流の図解力
これだけバランスよく一流のものが揃っていれば、おのずから「名品」になるわけで、どうやらこの作品が持っている溌刺とした生命力にわたしは心ひかれているようです。
また、この書物の魅力についてもう少し踏み込んで考えてみると、この書物には何かしら全人的なものがある、という点が挙げられます。
「情然」という発想はすぐれて宗教的なものでありながら、そこに展開される思想はきわめて哲学的であり、また、自身が立てた仮説から現実世界の現象をこまやかに説明する態度は、とても科学的です。
すなわち、この書物のなかには「宗教」と「哲学」と「科学」がごく自然なかたちで融和しており、なおかつ著者自身は芸術家(画家)だというわけですから、まるで、かのレオナルド・ダ・ヴィンチの仕事と重なり合うかのような部分がいくつもあります。
実際のところ、この『情然の哲学』がひとりの人物によって書かれたものであるとすれば、控えめに言っても、こういう本を書くひとはダ・ビンチのような天才でしょう。
ここでは、この書物の成立事情にまで立ち入る余裕はありませんが、何はともあれ、このような斬新な哲学が書物のかたちで存在していることは、わたしたちにとって大いなる福音です。
この書物にはいまだ類書というべきものがなく、孤高の存在として、ほかの多くの書物のなかに埋もれているような状態です。
いまはそうであっても、名著は名著として、いずれ世の中から正当な評価を受けるときがくることでしょう。
では、『情然の哲学』の解説に入ります。
哲学の原点回帰
わたしが通っていた中学の校歌には「真理の光身に受けて」という一節がありましたが(いまでもわたしの母校ではこの校歌が歌われています)、「この学校でほんとうに真理が学べるのだろうか」という疑問を中学生のわたしは抱いていました。
たしかに、中学で学ぶ理科や数学は科学的真理の一部かもしれませんが、歴史を学んでみると、人類の歴史は血にまみれた闘争と殺戮の繰り返しです。真理がないから人々は憎み合い争い合うのではないかと、わたしには思えてなりませんでした。
「とんでもない世界に生まれて来ちゃったな。ひょっとすると、ここは真理のない世界かもしれないぞ」と、中学生のわたしは心ひそかに思っていたものです。
案の定、高校に行っても大学に行っても、宇宙の真理を教えてくれる先生はわたしの前に現れることはありませんでした。
真理がないので人々は真理を探求してきたのかもしれませんが、人類の真理探求のその努力については、大いに認めるべきでしょう。
たとえば、古代のギリシア哲学。それから、古代中国の諸子百家と呼ばれる人たちのさまざまな世界観や人生観。
話を哲学に限っていえば、人類における哲学の発祥の地はギリシアであり、ギリシア哲学の発端は、自然哲学と呼ばれるものでした。
けれども、当時はまだ科学のない時代でしたから、「世界は何によってできているか」という問題に誰も答えを出すことができませんでした。
そのため自然哲学はほどなくして停滞し(いろんな説が出されても検証のしようがありませんから)、ソクラテスの登場などもあり、その後の哲学者たちの関心は人間学的なテーマに向かうことになります(ソフィストの哲学については省略します)。世界の根源は何か、という問いかけから、人間とは何であり、どう生きることがよいことなのか、という問いかけに人々の関心がシフトしたわけです。
だいぶあとになってから、「世界は何によってできているか」という自然哲学の課題は、自然科学が引き受けることになります。
ところが、自然科学は「なぜ」を問うことができないので、科学的な手法で「物」の世界をどこまでも探究していくと、究極の存在は「エネルギーの揺らぐ真空の場」だった、という謎めいた話になってしまいます。
自然科学は「神」の問題を扱うことができませんから、その「真空」の背後に「神」がいるのかいないのか、そういうことは分かりません。
それで、哲学は哲学、宗教は宗教、科学は科学、ということになってしまったわけですね。
話を戻して、自然哲学についてもう少し詳しく見ていきましょう。
自然哲学については、高校で履修する「倫理」の教科書にも記述があります。
引用してみましょう。
紀元前6世紀の初め小アジアのイオニア地方に建設されたギリシア人の植民都市で、自然のすべてのものが生まれてくる根源(アルケー)とは何か、を探求する自然哲学が誕生した。
自然哲学の祖とされるタレスは「万物の根源は水である」と説き、その根拠の一つとして、水が種子の発芽をうながすことをあげている。ヘラクレイトスは、すべてを焼きつくす火がすべてを生み出す根源であると考えた。彼は「同じ川の水に二度と足を入れることはできない」と語り、万物はとどまることなくたえず変化すると考えて、「万物は流転する」と説いた。エンペドクレスは、土・水・火・空気の四つの元素が、愛によって結合し、憎しみによって分離して万物が生成すると説いた。デモクリトスはそれ以上分割不可能な原子(アトム)の結合と分離によって、万物が生まれると説いた。
このように自然哲学は、世界の成り立ちを神話にたよらず、理性(ロゴス)によって筋道をたてて合理的・統一的に説明しようとした。哲学は、このような自然の根源についての問いかけからはじまったのである。(山川出版社『現代の倫理』p28〜29)
「哲学は、このような自然の根源についての問いかけからはじまったのである」という箇所はとても重要です。
トランスモダンの哲学がもしもあるとすれば、それはわたしたち人類が「世界に対して初めに抱いた疑問」に対し正面から答えを出すものでなければならないからです。
「倫理」の教科書の28ページには、自然哲学者の主張を一覧にした表が掲載されています。
それは次のようなものです。
●タレス 水
● ピタゴラス 数
● ヘラクレイトス 永遠に燃える火
●パルメニデス 有りて有るもの
● エンペドクレス 土・水・火・空気
● デモクリトス 分割不能な原子
では、この表の末尾に、「勝本義道 情然」という一列を加えたらどうでしょうか。
自然哲学者たちの出現と勝本氏の登場のあいだには二千数百年という時間の隔たりがありますが、もともと人類の思想史の発展とはそういうものであるのかもしれません。
138億年といわれる宇宙の歴史に比べれば、二千数百年という時間は小さなものであるともいえますね。
ただし、自然哲学者と勝本氏のあいだに「アルケー」の問題について正面から取り組んだ哲学者がまったくいなかったかというと、決してそうではありません。
哲学者と呼ばれるひとたちはみな多かれ少なかれ、「宇宙の根源」について思いを巡らせていたと思いますが、このテーマに関してわたしたちがすぐに思い浮かべる哲学者といえば、やはりライプニッツでしょう。
ライプニッツ(1646年〜1716年)は「倫理」の教科書にもかならず登場する有名な哲学者ですが、残念ながら、その哲学の中身に関する説明はほとんどありません。
そこで、「哲学叢書」としても役に立つ岩波文庫を調査してみると、この哲学者には『モナドロジー』が目録のなかにあることがわかります。
岩波文庫は各分野の古典作品を集めた文庫ですから、人類の知的遺産の集大成と見ることもできます。作品の巻頭や巻末にはおおむね、識者(多くの場合その分野の第一人者)による解説がついているので、ライプニッツの生涯の歩みやその哲学の概要について学びたい方は、岩波文庫版の『モナドロジー』を一読するとよいでしょう。
ありがたいことに、岩波文庫の『モナドロジー』はつい最近(2019年4月)新訳が上梓され、とても読みやすいものになりました。巻末には「訳者あとがき」としてモナドについてのわかりやすい解説も付属しているので、引用しておきましょう。
モナドは、古代ギリシアのピュタゴラス派以来の概念であり、すでにプラトンの『パイドン』や『ピレボス』に用いられている。16世紀後半になると、いろいろなモナド論が構想されている。ジョン・ディーは、万物を象徴的に集約するモナドの構想をもち、『象形文字のモナド』を著し、17世紀初めのカバラ的神秘主義の流れにも大きな影響を与えている。哲学史を見るとモナドは、ニコラウス・クザーヌスやジョルダーノ・ブルーノにおいて、世界を構成し、世界の多様を映す一なるものと捉えられている。ブルーノは、宇宙を構成する単純な要素として、モナドどうしの結合から宇宙のさまざまな在り方を説明する。ただし、そうしたモナドそのものは不滅であった。ケンブリッジのプラトニストたち、ヘンリー・モアやファン・ヘルモントは、宇宙を構成する動的・心的要素と解して、これらモナドが宇宙的神性に対して有機的関係に立ち、神性を自らにおいて現すとした。こうした諸原理を継承しつつライプニッツは独自の形而上学を組織する。(p240~241)
これを読むと、ギリシア哲学のアルケーの問題は、西洋哲学の歴史のなかに脈々と受け継がれてきたことがわかりますね。
ライプニッツは、その伝統の流れを受けてアルケーの問題に取り組み、新たな活路を見出しますが、モナドはそもそも物理的に存在するものではないので、かれの仕事は結局、一つの形而上学の構築にとどまります。『モナドロジー』はよくもあしくも哲学であり、それ以上のものではありません。ただ、時代的な制約を考慮に入れるならば、まだ近代の初期であったあの時代に世界の根源についてあそこまで考えたわけですから、やはりライプニッツは偉大だということになります。
20世紀に入り、科学の分野に量子力学が登場して、わたしたちはようやく、ミクロの世界を共通の言語で記述できるようになりました。しかしながら、では科学の発達によってアルケーの問題に答えが出るかというと、そういうものでもありません。「物質の根源」と「世界の根源」が同義のものであるとはかぎらないからです。
「情然」という概念は、自然科学のなかから生まれたわけではないし、哲学のなかから生まれたわけでもありません。いわんや、宗教のなかから生まれたわけでもありません。
どこの分野のなかにもなかった新しい概念が、あるときひとりの人物の頭のなかに宿り、その概念を言語化すると「情然」というものになった、というのが、ことの真相ではないかとわたしは考えています。
そのため、なぜ「アルケー=情然」なのかをわかりやすく説明することが、今後のわたしの任務となります。
もちろん、その説明はすでに『情然の哲学』のなかにありますが、それは誰にもわかるレベルのものではありません。そこで、わたしは、この講座のなかで「情然」の概念を噛み砕いて説明し、人々がこの新しい哲学について学ぶきっかけをつくりたいと思うわけです。
『情然の哲学』の功績
アルケーの問題は、科学の問題であるとともに哲学の問題です。
宗教、とりわけキリスト教では「アルケー=神」ということがすでに定まっていますが、なぜそうなのかという問題についてはまったく答えることができません(答えようとする発想自体がありません)。たとえば、アウグスティヌス(354年〜430年)は「神の無からの創造」を説きましたが、そうすると「アルケー=無」ということになり、科学的な思考が不可能になってしまいます。
また、先にも述べましたが、現代の科学を極めれば「世界の根源」が分かるわけでもありません。
科学の分野にも多くの学説があり、研究の領域が細分化すればするほど、そこから生まれる理論はより複雑なものになります。
専門家でなければわからないような理論のなかに「真理」(アルケーが何であるかという解答)が隠されているとすれば、ほとんどの人は真理から疎外されていることになりますね。
科学と宗教と哲学のいずれの分野にも深い洞察を投げかけながら、当の著作そのものはいずれの分野にも属さないところに、『情然の哲学』の魅力があるといってよいでしょう。
また、アルケーの問題を解き明かしたこともこの著作の功績の一つですが、わたしが思うに、『情然の哲学』には多面的な功績があります。それらを箇条書きにまとめると、以下のようなものになるでしょう。
●自然哲学のアルケーの問題に対して、一つの答えを出したこと。
●ソクラテスの人間学的な問題提起に対して、一つの答えを出したこと。
● 菅野盾樹氏の「ミニマム人間学」の限界に対して、新しい道を開いたこと。
● トーマス・クーンが提起した「共約不可能性」の問題に対して、その解決の道を示したこと。
● 中身が定かでないトランスモダンの理念に対して、その具体的な思想内容を示したこと。
これらの功績の詳細については、この講座の今後の話のなかで折に触れ言及する予定です。
次回は、「アルケー=情然」であることの理由について説明します。
これは、新しい哲学の扉を開ける鍵となる問題ですから、とても重要です。
もしかすると、ギリシア時代の哲学者たちやライプニッツたちも、あの世でわたしの話を心待ちにしているかもしれません。
これはもちろん冗談ですが、それくらい価値のある話だと思ってもらってよいでしょう。
では、今回の話はこのへんで。

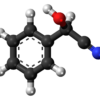









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません