人間学の現在(5)
前回までの講座で、人間学のルーツの問題から哲学の一領域として成立した「人間学」の問題まで、わたしが理解しているところのものを簡単に説明してきました。
わたしたちはいま、人間学についておよその輪郭を掴みつつあります。
そのため今回は、少しだけ学術的な世界に足を踏み入れて、「人間学が学問として成立する根拠とはどのようなものか」という問題について考えてみましょう。
人間学という用語は便利なもので、近年は書物のタイトルなどにもよく使われています。わたしたちはみな人間ですから、このテーマについては誰もが当事者であり、発言権を持っているのです。「おれだって人間なんだから意見を言わせろ」といった感じですね。
ですから、「〇〇の人間学」といったタイトルの書物は世の中にたくさんあります。ところが、それらがいわゆる人間学についての書物であるかというと、もちろんそうではありません。とするならば、「そもそも人間学とはどんな学問なのか」ということが問題になってくるわけです。「哲学的人間学」と銘打つ以上、そこには学問としてのなんらかの条件があるはずですから。
植物学や動物学においては、研究の範囲は明瞭に規定されます。言うまでもなく、植物学の研究対象は植物であり、動物学の研究対象は動物です。もちろん、ミドリムシなどはどちらにも属するような生物ですが、そうであるならどちらで研究してもいいわけです。そういう意味では、人間学の研究対象もあらかじめ規定されており、それはいうまでもなく人間です。しかしながら、人間について研究するのもまた人間ですから、そこにはどうしても、向かい合った二枚の鏡を覗き込んでいるようなややこしい事態が発生します。
人間学では、人間学の研究につきまとうこのような特性を「反射性」と呼んでいます。研究対象は明らかであっても、自分自身でもあるその対象にどう切り込んでいけばいいのか、という独自の困難がこの学問にはあるわけです。
人間は動物と違って、理性を持ち、言語を持ち、文化を持ち、文明を持ち、そして歴史を持っています。たとえば、猿の社会は百年たってもあまり変わらないでしょうが、人間の社会は百年も経つとずいぶん変わっていきます。その変化のすべてが好ましいものとは言えないものの、たとえば、科学技術の分野などには長足の進歩が認められます。つまり、人間自身が歴史とともに動いているわけですから、未来に対してつねに未知の可能性を秘めている人類をその当事者が捉えるということは、決して簡単なことではないのです。
ありがたいことに、人間学の探求はソクラテスによって適切なスタートを切ることができました。また、20世紀に入ってから、マックス・シェーラーらの努力によって人間存在の解明を主題とする哲学、すなわち人間学がひとつの学問として立ち上がりました。わたしたちはこのような歴史の流れのなかに立ち、あらためて人間とは何かという問いに取り組んでいるわけです。
人間学の成立根拠
では、人間学の成立の根拠とはどのようなものでしょうか。
人間学の周辺には、人間を素材とする多くの学問が存在しています。社会科学や人文科学の範疇に属する学問(経済学や心理学など)はすべて人間の存在が前提ですから、それらもまた人間学と無縁のものではありません。もちろん、歴史学や考古学なども然りです。また、自然科学の分野でも、医学のように人間の生理機能を研究する学問もあります。
ここでは、人間学と最も近い関係にある人類学との比較によって人間学の成立の根拠について考えてみましょう。
人間学はこの講座のテーマですから、すでにある程度の了解があると思いますが、人類学についてはまだ何の話もしていません。そこで、人類学という学問について簡単に説明しましょう。
人類学について最初に知るべき事柄は、この学問にはいくつかのテリトリーがあるということです。人類について研究する側面はいくつもあるため、この学問もいくつかの領域に分かれています。このあたりの事情については、日本人類学会という研究機関のサイトに簡便な説明が見出されるので、そちらを引用することにしましょう。
人類学は,「生物としてのヒト」を総合的に研究する学問で、ヒトとは何かを科学的に偏りなく理解し、実証的で妥当性のある人間観を確立することを目標としています。言い換えますと、人間自身について科学的な根拠に基づいた認識を得ることが人類学研究の最終的な目的となっています。それには下記の3つの観点が重要となります。
●人類の本質(他の生物種との共通性と異質性、人類の独自性・特質)
●人類の変異(集団や個体ごとの違い・ばらつき、およびその意味)
●人類の由来(起源と進化・変遷)具体的には、過去および現在の人類の解剖・生理・発育・運動機能・遺伝・行動・生態・文化、地球における人類の出現と変遷に関わる場所・時代・環境など、また、それらに関する人類と近縁な動物との比較などが研究項目として挙げられます。
現在の人類は「発達した文化を持つ生物種」という特徴を有するため、人類の身体形質を主対象として主に自然科学的観点から「ヒト」を探求する自然人類学と、人類の文化・社会を主対象とし主に人文科学的観点から「人間」を探求する文化人類学とに大別されることが多いのですが、人類学は、上記のように広く、考古学、民族学、民俗学、霊長類学、遺伝学。解剖学、生理学、古生物学、第四紀学、年代学などと接し重なりあった包括的な科学です。
上記の説明からもわかるように、人類学は「生物としてのヒト」を科学的に理解しようとする学問であり、哲学とは別のものです。ところが、人間学は人間について哲学的に理解しようとする学問です。ですから、人間学は必然的に哲学的人間学を意味するものとなり、そこに人間学の独自性があるといえます。
たとえば、人間の精神を科学的に研究しようというのであれば、それは精神医学になるでしょう。また、人間の心の動きなどを科学的に研究しようというのであれば、それは心理学になるでしょう。このように、人間についての科学的なアプローチは人間学以外の学問としてすでに成立していますから、人間学の牙城はどうしても「哲学」ということになるわけです。
以上の説明で、人間学のアイデンティティの問題(ならびにポジショニングの問題)は整理できたのではないかと思います。ただし、人間学が哲学の一領域だとしても、それがただちに形而上学を意味するわけではありません。人間学の研究対象はあくまでも人間ですから、人間学に隣接する諸学問の成果も積極的に取り入れる必要があります(取り入れるというよりもつながり合うと言ったほうがいいかもしれません)。それが哲学である以上、人間についての思弁的な考察ももちろん行われますが、それのみに終始する学問ではないのです。
人間学の意義
次に、人間学の意義という問題について考えてみましょう。
周知のように、わが国では学問の自由が憲法で保障されています。世の中には数多くの学問がありますから、学問の道を志す人は、まずは自分が取り組む学問を選ばなければなりません。そうなると、ひとは必ず探求する価値があると思う学問を選ぶことになるでしょう。
学問自体は価値の問題から独立したものであるとしても(外在的な価値観の支配下にある学問はそもそも学問とは言えないでしょう)、わたしたちの人生は価値の問題を避けて通ることができません。たとえば、日常的な買い物ひとつをとってみても、ひとはつねによりよい商品を購入しようとします。たいていは、類似の商品を比較してより価値が高いと思えるものを選択しますね。これなどはまさに、人が生きるうえでの価値の問題と言えるでしょう。
もちろん、人間学がほかの学問と比較して価値があるとかないとか、そういった議論はもとより成立しません。これはすべての事象に当てはまることですが、価値というものは当該の事象に不動の客観物として付属するものではないからです。ですから、人間学の意義の問題はあくまでもわたし個人の見解となりますが、この講座は人間学の道案内を趣旨とするものですから、この問題について少し掘り下げて話してみましょう。
わたし自身が人間学に対して関心を持ったのは、それが人間を研究テーマとする哲学であったからです。
哲学というと、何やら難しい学問のように思えますが、物事について深く考えようとすれば、ひとはみな多少なりとも哲学者になるものです。実際、世の中で活躍している人の多くは自分自身の哲学を持っており、「〇〇の人生哲学」といった書物なども多く見受けられます。
また、人間についての哲学的な疑問に関しては、次のような言葉が広く知られています。
●われわれはどこから来たのか われわれは何者か われわれはどこへ行くのか
これは、フランスの画家ポール・ゴーギャン(1897〜1898)が19世紀の末に制作した作品のタイトルです。
人間学は、このような哲学的な問題について研究しようとする学問です。
先にも触れましたが、こうした問題はすでにソクラテスによって提起されており、長い歴史を通じて人類の思索の基本的なテーマとなってきました。わたしたち人間は「いちばん新しい動物」としてこの地球に現れていますから、どこから来たのかがわからないし、何者であるのかがわからないし、また、どこへ行くのかもわからないわけです。
(どこから来たのかという問題に関しては、今から百数十年ほど前にダーウィンが進化論を唱え「サルが進化してヒトになった」と主張しましたが、それでこの問題に解答が出たわけでもありません。)
仮に神という存在を想定したとしても、このような問題が簡単にかたづいてしまうとは思えません。
わたしは個人的には、神学は人間学のすぐ隣にあると思っていますが、「神学と人間学」というテーマは前人未到のもので、このテーマを基軸としてひとつのまとまった世界観を構築するには、おそらく多大な労苦が必要となると思われます。
結局のところ、人間学はいまだに多くの課題を抱えている学問なのです。
人間についての根本的なところがまだよくわかっていないわけですから、「謎を秘めている学問」と言ってもいいでしょう。
ただ、謎を秘めているものには魅力があることも事実です。
人間についての哲学的な思索を武器として世界について根本から考えてみること。
このような行為のなかにこそ「人間学の意義」があるのではないかとわたしは思います。
秘境をめざして旅を続けることのなかには、「未知との遭遇」が期待できますね。
わたしは現在、多くの謎と遭遇する秘境の旅を続けている最中であり、そのようなチャンスを提供してくれている日本人間学会の会員であることに、少なからぬ生きがいを見出しているのです。
人間学の意義について個人的なことを言うなら、そのようなことになります。
今回は、人間学の成立根拠についての話と、人間学を学ぶ意義についての話でした。
次回は、「人間学の必要性」というテーマで所見を述べてみたいと思います。


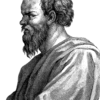
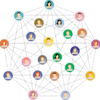




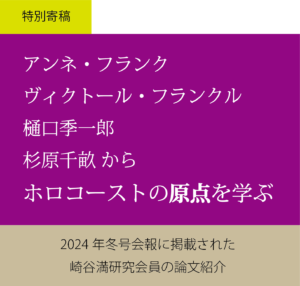






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません