人間学の現在(29)
前回の講座で予告したとおり、今回は「新しい人間学」の構想についての話です。
わたしが現在構想している「人間学」が何に対して「新しい」のかというと、やはり、これまでの人間学研究の一連の流れに対して、ということになります。
こんなふうに言うと、「ひとりで新しがっているだけじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、わたしとしてはまぁ、新しくても新しくなくても、そういうことは大して重要ではないと思っています。ただ、これまでの人間学研究の文脈を踏襲するだけでは現在のわたしの世界観を語ることができないので、とりあえずそれを、新しい人間学、と呼んでおこうと思っているわけです。

人間の類型学を括弧に入れる
新しい人間学の構想について語るにあたり、まずは、「人間の類型学」を括弧に入れることからはじめたいと思います。
人間の類型学については、この講座のはじめのほうで取り上げているので、ここでは繰り返しません。わたしたちはそれぞれ唯一無二の個性を持っている存在ですから、それをいくつかのグループに分けようとしてもうまくいかないのは、当然といえば当然です。このあたりのこともすでにこの講座のなかで説明しているので、繰り返しは避けましょう。
人間のグループ分けを括弧に入れるということは、人間に対して「ホモ・◯◯◯◯」という捉え方をしないことです。たとえば、ホモ・サピエンスということばは人間の存在の一面をよくあらわしていますが、それはあくまでも一面に過ぎません。もちろん、ホモ・ロクエンスでもホモ・シグニフィカンスでも事情は同じです。
ですからそれは、一つのレッテルに過ぎず、ある角度から見た場合にはそう見える、といったことがらに過ぎないわけです。
では、わたしたちはこれまで、人間について考えるためのより適切な観点というものを考えてこなかったのでしょうか。
もちろん、そういうわけでもありません。
たとえば、マスロー(1908~70)という学者がいます。
この人は、高校の「倫理」の教科書にも定番で登場するほど著名な心理学者ですが、人間の欲求には五つのランクがあるという説を出しています。
教科書の記述を引用してみましょう。
欲求は一般的に、生命の維持のために身体的・生理的に欠くことのできない生理的欲求(一時的欲求)と、自己の個性の実現をはかることや他者に認められることを願う社会的欲求(二次的欲求)の二つに分けられる。
アメリカの心理学者マスローは、人間の欲求を分類し、低次から高次の順に五段階の階層を提示した。第一層には生理的欲求があり、これが満たされると第二層の安全と安定を求める欲求が生じ、これがかなえば愛情と所属の欲求、さらに自尊と承認の欲求へとすすんでいく。第一層から第四層までを欠乏欲求といい、下位の欲求が多少とも満たされることで、はじめて上位の欲求が生じる。そして、欠乏欲求がすべて満たされると、第五層の自己実現の欲求が生じる。(清水書院『高等学校新倫理改訂版』p12)
マスローはシェーラーのように人間のタイプを五つに分類したのではなく、人間が普遍的に持つ欲求を五つの階層に分類したわけです。
たしかにわたしたちは人種や国籍にかかわりなく、また性別や個性にもかかわりなく、マスローが分類したような欲求をみな持っていますね。
そして、これらの欲求がすべて満たされるとき、わたしたちはこの上ない幸福を感じる存在なのではないでしょうか。
であるとすれば、マスローのこの学説は、わたしたちの人生において大いに役立つものといえるでしょう。
そのため、わたしは人間の類型学を括弧に入れ、その代わりに、マスローのこの学説を「新しい人間学」の土台に据えようと思っているのです。
「情然の哲学」と新しい人間学
次に考えておくべきことがらは、「世界とは何か」という問題です。
すでに何度も述べているように、人間学の基本的なテーマは、人間の基本構造の解明と、よりよく生きるとはどういうことか、という問題についての探求です。
この二つのテーマは、菅野盾樹氏の『人間学とは何か』のなかでも詳しく解説されています。
問題自体はすでに、はるか昔、ソクラテスによって提起されてはいたものの、わたしたちは現在、この二つのテーマについて満足のいく答えを得ていません。
人間の基本構造の問題もいまひとつわかっていないし、いかに生きるべきかという問題についても同様です。
ですから、哲学的人間学というものは、これからあらためて基礎づくりをしなければならない学問の領域なのです。
少なくともわたしには、そのようなものとして捉えられるのです。
ただし、これもこれまで何度か述べてきたことですが、人間だけを見つめていても、人間とは何かという問題に答えを出すことはできません。
わたしたち人間は社会のなかに生きる存在であり、また自然界のなかに生きる存在ですから、人間を人間として生存せしめている世界そのものの本質がわからないかぎり、人間とは何かという問題にも答えを出すことができないのです。
そこで登場したのが、『情然の哲学』のなかに語られている世界観でした。
「情然の哲学」の内容については、すでにこの講座のなかでかなりのスペースを割いて解説しているので、ここでは繰り返しません。
この哲学をベースにすれば「人間」についての理解もぐっと深まるのではないかとわたしは思い、新しい人間学の構想について考えはじめたのでした。
「情然の哲学」は、アルケー(世界の初めにあったもの)を「情然」と見ることで新しい世界像の定立に成功しています。
情然という概念自体がそれまでになかった新しいものですから、必然的に、「情然の哲学」は新しい哲学となります。
その新しい哲学の観点から改めて人間について考えるとすれば、それもやはり必然的に、新しい人間学ということになるでしょう。
この哲学では、「情然」の状態から「原初格」が生まれ、その「原初格」からわたしたちのこの世界が生み出された、ということになっています。
また、存在の問題においても、その原理を「家族的四位構造」と見ることで、わたしたち人間がなぜ家庭のなかで生まれ、家庭のなかで育ち、成人してからは新たな家庭をつくり、老いた末に家庭のなかで死んでいくのか、という問題についても哲学的な答えを出すことに成功しています。
そのため、この哲学の世界観をベースにして新しい人間学を構想することは十分に可能ではないか、とわたしは考えているのです。
「神」と「原初格」の問題
ただし、既存の人間学や、マスローの学説や、「情然の哲学」などを学んでも、そこから新しい人間学のビジョンがすんなりと生まれてくるわけではありません。
なぜなら、「情然の哲学」も完結した哲学ではなく、それを人間学のベースとして援用する場合、わたしたちはいくつかの課題に直面することになるからです。
課題点はいくつかありますが、ここではそのうちの一つを取り上げておきましょう。
たとえば、『情然の哲学』に登場する原初格という概念。
このことばにはどことなく無機的な感触があり、また、西洋の形而上学のなかにでも出てきそうな雰囲気があります。
このことばを「神」に置き換えてみるととてもわかりやすくなるのですが、では「原初格」と「神」がイコールなのかというと、そうでもありません。
もしも「神」と置き換えて差し支えないのであれば、『情然の哲学』の著者は初めから神という言葉を使っていたことでしょう。
しかしながら、わたしたち人類はすでに数千年間も神ということばに馴染んできているので、いまさら神ということばの代わりに原初格ということばを使うわけにもいかないだろう、とわたしは思うわけです。
そこで、このあたりの問題をどうするか、ということが一つの課題となります。
わたしたちがまずするべきことは、神という概念をある程度明確にしておくことでしょう。
というのは、わたしたち日本人にとって、神というのはかなり曖昧な概念だからです。
神社に行っても神様がいるし、また教会に行っても神様がいますね。(ちなみにお寺に行けば仏様がいます。)
神社の神様と教会の神様が違うのは当然ですが、「原初格」に近い神といえば、やはり教会の神様ということになるでしょう。
このあたりまではすぐにわかることですが、では、キリスト教の神と原初格ではどこがどう違うのか。
この問題についてここで詳しく話すことはしませんが、こうしたことがらが「新しい人間学」にとっての喫緊の課題としてある、ということだけは今の段階で指摘しておきましょう。
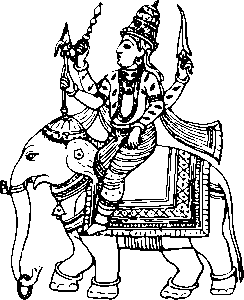
人間学の普及のために
最後に、わたし自身の今後の活動のおよその方向について話しておきます。
まず、当会のホームページに連載しているこの講座ですが、すでにお知らせしてあるとおり、「人間学の現在」は次回が最終回となります。
そして、「文学と人間学」というタイトルの新しい講座の連載を、11月からはじめる予定です。
この新しい講座の内容については、次回の講座でお話しします。
そして、今回その概略を紹介した「新しい人間学」の試みについては、当会が年四回発行している会報のなかで展開していく予定です。
こちらも連載のかたちをとり、「新しい人間学」の構築のための予備的な考察を主な内容にする予定です。
連載をするには何かしらのタイトルが必要ですが、今の時点でわたしはそれを、「人間学アラカルト」にしようかと思っています。
アラカルトというのは、もしかすると、若い読者の方にとってなじみの薄いことばかもしれません。
昔はやったことばというわけでもありませんが、最近、アラカルトということばはあまり目にしないように思います。
アラカルトの語源はフランス語で、コース料理に対し、客が自由に選べる一品料理を意味することばです。
はじめは料理の分野で使われていたこの「ア・ラ・カルト」がやがて他の分野にも進出し、「好きなものをいろいろ選べる」といった意味としていろんな場面で使われるようになりました。
したがって、「人間学アラカルト」は、毎回のテーマを自分の好みで自由に選べるという、当事者にとってまことに都合の良い、これぞまさしく自己愛に溢れたタイトル設定(笑)、ということになります。
これこれのテーマで記事を書いてくれませんか、と依頼されると、執筆者にはそれだけで何かしらのプレッシャーがかかるものです。
自分で自分にプレッシャーをかけてしまうとそれだけで原稿の執筆が苦行になってしまうので、どうせやるならおたがいに楽しくやろう、といったほどの意味で、「人間学アラカルト」(別名「人間学なんでもあり」)に決めさせていただいた次第です。
物事は何でもそうですが、楽しければ続くものです。
人間学については、今もなお、語りたいと思うことが数多くあるため、記事の連載はマラソンレースのような趣もあります。
しかしマラソンだとやはり苦行になってしまうので、マラソンではなくウォーキングとして、途中の景色も楽しみながら、時々は寄り道などもして、マイペースで活動を続けていこうと考えています。
今後のわたしの取り組みの三つ目は、「月例座談会レポート」の作成です。
当会では月に一度、有志の研究会員の方々が集まって座談会を行っていますが、その活動もかれこれ三年余り、欠かさずに続いています。
リモートで行われる会合のためその内容はすべて録画されていますが、発言の内容を編集して記事にするところまでは手が回りませんでした。
話の内容を文字に起こして記事にする人がいれば問題は解決するため、その作業をわたしが担当することになったわけです。
ということで、今年の夏号の会報から「月例座談会レポート」の記事が登場することになります。
以上がわたしの今後の活動の大まかな方向性です。
いずれにしても、すべては人間学の普及のため。
当会が研究のテーマとしている哲学的人間学は、文化人類学などにはない独自の魅力を持っているため、深堀りをすればするほど面白いものになっていくようです。
話はちょっとずれますが、とある成功哲学の学説によると、「面白くなってきたぞ」というフレーズを口癖にすると人生は自然に好転していくとのことです。
たしかにそうかもしれません。
わたしはこの学会に入会しておよそ14年になりますが、最近、「面白くなってきたぞ」と思うことが以前よりも増えてきています。
本業の仕事とは別に上記の三つの仕事をこなすのは少々きついことではありますが、仕事が面白くなってきているので、その勢いで乗り越えていけたらと思っています。
では、今回の話はこのへんで。
(関根均 せきねひとし)
1960年生まれ。慶応大学卒業。専攻は国文学。2010年日本人間学会に入会。現在、研究会員として人間学の研究に取り組んでいる。






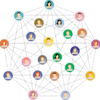



ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません