人間学の現在(10)
前回の講座では、「ホモ・シグニフィカンスの人間観」についての解説を行いました。
わたしはこの人間観を、現在の人間学における最も有力な見解であると考えていますが、この学説が完璧なものであり、人間学の研究が菅野盾樹氏の登場によって終着点に到達したとまでは思っていません。
そこで、今回は、「ミニマム人間学」を提示した菅野氏の仕事(おもに『人間学とは何か』の著作を指します)の功績とその限界について考えてみたいと思います。
「ミニマム人間学」の功績と限界
「ミニマム」という英語は最小限という意味で、マクシム(最大限)とともにアンプの音量表示などによく使われます。
菅野氏は自らの人間学をミニマム人間学と呼称していますが、このことは逆に言うと、菅野氏以前には人間学の基礎づけすら充分なされていなかったことを意味しています。
わたしが思うに、菅野氏の登場によって、人間学は揺るぎない基礎を現代哲学のフィールドに築くことができたのです。これがなんといっても、菅野氏の仕事の一番の功績であるとわたしは考えています。菅野氏は自身の人間学研究が「ミニマムなもの」であることを充分承知しているので、まずはこの点に関する氏自身のことばに耳を傾けてみましょう。
本書は「人間学」という学問を体系的に記述し展開することを目的とするものではまったくない。また「人間学」の全体像をいわばスケッチとして描き出すことを目指したものでもない。私はもともと「人間学の基礎」という表題をこのテクストにつけようと考えていた。その表題には筆者として二つの意味を込めたつもりである。一つには、この表題は、現代において「人間学」という総合的な学問が果たして可能であろうか、可能だとすればそれにはどのような学問的制約がともなうのか、という問題意識を表している。本書はそうした意味で人間学の「基礎」についての考察であり、筆者なりの基礎の敷設を読者に提示する試みである。
第二にこの表題は、「人間学」を樹木にたとえるなら、本書の課題がもっぱらその根や幹にあたる部分についての考察に限定されることを意味している。人間学の基幹部分を、本書では「ミニマム人間学」と名づけている。それは人間の基礎的な存在構造を明らかにすることを任務とする人間学的探究の部面である。したがって本書では、人間の存在構造のさまざまなディテールを取り上げて論究することはほとんどしていない。すなわち、社会的動物としての人間が営む経済、法、倫理、習俗などの諸問題には、意図的に立ち入ることをしていないし、文化を営む動物としての人間が創りだす科学、技術、藝術、儀礼、宗教などについても、同様に考察をあえて控えている。以上のような意味あいで、本書の眼目はあくまでも「人間学の基礎」についての考察にある。(『人間学とは何か』p6〜p7)
菅野氏は、自身が提示する人間学がどのような限界をもっているかということにも十分に自覚的ですね。
『人間学とは何か』において、菅野氏は、時代の要請でもあった「人間学の基礎」の構築を見事に成し遂げたといえるでしょう。なにごとであれ、基礎を築くのは重要な仕事ですから、少なくともこの一点において、菅野氏の仕事は不朽のものであるとわたしは思います。
すでに述べたように、「ホモ・シグニフィカンスの人間観」の登場の背景には、20世紀に成立した言語学や分子生物学の存在があります。ところが、菅野氏はそうした学問の成果とともに仏教倫理学の知見も紹介しています。そのあたりの視野の広さも氏の著作の魅力のひとつでしょう。
その部分は今後、宗教と人間学の関わりの問題を考える上で重要な視点となるため、少し長くなりますが、以下に該当箇所を引用しておきましょう。テキストをお持ちの方は、58ページを開いてみてください。
参考までに付け加えておくなら、人間存在の身体-言語-心の三重構造という把握は、古代東アジアの人間観でもあった。仏教の思想では、「身口意の三業」ということをいう。〈身〉は身体を、〈口〉は〈語〉とも漢訳されて言語を、〈意〉は心を意味する。そしてあらゆる〈業〉は身業つまり身体的行為、口業つまり言語表現、意業つまり心的作用の三業に包括されるという。こうした把握のすぐれた点は、人間のなしうるすべての行為(業)に基づいて人間の存在構造を規定したことであろう。言語がすでに行為として正確に捉えられている点は特筆に値する。こうした認識が西洋で確立したのは二十世紀になってからにすぎない。
またこの存在構造の把握がそのまま徳の倫理学へ展開してゆく点にもすぐれた洞察が含まれている。すなわち、仏教倫理学の体系は、基本的に身口意の悪業を戒め善業を推奨することから成っている。悪業には、まず身の三業(殺生、偸盗、邪淫)、次に口の四業(妄語、両舌、悪口、綺語)、最後に意の三業(貪欲、瞋恚、邪見)の、全部で一〇種類が数えられている。
一見して素朴な倫理学のように見えるが、ここには十分に掘り下げるべき多くの問題が残されている。私たちは、西洋の近代に確立された心身の二元論をいったん離れた立場で人間への考察を開始した。いまや私たちは、古代アジアの人間観から直接学ぶ可能性を手にしていることになる。本書では非西洋世界の人間観に主題的に立ち入ることはしないが、この可能性は記憶に銘記したい。
「人間」と「言語」には切っても切れない関係があることを仏教はすでに説いているわけですが、言語の本源性についての洞察は、仏教に限ったことではありません。世界三大宗教のひとつ、キリスト教の教典である新約聖書を紐解いてみても、言語に関する注目すべき洞察が見出されます(本講座での聖句の引用はすべて「聖書協会共同訳」を使用しています)。
初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった。
この言は、初めに神と共にあった。
万物は言によって成った。言によらずに成ったものは何一つなかった。言の内に成ったものは、命であった。この命は人の光であった
これは、『ヨハネによる福音書』の1章1節から4節までの聖句です。
また、先に引用した仏教の教えとイエスの教えにも、実は共通点が見出されます。『マタイによる福音書』の15章10節から20節まで読んでみましょう。
それから、イエスは群衆を呼び寄せて言われた。「聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出て来るものが人を汚すのである。」
その時、弟子たちが近寄って来て、「ファリサイ派の人々がお言葉を聞いて、つまずいたのをご存じですか」と言った。
イエスはお答えになった。「私の天の父がお植えにならなかった草木は、みな根こそぎにされる。放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人である。盲人が盲人を手引きすれば、二人とも穴に落ちてしまう。」
するとペトロが、「そのたとえを説明してください」と言った。
イエスは言われた。「あなたがたも、まだ悟らないのか。口に入るものはみな、腹に入り、外に出されることが分からないのか。しかし、口から出て来るものは、心から出て来て、これが人を汚すのである。悪い思い、殺人、姦淫、淫行、盗み、偽証、冒瀆は、心から出て来るからである。これが人を汚す。しかし、手を洗わずに食事をしても、人が汚れることはない。」
このように見てくると、「ホモ・シグニフィカンスの人間観」は、西洋哲学や現代科学の知見を背景として登場した人間観であるとともに、広く東西の伝統的な宗教の世界観とも融和することのできる人間観であることがわかります。
このような人間観を明確に打ち出した点は、何より「ミニマム人間学」の功績と言えるでしょう。
では、「ミニマム人間学」の限界とはどのようなものでしょうか。
これについては、近代以降の哲学の流れを視野におさめながら考えてみる必要があります。
「ミニマム人間学」の登場から今日まで、およそ20年の歳月が過ぎていますが、菅野氏はその後、人間学に関する体系的な著述を世に問うていません。また、別の人が菅野氏の仕事を引き継ぎ、何らかの体系的な人間学の著作があらわされたという話も聞きません。
すなわち、「ミニマム人間学」は「ミニマム人間学」のままでとどまり、今日に至っているのです。
「ミニマム人間学」は一般に、20世紀初頭に確立した哲学的人間学の現代化(バージョンアップ)に挑戦し一定の成果を収めたもの、といった評価を得ていますが、今のところこれ以上のことは何とも言えない、という状態になっているわけです。
人間学の基礎づけはなされたものの、その基礎の上にはまだ何の建物も建てられていない、ということは、言うまでもなく、「哲学的人間学」は基礎の敷設の状態のままで停滞していることを意味します。
とするならば、現在の人間学は、何らかの理由で行き詰まりの状態にあると考えられます。
では、「ミニマム人間学」の登場以後、なぜ人間学を本格的に体系化する業績があらわれていないのでしょうか。
このような問題に対し、単に「人材不足」といったような回答を出してしまうと元も子もないので、ここでは先にも述べたように、近代哲学の全体の流れを考慮しながら、「ミニマム人間学」の限界の問題について考えてみることにしましょう。
デカルト哲学の功績と限界
『人間学とは何か』には、デカルト以来の哲学の知見が含まれていますから(この点がこの著作が持っている説得力のひとつになっています)、「ミニマム人間学」の限界について考えるためには、デカルト哲学の限界について考えてみなければなりません。
(この講座は人間学の初学者をおもな読者層としていますが、煩雑になるのを避けるため、デカルト哲学の概要の説明は省略します。デカルトのいわゆる「方法的懐疑」については『人間学とは何か』の56ページにも簡明な解説があるので、その箇所をお読みになってみてください)。
デカルトは、若い頃イエズス会が運営するラ・フレーシュという学校に学び、その時代の最高の教育を受けながらも、スコラ哲学などの学問に満足することができず、自ら思索を重ね、近代人の発想に目覚めることのできた人です。
デカルトの著作には、『方法序説』のほかに、『省察』、『哲学の原理』、『情念論』、『精神指導の原則』などがあります。
『方法序説』は、哲学のみならず広く一般の学問の方法について述べたものですが、学問の方法論を正面から論じた著作はそれまで存在しなかったため、これが時代のエポックメイキングとなったわけです。
デカルトが生きていた時代に主流だった哲学はスコラ哲学と呼ばれ、それは「哲学は神学のはしため」という原則のもとに存在することが許された学問でした。デカルトは、学問のなかに信仰を持ち込むことをせず、信仰と理性を分離することで、哲学の新しい出発を可能にしたのです。
デカルト哲学の功績を簡単にまとめてみると、次のようになるでしょう。
●哲学が神学から独立したことで、人類はキリスト教の世界観から解放され、合理的な思考を自由にめぐらせることができるようになり、そこから科学が生み出され、科学の発達によって近代的な文明社会を築くことができるようになった。
これが、デカルト哲学の功績です。
では、デカルト哲学の限界とはどのようなものでしょうか。
紙数も尽きてきたので、ここでは結論だけを述べておきましょう。
この問題についてわたしなりにごく簡単にまとめてみると、次のようになります。
●哲学が宗教から分離し、科学が哲学から分離したことで、宗教と哲学と科学がそれぞれの道を歩んだまま共通の場を持つことができず、お互いに対話することのできない状態に陥っている。そしてそのこと(意思の疎通ができなくなっていること)が、さまざまな対立や紛争の種になってしまっている。
20世紀の初頭、マックス・シェーラーが「哲学的人間学」の必要性を訴えたのは、宗教と哲学と科学の分離によって統一的な世界像が失われていくことに危機感を抱いたからにほかなりません。
そして、このような状況は今日に至るまで続いているのです。
浮上する「存在論」の問題
「ミニマム人間学」の限界の問題は、近代哲学(現代哲学を含む)の限界の問題と深い部分で関わり合っています。
その点については今し方見てきた通りですが、問題点を指摘する以上、その解決策を提案し、ものごとを建設的に進めていくのが大人のやり方というものですね。
日本人間学会では、10年以上前から「ミニマム人間学」の限界を指摘する声があがっていました。わたしももちろんそのうちのひとりでしたが、その代案の提示ともなると、これは途方もない仕事となります。
ところがその「途方もない仕事」をやってくれたひとたちが学会のなかに存在するので、わたしのこの講座もその恩恵に浴しているというわけです。
これは、とても希望的なことだとわたしは思っています。
では、その「途方もない仕事」とは、具体的にはどういうものでしょうか。
それは簡単に言うと、現代哲学の新しい基礎づけです。
わたしはいま、とても大それたことを言ってしまいましたが、おそらくは学術の世界に深く関わっている人であればあるほど、「そんなことはありえない」と思われることでしょう。その気持ちは、わたしにもとてもよくわかります。なぜなら、わたし自身がそのように考えるタイプの人間ですから。
デカルト以来数百年も続いている哲学の歴史。
この数百年の歴史のなかには、天才的な哲学者が何人もあらわれ、人間存在の根本問題についてあれやこれやと思索を重ねてきました。
そのおかげもあって、哲学は時代とともに深化し、またそれと歩調を合わせるかのように、科学技術もめざましく進展してきました。
ところが、です。
近代の数百年の歴史を振り返ってみると、人類は必ずしも「希望」に向かって歩みを進めてきているわけではありません。それが証拠に、前世紀には二度も世界大戦が勃発しているし、そのあとには冷戦がはじまり、冷戦のあとにはさまざまな民族紛争が続いていますね。
そして現在においては、アメリカと中国の対立の構図がますます顕在化してきています。なかには、第三次世界大戦の勃発を危惧する声さえあるほどです。
ですから、デカルト以降の近代哲学の進展が近代社会の平和的な発展に寄与しているとは、お世辞にも言えないわけです。
デカルトは独自の発想によって、「思考する人間の思考する限りにおいての実在」を定理とする哲学の旅をはじめましたが、その定理のなかには「自分以外のものはすべて疑わしい」という懐疑主義(および個人主義)が含まれているため、物質的な実在の世界を探求する自然科学は進展しても、本家本元の哲学は、そのようなデカルト哲学の流れから豊かな実りを収穫することができないできました。
もともと世界のすべてを疑っているのですから、そこから何かの建設的な世界観が構築されることはないわけです。
(さらに言うと、バブル経済の時期に訪れたポストモダンの時代には、構築よりも「脱構築」の風潮が強まり、建設よりも解体のほうに力点がおかれていました)。
では、デカルト以来数百年におよぶ近代哲学のそのような「負の連鎖」を根本から断ち切るような新しい哲学は、今のこの時代に本当にあらわれたのでしょうか。
もちろん、「あらわれました」などと軽々しく断言することはできません。
しかし、少なくとも新しい出発にはなっているのではないか、とわたしは考えているのです。
ただし、ここでその問題を掘り下げていく余裕はないので、また回を改めて話すことにしましょう。
次回の講座では、「現代哲学の新しい基礎づけ」とは具体的にどのようなものか、というテーマについて話します。
「新しい人間学」は、当然のことながら、「新しい哲学」の土台を必要とします。
「新しい哲学」は「世界に対する新しい見方」を必要としますが、「新しい世界観」の定立のためには、「新しい存在論」が必要です。
では、その「新しい存在論」とはどのようなものでしょうか。
次回は、ある一冊の著作を紹介しながら、そのあたりのことをお話しすることになります。
最後に、再びイエスのことばを引用して今回の話を締めくくることにしましょう。
また、誰も、新しいぶどう酒を古い革袋に入れたりはしない。そんなことをすれば、新しいぶどう酒は革袋を破って流れ出し、革袋も駄目になる。
新しいぶどう酒は新しい革袋に入れねばならない。
これは、『ルカによる福音書』の5章 37節から38節の聖句です。
イエスは、新しい時代の到来をさまざまな比喩を使って人々に語りましたが、この聖句もそのうちのひとつと考えられます。
このイエスのことばを借りると、人間学に関して次のような定理が立てられるかもしれません。すなわち、「新しい人間学は新しい哲学の上に築かれなければならない」。
では、今回の話はこのへんで。





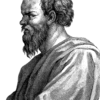
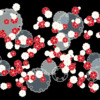

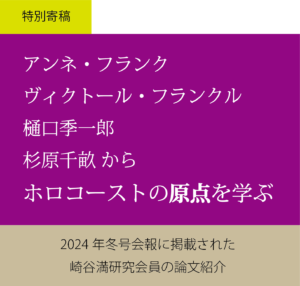





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません