人間学の現在(9)
今回は、菅野盾樹氏の『人間学とは何か』のなかで提示されている「ホモ・シグニフィカンスの人間観」について解説します。
「シグニフィカンス」の語義的な意味については、前回の講座で説明してあるので、ここでは簡単に振り返るだけにしておきましょう。
この用語の「有意」という訳語は「有意義」という言葉とほぼ同義と考えてよく、自分が関わる物事に意義や価値を求める(意義や価値があってほしいと思う)人間の特性に着目したのが、ホモ・シグニフィカンスの人間観、ということになります。
(この概念にはもっと広い意味がありますが、さしあたりこの程度の理解から学びをはじめていきましょう)。
たしかにわたしたち人間は、ただ身体の生命だけを維持していればいい、という存在ではありません。
自分の存在を絶えず気にかけているのがわたしたち人間ですから、自分のことにまったく無関心な人はいないはずで、自己が常に自己に関わっているという点で(そして自尊心というものがその中核にあるという点で)、人間はほかの動物たちとは決定的に違います。
では、菅野氏はこのような人間の特性についてどのような話をしているのでしょうか。
しばらくのあいだ、菅野氏の論議に耳を傾けてみることにしましょう。
人間の存在構造の問題
前回の講座で紹介した『人間学とは何か』の章立ての一部を再度引用すると、次のようになります。
第4章 ホモ・シグニフィカンスの存在論(1):身体
第5章 ホモ・シグニフィカンスの存在論(2):言語
第6章 ホモ・シグニフィカンスの存在論(3):心
人間には心があり、そして体があるということは、誰もが了解している基本的な事実ですね。
実際、西洋の哲学もデカルト以来、人間の存在を心と体の二元的なものとして捉えてきました。
デカルト以前にさかのぼってみても、たとえばソクラテスは身体のなかに魂が宿っていると考えていたし、アリストテレスの哲学においても、この世のすべてのものは「形相」と「質量」によって成り立っていると考えられています。
簡単に言うと、この世界は見えるもの(形のあるもの)と見えないもの(形のないもの)の相互補完的な関係(もしくは表裏一体の関係)によって成り立っているというわけです。そしてこの考え方は、わたしたちの常識とも一致します。
ところが、菅野氏は、人間を心と体の二元的な構造体と捉えることに疑問を投げかけます。
その理由をごく簡単に説明すると、「言語」もまた「心」や「体」と同じくらい人間にとって本源的なものではないか、という疑問があるからです。
そこで、ホモ・シグニフィカンスの人間観においては、人間の存在構造を「身体ー言語ー心」と考えるわけです。
このあたりの事柄について、菅野氏の論議をいくつか引用しておきましょう。
古来、人間は理性的動物と見なされ、古代ギリシアで確立されたホモ・サピエンスの人間類型は歴史的に大きな影響をふるってきた。これらの人間観の根底には、人間がことばを話すという理解、ソシュールのいう言語能力をもつという理解が横たわっていた。特にその点を強調した人間観は、〈ホモ・ ロクエンス〉(ことばを話す人)と呼ばれる。人間が産業に従事し複雑な社会を営み学問を構築することができるのは、つまり一言でいって〈文化〉を営むことができるのは、言語能力を所有するからである。たしかにこうした人間観には多分に真理が含まれている。とはいえ、あえて言うならこの人間観には狭すぎるという欠点がある。なぜなら、人間はいわゆる「言語」以外にも表現能力において優るとも劣らない様々な記号機能(知覚、表情、絵画、ダンス、音楽、身振り・・・)を有するからである。その意味でむしろ人間は〈ホモ・シグニフィカンス〉(記号機能を営む人)にほかならない。
しかし、言語が記号機能の中で枢要な位置を占めることもまた確かなことである。問題は〈言語〉を旧来の誤解や偏見から救い出すこと、人間の存在構造そのものとしての言語を正しく認識する点にある。ヒトという動物は言語を生きるかぎりにおいて人間となるという意味で、人間とはそのまま言語なのである。
(『人間学とは何か』p71〜p72)
「ヒトという動物は言語を生きるかぎりにおいて人間となるという意味で、人間とはそのまま言語なのである」という果断に富んだ宣言が、非常に印象的ですね。
また、デカルト以来のいわゆる物心二元論について、菅野氏は次のように語ります。
デカルトにおける二元論の成立を追体験するとわかることは、二元論がそれ自体きわめて不安定な体系だという点である。心身問題の解決を目ざして、身体ないし物質の要素を重視する人々は、心ないし精神を物質的なものへと還元することを企てる。この行き方がいわゆる唯物論にほかならない。反対に、事物の認識が心の働きである点を強調する人々は、心が認識するかぎりでしか事物の存在を確証できないという理由で、物質的なものを精神的な要素へ還元しようとする。これがいわゆる観念論である。唯物論にしても観念論にしても、それらの考え方の前提には心身の二元論があることに注意しなくてはならない。二元論のバランスが破綻して、物体か精神かのどちらか一方へ体系が傾いた結果、一元論としての唯物論ないし観念論が得られることになるからである。(p55)
『人間学とは何か』では、この叙述のあとに、「二元論を括弧に入れる」という小見出しが続きます。そのセクションの要点は最後の部分に明瞭に出ているので、以下に引用しておきましょう。
デカルトはいったんはすべてが疑わしい、確実なものは何もないという結論に達する。ところがここで一種の逆転現象が生じる。すべてが疑わしいとしても、疑っているかぎりでの私の存在はかえって疑いえないのだ、というドンデンガエシである。こうして有名な「私は考える、ゆえに私はある」の宣言となる。「疑っているかぎりでの私の存在」とは、懐疑が思考の一つの様態であるかぎり、思考という働きそのものが生起していることを意味する。「精神」という実体の定立まではあと一歩である。そして神は別格として、この実体と対立するあらゆる他のものが「物体」という実体として前者に対置される。こうしてデカルト的二元論の成立が宣言されるのだ。
ところが私たちは、「懐疑の物語」が言語と共同体とを前提とするかぎり、物語としての成功がむしろ形而上学(直接には、心身の二元論)としての破綻を意味することを知っている。これが私たちがデカルト的二元論を括弧に入れる歴史的理由にほかならない。(p57〜p58)
菅野氏の叙述は常に明晰なので、上記の引用文に対する解説は不要だと思いますが、念のため、「デカルト的二元論」の弱点をわたしなりに要約しておくと、「デカルトの思想もことばがなければ成立しない」ということになります。
「われ思う、ゆえにわれあり」という有名な名言にしたところで、人間は言葉がなければ「思う」ことすらできないわけですから、人間と言語の関わりの問題は、現代哲学(とりわけ構造主義台頭以降)の主要なテーマとなってきたわけです。
菅野氏はデカルト的二元論に対する批判を行ったあとで、もちろんその代案を示しています。それがすなわち、「ホモ・シグニフィカンスの人間観」の提示となるわけですね。
その部分を引用しておきましょう。
このテクストで私たちが「人間の存在論」と呼ぶのは、人間の存在構造への問いに答えようとする知的探求である。すなわち、人間とはいったい何だろうか、どのような性質や成り立ちをしているのかといった問いへ、経験科学の知見からできるかぎり学びつつ、しかも客観主義や実在論の形而上学にとらわれることなく、合理的でバランスのとれた人間像を描写しようとする試みにほかならない。心と身体の古典的二元論を括弧に入れた私たちがその代わりに用意している新たな枠組みは、人間存在を、身体ー言語ー心という三つの秩序の統合体と捉える人間観である。(p58)
以上の説明で、「ホモ・シグニフィカンスの人間観」がおよそどのようなものかということは、ある程度お分かりいただけたのではないかと思います。

世界認識の窓口としての言語
最後に、ことばと「もの」との関係、あるいはことばと「世界」との関係について、少しばかり考えておきましょう。
といっても、難しい話をするつもりはありません。
これから話そうと思うのは、わたし自身の経験談です。
わたしが「ことばの問題」に関心を持つようになったのは、大学で受けたある講座がきっかけでした。
その講座の担当者は、鈴木孝夫教授(1926〜2021)。
今から40年ほど前のことになりますが、当時わたしは大学一年生で、「履修案内」の次のような講座説明に興味を持ち、受講することにしたのでした。
人間という動物を、他の動物から決定的に区別する特徴は言語である。我々の日常生活はもちろん、学問や知識の伝達も、その大半を言語情報に依存していることは明らかである。いやそれどころか、人間が事実を認識する行為そのものすら、言語という媒体を通すことが多い。現在の人間は本能という決定論的な性格の強い行動様式を極小化し、そのかわり文化という集団および個人の行動を基本的に規制する原理で動いている。その文化が、また言語のしくみと不可分の関係にあるのだ。本講義では、このような複雑で重要な言語現象を単に一つの学問つまり言語学としてではなく、人間理解の手がかり、ひいては自分というものの正しい位置づけの手段として考えていくつもりである。
テキスト: 鈴木孝夫『ことばと文化』岩波新書851
当時の鈴木先生は慶應義塾大学の言語文化研究所の教授で、学問の研究者(つまり普通の意味での大学教授)というよりも、学術分野の探求者といった風格をお持ちの方でした。
大学教授の講座は一般的に言ってあまり面白いものではありませんが、鈴木先生の講座は別格でした。
水曜か木曜の5限だったと思いますが、日吉キャンパスの中規模の教室で先生の話に90分間耳を傾けることが、当時のわたしの楽しみのひとつでもありました。
マイクを片手に滔々と「ことばの問題」を論じ続ける鈴木教授の姿に接して、「知識人とはこういう人のことをいうのか」という印象を持ったことを、今でも覚えています。
その講座でテキストとなっていた先生の著作(『ことばと文化』)は1973年に出版されており、英語や韓国語にも翻訳されているベストセラーです。
この本についてここで詳しい説明をする余裕はありませんが、ことばと「もの」との関わりに関して重要と思われる部分を一箇所、引用しておきましょう。
ところが、ことばとものの関係を、詳しく専門的に扱う必要のある哲学者や言語学者の中には、このような前提について疑いを持っている人たちがいる。私も言語学の立場から、いろいろなことばと事物の関係を調べ、また同一の対象がさまざまな言語で、異なった名称を持つという問題にも取り組んできた結果、今では次のように考えている。
それは、ものという存在が先ずあって、それにあたかもレッテルを貼るような具合に、ことばが付けられるのではなく、ことばが逆にものをあらしめているという見方である。
また言語が違えば、同一のものが、異なった名で呼ばれるといわれるが、名称の違いは、単なるレッテルの相違にすぎないのではなく、異なった名称は、程度の差こそあれ、かなりちがったものを、私たちに提示していると考えるべきだというのである。この第一の問題は、哲学では唯名論と実念論の対立として、古くから議論されてきているものである。私は純粋に言語学の立場から、唯名論的な考え方が、言語というもののしくみを正しく捉えているようだということを述べてみようというわけである。
私の立場を、一口で言えば、「はじめに言葉ありき」ということにつきる。もちろんはじめに言葉があるといっても、あたりが空々漠々としていた世界のはじめに、ことばだけが、ごろごろしていたという意味ではない。またことばがものをあらしめるといっても、ことばがいろいろな事物を、まるで鶏が卵を生むように作り出すということでもない。ことばがものをあらしめるということは、世界の断片を、私たちが、ものとか性質として認識できるのは、ことばによってであり、ことばがなければ、犬も猫も区別できないはずだというのである。
ことばが、このように、私たちの世界認識の手がかりであり、唯一の窓口であるならば、ことばの構造やしくみが違えば、認識される対象も当然ある程度変化せざるをえない。
なぜならば、以下に詳しく説明するように、ことばは、私たちが素材としての世界を整理して把握するときに、どの部分、どの性質に認識の焦点を置くべきかを決定するしかけに他ならないからである。いま、ことばは人間の世界を認識する窓口だという比喩を使ったが、その窓の大きさ、形、そして窓ガラスの色、屈折率などが違えば、見える世界の範囲、性質が違ってくるのは当然である。そこにものがあっても、それを指す適当なことばがない場合、そのものが目に入らないことすらあるのだ。
ここに引用した一節には「ことばがものをあらしめる」という小見出しがついています。少し長くなりましたが、この箇所がひとつの意味段落を形成しているため、全文を引用しました。
どうやら言語というものは、わたしたち人類が進化の過程において、それがあれば便利だから、という理由でたまたま発明し使いはじめたものではないらしい、ということのようです。
このあたりの問題はさらに深い考察が必要となりますが、ここで掘り下げてみる紙幅の余裕がないので、次回の講座のなかであらためて考えてみることにしましょう。
では、今回の話はこのへんで。


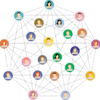

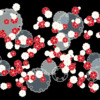






ディスカッション
コメント一覧
こんにちは。記事を拝読しました。
人間学という学問が少し摑めそうな、まだよく分からないような、大きなバルーンのようにぼわんと空中に浮かんでいる、それが視野に入ってはいる、今の私の立ち位置はそんなところです。
身体と心に言語を加えるホモ・シグニフィカンスの人間観を示された菅野盾樹氏の「もっともな」学究の成果に触れる今の今まで、言語をそのようなものとして認識したことはありませんでした。言語学から人間学へと所変われば別の捉え方がある、そうと捉える道筋がある、何よりは人間存在の探究とそのうえの理解へとも導かれうる非常に重要な切り口である、そういうことだろうかと受け止めたのですがいかがでしょうか。
先般第8回のコメント欄で関根先生は、「多くの人に人間学の魅力を伝えたい」と記していらっしゃいました。知識と理解の程度には天と地ほどの差がありながら、私も同じことを思うのです。魅力があるということだけは、しっかり分かっているものですから(笑)。私的に惹きつけられる学問であることのみに留まらず、現代において「この視座が欠けているのではないか」「この試みが出てくると非常に面白いのではないか」― そんな直感と期待感、さらには希望を抱くことさえできるのです。
鈴木孝夫氏の『ことばと文化』は興味深い内容で、購入しようと思っています。「ことばがものをあらしめる」という小見出しの付いた箇所を関根先生が引用されたなかで、自分の思考がしばらく停止したほど強烈な文言がありました。言葉が「世界認識の手がかりであり、唯一の窓口であるならば」という部分です。困難は、問いに答えられないことではなく、問いを立てる力自体がないことだと思いました。次回の投稿を楽しみにお待ちしています。
このたびはご入会ありがとうございました。
わたしのブログがお役に立っているようで、たいへん嬉しく思います。
ことばの問題については、20世紀の哲学を概観すると、「なるほどなぁ」と思うことが多くあります。
わたし自身は、若い頃、ミシェル・フーコーの著作(『言葉と物』や『知の考古学』など)を読み、少なからぬ影響を受けました。
構造主義の発祥がソシュールの言語学にありますから、あのあたりをつついてみると、人間と言語の関係に関わるいろんな知見が出てきて、とても興味深いですね。
日本ではやはり、鈴木孝夫先生(今年の二月にお亡くなりになりました)の著作が非常に分かりやすいと思います。岩波書店から八巻の著作集が刊行されています。
そして、これは次回の講座でとりあげることになりますが、仏教とキリスト教が言語の本源性にすでに(千数百年も昔に)気づいていたという点も、見逃せない事実です。
「人間学の現在」は、今後、言語の問題から、人間が頭のなかに抱く「概念」の問題、そして、人間の心のなかの「情」の問題へと話を深めていく予定です。
いつも熱心にお読みいただき、ありがとうございます。
またのコメントを楽しみにしております。