人間学の現在(22)
今回は『情然の哲学』第7章の解説です。
この章のタイトルは、「世界平和に向けて」。サブタイトルは、「いま私たちにできること」というもの。
こんなに大きなテーマについていったい何を語るのだろう、と思い、好奇心に駆られながらわたしはこの章を読みましたが、著者の言わんとすることは明快で、しかも説得力のあるものでした。
この章のなかで、著者は、まず世界観の問題を取り上げています。これはこれでとても大きな問題ですが、わたしたちが心に描く世界観は、大まかに見ると三つの類型に整理できるというのです。そのため、この章の最初の見出しは「三種の人間観・世界観」というものになっています。
考察の素地になっているのはマックス・シェーラーの「類型学」ですが、このあたりは人間学の領域とも重なるので、少し掘り下げて考えてみることにしましょう。
世界観の三つの類型
哲学的人間学の先駆者と言われるマックス・シェーラー(1874~1928)は、その時代までに上梓された西洋の文献を幅広く調べ、人間の類型学というものを提示しました。
シェーラーのその業績は哲学の分野においても有名なもので、たとえば、菅野盾樹氏の『人間学とは何か』においても、「人間の類型学」は主題的に取り上げられています。
また、わたし自身もまた、本講座のはじめのあたり(2回および3回)でこの問題を扱っています。
『情然の哲学』では、シェーラーが提示した五つの類型を三つにまとめることで、よりすっきりとした整理の仕方になっていますが、世界平和の問題について考える場合、「三種の世界観」に関する理解がどうしても必要になるので、ここで著者の見解を確認しておきましょう。
まずは、次の箇所を読んでみてください。
古代において初めて主流となったのは「ギリシャ的世界観・人間観」であった。その次に来るのが「キリスト教的世界観・人間観」。その源流はキリスト教以前のユダヤ教(古代イスラエル)にあるが、世界に影響を与えるようになったのは、やはりキリスト教がローマ帝国の国教となった四世紀以降のことになる。そして十九世紀、急速に発展した科学を背景に、宗教や道徳的な考えとは全く異なる思想が現れる。即ち「自然科学的、唯物論的世界観・人間観」である。
これら三種の人間観は、それぞれ人間の心の機能である「知・情・意」のどこに重きを置いているかという違いとして見ることもできる。いずれも今なお現代社会に大きな影響を与えている思想である。
(『情然の哲学』p267〜p268)
筆者はこのあとそれぞれの世界観について説明していますが、それらを引用すると長くなってしまうので、わたしのほうで簡単にまとめておきましょう。
(ただし、キリスト教の世界観については「情然の哲学」のそれと重なるところが多いので、ここでは省略します。)
はじめに、ギリシャ的世界観について。
これは簡単に言うと、人間の理性によって世界を把握しようとする態度のことです。そのため、ここでは、ホモ・サピエンスという概念が登場します。人類の哲学の営為は遠い昔、古代ギリシャの時代からはじまっていますが、たしかにわたしたちは理性がなくては人間らしく暮らしていくことができないので、このような人間観は現在に至るまで有効です。
ギリシャ哲学の流れは中世に入ってからキリスト教神学の陰に隠れることになりますが(スコラ哲学と呼ばれるものです)、デカルトの登場により近代哲学として復活します。デカルトは「われ」という自己意識の存在を最も確実なものと考え、そこに新たな哲学の出発点を見出しました。哲学を神学から独立させることで、人間の理性を軸とする新たな思索の道が可能になったわけです。
世界の成り立ちを理性によって解明しようとする態度は、科学を生み出す源泉にもなりました。古代ギリシャにおいて隆盛した自然哲学は、「はじめにあったものとは何か」という問題意識に基づく探索でしたから、人類にはもともと科学を生み出すだけの潜在能力があったと言えます。
(このような能力がなぜ人間にだけあるのかということについて考えるのも、人間学の課題です。)
自然界の仕組みや本質を知りたいという欲求は科学を芽生えさせ、科学はやがて哲学から独立して発展していきます。ここでは、宗教(キリスト教)も哲学も科学も西洋という特定の地域で発祥したものである点に留意しておきましょう。
科学的な知見によって自然界を利用する方法を見出した西洋では、やがて産業革命が起こるようになります。さまざまな機械が発明されることで大規模な工場が出現し、生産力が飛躍的に向上する一方で、労働問題などが起こるようになります。労働者が資本家に酷使され、重労働に苦しむという問題です。そして、産業の近代化にともなって発生したこの問題が、後年、マルクスが『資本論』を書くことになる主要な要因になります。 
次に、唯物論的な世界観について。
神学から独立した哲学の分野では、デカルトのあと、大陸の合理論とイギリスの経験論を統合する哲学者があらわれ(これがカントです)、ドイツ観念論の流れが形成されます。この流れからヘーゲルが登場しますが、かれの哲学は近代哲学の集大成という性格をもっています。デカルトによって出発した近代哲学は、ヘーゲルによって大成されたわけです。
ヘーゲルは絶対精神という概念を用いて壮大な世界観を構築しましたが、かれの思想の背後にあったものはキリスト教でした。哲学が神学から独立したとはいえ、それが西洋という風土のなかで培養されたものである限りにおいて、やはりキリスト教の影響から完全に抜け出ることはありませんでした。
ところがヘーゲル以後、哲学は興味深い展開を示すことになります。ヘーゲル以後の哲学は一般に現代哲学と呼ばれますが、後代の哲学者たちはヘーゲルの哲学をさまざまに批判することで、新しい問題意識を内包したより現代的な哲学を提示したのです。
具体的に言うと、フッサールの現象学や、キルケゴールの実存主義や、マルクスの共産主義思想などです。
人々の人生に影響を与える世界観の形成という観点から見た場合、なかでもとくに重要な出来事は、やはりカール・マルクス(1818〜1883)の登場でしょう。
マルクスはヘーゲルの弁証法から観念的な要素を抜き取り、階級闘争があたかも歴史の必然であるかのような正当化を試みました。いわゆる、唯物史観というものです。ヘーゲルやマルクスの哲学そのものの解説はここではしませんが、マルクスはヘーゲルの哲学を裏返すことによって、「運動する物質」を「神」の位置に置き換えた新しい世界観を構築することになります。
こうして、キリスト教の世界観を根本的に転覆させる世界観が、マルクスによって提示されることになったわけです。
これがいわゆる、共産主義思想(唯物論的世界観)というものです。
キリスト教の経典は『聖書』ですが、共産主義の経典は『資本論』です。キリスト教には、「キリストによる罪からの解放」という理念がありますが、共産主義には、「革命による労働者たちの解放」という理念があります。どちらもその構造には類似点があり、共産主義はキリスト教とは真逆の「唯物論信仰」であるともいえるでしょう。
結局、共産主義はキリスト教の「鬼っ子」として世に出ることになったわけです。
実際、共産主義は、その発生の当初からキリスト教を目の敵にしていた歴史があります。マルクスはもともとユダヤ教の家系に生まれたひとでしたが(かれの先祖は代々ユダヤ教のラビでした)、マルクスがまだ幼い頃、家族がキリスト教に改宗するという事件が起こります。キリスト教の素晴らしさに触れて心から改宗したというよりも、ユダヤ教徒のままでいるとなにかと肩身が狭いから、という理由だったようです。
ですから、マルクスにとってキリスト教は憎むべきものでした。
共産主義の思想のなかには抑圧や疎外という概念がありますが、これらの概念は、かれにとって実感を伴うものだったのでしょう。
そんな状態ですから、このままでは世界観の統合はおろか、それぞれの陣営の有力者たちが対話の機会を持つことすらできません。みんなが協力しあって平和な世界を築きあげていくことなど、夢のまた夢という状態にあるわけです。
とりわけ、アメリカ(キリスト教)と中国(共産主義)の対立などは、先行きのまったく見えないとても大きな問題ですね。
しかしながら、改めて冷静に考えてみるなら、この世界は一つのものであると考えることもできます。
一つの世界に、三つの世界観。
これはいったい、どういうことなのでしょうか。
一つの世界に生きているはずのわたしたちが、どうして三つの世界観を持つようになり、たがいに争い合っているのでしょうか。
誰もが一度は心に抱くであろうこのような疑問について、もう少し掘り下げて考えてみましょう。

世界観をめぐる三つの立場
ここからはわたし個人の見解になりますが、ひとが世界の根源について考える場合、そこには必然的に三つの立場が生まれるようになります。
一つ目は、この世界は偶然に生まれた、というもの。二つ目は、この世界は必然的に生まれた、というもの。三つ目は、偶然であれ必然であれ、人間は世界が生まれた原因についてその真相を知ることはできない、というもの。
一つ目の立場は、唯物論。二つ目の立場は、神の創造論。そして三つ目の立場は、不可知論というものです。
原理的に考えてみても、世界の発生は、偶然か必然かのどちらかであり、それ以外の可能性はありません。なぜかというと、わたしたちは物事の発生の原因について考えるとき、「偶然」と「必然」以外の概念を持ち合わせていないからです。
ですから、世界の発生について考える立場としては、偶然説、必然説、不可知論説、という三つの選択肢しかないわけですね。
そして、偶然説の陣営は共産主義の思想としてまとまり、必然説の陣営はキリスト教の思想としてまとまり、また不可知論説の陣営の人たちは、哲学的もしくは科学的な探求を今なおエンドレスに続けているわけです。
ごく大雑把に捉えてみると、「世界観の三つの類型」はこのようなものになると考えられます。
ここで、少し話題を変えて「知識人の苦悩」という問題について考えてみましょう。
昔から知識人の肖像画というものは、とてもいかめしいものになっているのが通例です。高校の「倫理」の教科書に掲載されているヘーゲルの顔などを見ても、このことはよくわかりますね。にこやかな笑顔で仕事に励んでいるヘーゲルなど、ちょっと想像できません。かれら知識人たちはみな、ああでもないこうでもないといった出口のない思索の生活を続けているため、どうしても暗い表情になってしまうのでしょう。
『出口なし』という戯曲を書いたサルトルもまた、教科書に出ているのはいかめしい顔がほとんどですが、ここで留意しておきたいのは、わたしたちがどのような世界観を信ずる(もしくは支持する)にしても、そこに「出口はない」ということです。
共産主義の思想を信じた場合には、世界的な規模で共産革命が起こらないかぎり搾取のない平等な世の中が訪れることはない、ということになります。また、キリスト教の思想を信じた場合には、イエス・キリストが天から降りてこないかぎり(これをイエスの再臨といいます)「神の国」がこの地上にあらわれることはない、ということになります。それから、不可知論の陣営では「アルケー」の問題はもとより迷宮入りの状態ですから、探求を続ける科学者や哲学者たちは、何かの未来像を思い描くことすらできません。
いずれにしても、未来に大きな希望を抱くことができるような世界観を、現在のわたしたちは持ち合わせていないというのが現状です。
そのため、歴代の知識人たちはみな、申し合わせたようにいかめしい顔をしているのです。
ところが、『情然の哲学』では、これまでわたしたちが見てきたような三つの世界観のほかに、第四の世界観と言うべきものを提示しています。
それがすなわち、「情然の哲学の世界観」というものです。
第四の世界観の登場
では、「情然の哲学」の世界観とはどのようなものでしょうか。
それは本当に、わたしたちに大きな希望を与えてくれる世界観なのでしょうか。
知識人たちが明るい顔をしながら言論活動に勤しむような、そんな新しい時代が、「第四の世界観」の登場によって本当にやってくるものなのでしょうか。
このあたりの問題について検討してみることにしましょう。
まずは、『情然の哲学』の本文を確認します。
情然の哲学は宇宙の本体を情然であるとしている。あらゆる存在の前に情然のゆらぎがあった。そしてそれは今この瞬間もすべての存在を底流で支えている根源的エネルギーである。
情然の場は、物理学的には真空エネルギー場と捉えられる。それが単なる無機質な運動ではなく、原クオリアを伴ったものであるという観点から「情」という言葉を使用している。それは私たちが通常意識する「感情」と同じものではない。知・情・意に分化する前の原初的な精神的エネルギーであり、これまで繰り返し述べてきたように、理性も、そして物質も、そこから生まれることになる文字通り一元的な根源である。
情然は、人間の意識の中では知・情・意という心の機能として現れる。「情」は感じる心であり、「知」は考える心である。「意」は情と知の相互作用によって生じる欲求であり、自らを目的や理想に向かって進めようとする力となる。本来的にはそれぞれ調和的な関係であり、そこに対立や闘争があるとすれば、それはむしろ病的あるいは未熟な状態と言わざるを得ない。しかし実際はほとんどの人が本来の人間性を確立できずにいるというのが現実ではある。キリスト教では原罪を負った罪人であり、仏教では煩悩の囚人ということだ。それゆえに「原罪からの救済」や「煩悩からの解脱」など、本来の状態に戻ろうとする修行や信仰的・道徳的生活は、その方法の是非は別として大切なことであり、情然の哲学では、それは知・情・意の調和的なバランスを取り戻すアプローチであると考える。
右図(省略)にあるように情然の哲学の世界観や人間観は、結果的に先に挙げた三種の人間観を補完的に統合したものになっている。
(『情然の哲学』p273〜275)
新しい世界観についてのじつに見事な解説であると思います。
「結果的に先に挙げた三種の人間観を補完的に統合したものになっている」というくだりも、とても希望的かつ建設的です。
わたしのほうでは、なぜ「情然の哲学」が新しい世界観なのかということについて、次の二点を指摘しておきましょう。
■アルケーの問題について明確な回答を提示したこと。
■ ヘーゲルの弁証法に対し根本的な訂正を提案したこと。
この二点について若干の説明をしておきます。

先に引用した箇所にもあるように、「情然」という概念は非科学的なものではありません。科学そのものではありませんが、現代科学の知見に反するものでもないのです。強いて言うなら、「情然」という発想は、科学と哲学と宗教を超えた次元のある特別な直感によって生まれ出た、と言うべきものかもしれません。
そのため、「情然の哲学」は、科学的でもあり、哲学的でもあり、宗教的でもあるのです。
それからもう一つ。
「情然」とは、「情が情のままにある状態」ですから、わたしたち人間にとって決して「不可知のもの」ではないということです。
たとえば、「霊」や「魂」という用語にはつねにある種の曖昧さがつきまといますが、「情」にはそうしたとらえどころのないイメージはありません。なぜかというと、わたしたちは日々の生活において、つねに何かしらの「情」を心の中に宿らせながら生きているからです。
うれしいとか、悲しいとか、せつないとか、やるせないとか、腹立たしいとか、うしろめたいとか、そのような「情」を経験したことのない人はおそらくいないでしょう。
そのため、「情然の哲学」においては、わたしたち人間は宇宙の本体と直接的に結びついていることになるのです。
宇宙における人間の位置をかつてないほど高めたものであるために、わたしはこの思想、この世界観に対して大きな希望を持っているわけですね。
次に、「情然の哲学」における発展の法則について説明します。
この法則について考えるときには、三世代家族のモデルを思い浮かべてみるのがよいでしょう。
三世代家族のなかには、祖父母と父母と子女がいます。時間的に見ると、三世代家族は二世代家族の発展形態であり、空間的に見ると、子供たちがそれぞれ家庭をもつことで家族が氏族に発展することになります。
個人から家庭へ、家庭から氏族へ、氏族から民族へ、民族から国家へ、国家から世界へという発展形態は、ヘーゲルが言うような「正・反・合」の原理(弁証法)によってなされるのではなく、「正・極・昇合」の原理によってなされるのではないでしょうか。
「家族的四位構造」(これについてはこれまで何度か説明してきました)はそれ自体のなかに「正・極・昇合」の関係性をもっているので、存在するものはすべて、自らのアイデンティティを保持しながら次の段階に発展することができるのです。
そしてそこにあるのは、「正と反」の闘争の関係ではなく、「正から分かれた二つの極」の互恵の関係だというわけです。
平和な状態(互恵的関係)を維持しつつ望ましい発展をしていく、というのが、「情然の哲学」の世界観だと考えてもらえればよいでしょう。
男性と女性が愛し合って新しい家庭をつくるというのも、わたしたちに身近な実例ですね。
(そして聖書によれば、これこそがまさに神の祝福です。)
ヘーゲルやマルクスの弁証法は知識人の世界観にも多大な影響を与えてきており、闘争の現実が闘争の世界観をつくり出し、そしてまた闘争の世界観が新たな闘争の現実を生み出してしまうという悪循環が、人類の歴史において繰り返されてきました。
そのような負のスパイラルから抜け出すために生まれた新しい思想が、「情然の哲学」だというわけです。
「正・極・昇合」の法則については『情然の哲学』の4章と5章に詳しい解説があるので、関心をお持ちの方は直接原典にあたって確認してみてください。
ちなみに、ここでいう「昇合」は、「昇華」と「融合」の概念を組み合わせてつくった造語です。
新しい世界観を表現するために、新しいことばが必要になったのでしょう。
では、今回の話はこのへんで。

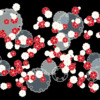









ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません