人間学の現在(13)
今回は、『情然の哲学』の主要概念である「情然」について、わたしが日頃考えていることを話してみたいと思います。
この概念はとても奥が深いため、不用意に掘り下げていくと深みにはまり、難解な議論になってしまう危険性もあります。
そのため、まずは、わたしたちが日ごろ身近に経験していることから話していくことにしましょう。

点と線と面と立体
上記の見出しにある「点・線・面・立体」については、わたしたちは小学生のときに学んでおり、誰もが理解していることがらのひとつとなっています。
ですから、そこに何かしらの神秘を感じる人はおそらくいないでしょう。ところが、この四つの存在について哲学的に考えてみた場合、点と線と面は概念上の存在であり、わたしたちが生きているこの世界に実在するものではありません。
このことは、ちょっと考えてみるとすぐにわかりますね。
小学校では、「線は点を集めたもの」と学びますが、これはあくまで子供向けの説明であり、「とりあえずそう理解しておけばいい」という教育的な配慮を含んだ説明です。点にはそもそも長さがありませんから、長さがゼロのものをいくら集めても、そこから長さのあるものが出てくることはないのです。
同様の理由で、面は線を集めたものではないし、また、立体は面を集めたものではありません。
そもそも、この世界は時間と空間によって成立しており、空間のなかには、縦・横・高さを属性にもつ三次元のもの(立体)以外存在することができません。
実際、筆記具で点を書いてみても、そこにあるのは立体であり(顕微鏡で見ると長さや高さを測定することができます)、その立体の長さや高さを考えないことで(あるいはないものとすることで)、わたしたちはその立体を「点」として扱っているわけです。
とするなら、この世界をいくら分割しまた縮小したとしても、その最終的な形態が「点」になることはない、ということになります。
では、この世界の初めにあったものとは何だったのでしょうか。また、この世界の最小単位とはいったい何なのでしょうか。
これはいわゆる、わたしが前回の講座で俎上に乗せたアルケーの問題ですが、このあたりの問題についてもう少し掘り下げてみることにしましょう。
数字と文字と音符
小学校の算数でいちばんはじめに学ぶのは、自然数というものです。指の数を数えると5本あり、右手と左手の指を合わせると10本になります。これが、わたしたちにとっていちばん身近な自然数です。
それが証拠に、低学年の児童たちは、指を折ったり伸ばしたりしながら足し算や引き算をしますね。
子供たちはそれから、筆算を学び、九九を学び、小数を学び、そして分数を学びます。たとえば、10 ÷ 3の計算では「割り切れない」という問題が発生しますが、子供たちは分数を学ぶことでこの問題に対処します。
また、自然数に0という数を加えることで、整数の概念も学びます。
小数と分数と整数を学ぶことで、日常生活で必要な計算の大半はできるようになるわけです。
また、国語の時間では、子供たちは文字を学びます。小学校に上がる時点で話し言葉は相当数覚えていますから、その土台のうえで、書き言葉を学んでいくわけです。
わたしは今でも、小学一年の最初の国語の授業を覚えていますが、教科書の最初のページには、「見える見える」とありました。その文字が右ページの上のほうに大きく書いてあり、見開き2ページにわたって街の風景が広がっていました。
何が見えるかな、と、先生が質問を投げかけると、子供たちは元気よく手を挙げて答えます。山が見えます、川が見えます、学校が見えます、公園が見えます、というように。
生まれてから数年間の生活のなかですでに習得している話し言葉をもとにしながら、子供たちは読み書きの勉強をはじめるわけです。
文字の学習はどこがスタートラインかというと、もちろん、「あいうえお」ですね。
算数で学ぶ「12345」と、国語で学ぶ「あいうえお」と、音楽の授業で学ぶ「ドレミファソラシド」は、ある観点から見ると、じつは同じ原理に基づいたものと考えることができます。
では、その「同じ原理」とはどのようなものでしょうか。
答えを言いましょう。
わたしたちが日ごろ身近に接している「数字と文字と音符」は、すべて「差異の原理」によって成立し、機能しているのです。
「あ」や「い」や「う」は、それ自体としては何を意味するものでもありません。たとえば、人の口からいきなり「あ」という声が発せられたとしても、その人が何を言いたいのかはわかりませんね。
「あ」という文字は、それ自体として何を意味するものでもありませんが、「い」や「う」ではない、というアイデンティティは持っています。すなわち、「あ」という文字は、五十音のなかでの自分の位置を「あ」として持っており、全体(五十音)との関係のなかで「あ」として存在しているわけです。とするならば、「あいうえお」をはじめとする日本語の元素は、そのおのおのが五十音(およびそれぞれの音に対応する文字)のなかでの差異によって成立していることになります。
ごく簡単に言うと、これが「差異の原理」というものです。
差異があるから意味が生まれ、意味があるから認識が生まれ、認識があるから存在が生まれる。
これが、「差異」と「存在」の間にある因果関係ではないかと、わたしは考えているのです。
結局のところ、「12345」も、「あいうえお」も、「ドレミファソラシド」も、あるいは「ABCDEFG」も、そこに働いているのは「差異の原理」であり、それ以外のものではありません。
以前の講座で、わたしは鈴木孝夫教授の著書を引用し、「言葉がものをあらしめる」という話をしましたが、考えてみると、文字も、数字も、記号も、音符も、すべて「差異」によって成立しているわけですから、より普遍的な言い方をすると、「差異がものをあらしめている」ことになります。
ところで、数字や文字というものは、そもそもわたしたち人類が世界認識のためのツールとして生み出したものです。わたしたちは言語や記号によって世界を「分節化」し(さまざまな事象を概念に還元して把握するといったほどの意味です)、万物の霊長として、地球という星に文明社会を築き上げてきました。そういう意味では、菅野盾樹氏が指摘するように、わたしたち人類はたしかに「ホモ・シグニフィカンス(記号活動を営む動物)」であるといえるのです。
では、この「差異」の問題についてもう少し掘り下げて考えてみましょう。
数字は純粋に「量」を表す記号ですから、数字を例にとり、数と数の「間にあるもの」について考えてみると、少し不思議な世界が見えてきます。

数の「隙間」問題
わたしは文系の人間なので、数学をとことん学んだわけではありません。高校三年になって文系の進路を選択したため、数学ⅡBまでは学習しましたが、数学Ⅲは学んでいません。そのため、数学の分野において、わたしのなかで未解決のままの問題がいくつかあります(今からでも学べばいいのですが、なかなかそこまでの時間がとれない状態です)。そのうちの一つが、数の「隙間」問題というものです。
数直線上の数を整数に限定して考えた場合、ある数の隣にある数はすぐにわかります。たとえば、5の右隣りにある数は6であり、左隣りにある数は4です。また、数と数の間にある距離も、引き算を使えばすぐに求められます。たとえば、6から9までの距離は3ですね。
ところが、整数という条件を外してしまうと、「ある数の隣りにある数」は数字で表すことができなくなります。たとえば、5と6の間には、5.1や5.01といった小数が無数にあるため、「5のすぐ隣りにある数」は表記できないし、表記による数の特定ができないのであれば、そもそも「ある」と言えるのかどうかも分かりません。
高校の数学の教科書には、「有理数+無理数=実数(数直線上にある数)」という説明がありましたが、無理数とはすなわち循環しない無限小数のことですから(循環する小数であれば分数で表記することができます)、そうした数は表記することができません。
数直線上にありながら数字で表記することのできない数(無理数)があり、有理数だけでは数直線が隙間だらけになるという事実は、わたしたちにいろんなことを考えさせてくれます。
たとえば、ルート2は無理数であり、数字では表記できませんが、ルート2にルート2をかけると2という整数が出現します。無理数を二乗すると、そこから有理数が出てくるわけです。
循環せずに無限に続く小数を二乗すると、小数点以下の無限に続く数字がそっくり消えてしまうのですから、これは、不思議といえば不思議です。また、数直線のなかには無数の無理数があるということも、不思議といえば不思議です。高校生のわたしはこのような現象について「なぜなのか」と哲学的に考えてみましたが、結局答えは出ないままに終わりました。
ここで、「アルケー」の問題に戻り、「世界の初めにあったものとは何か」という問題について再び考えてみましょう。
「差異」と「間」と「関係」と「場」
以上見てきたように、有理数の範囲で数の並び(数列)について考えてみると、数と数は明らかに離れて存在しています。そのため、頭の中である特定の数を想定した場合、その数は他の数とは違うというアイデンティティを持ち、「差異」の原理によって存在していることがわかります。
しかしながら、差異の原理が発動するためには、その数は他の数と関連づけられていなければなりません。たとえば、先に例に挙げた5という数は、他の数との関係のなかで初めて「5」であることができるわけですね。もちろん、他のすべての数においても事情は同じです。
したがって、アルケーについて考える際には、「差異」や「間」や「関係」という概念が重要になってきます。現代に生きるわたしたちは、これらの概念を抜きにして存在の問題を考えることができないのです。
面白いことに、現代の物理学においても、ミクロの世界を考える際には、これらの概念が必須のものとなります。
わたしたちが日頃接している物質というものは結果的な存在であり、原因的な世界においてはモノの姿もモノの性質も見当たらないというのが、今の科学の常識です。
ですから、アルケーは少なくともモノではありません。とするなら、分子や原子はもとより、原子を構成している素粒子ですらないということになります。
紙数も尽きてきたので、そろそろまとめに入りましょう。
世界の初めにはある何らかの「量」があり、人類はその(完全には理解できない)「量」を分節化して「数」や「文字」を生み出し、その数や文字をさまざまに利用することで世界を把握することができる存在となった。
おおざっぱに言うと、そういうことになります。
そうなると、「はじめにあったもの」とはあるなんらかの「量」であり、その量はある何らかの「場」として存在していた、ということになります。
「情然の哲学」では、はじめにあったものは「情然の場」であると定義していますが、なぜ「情然」なのかということについては(そしてなぜ「場」なのかということについては)、さらなる説明を必要とします。
「情然」とは、「情」+「然」を意味する造語ですが、そもそも「情」とはいかなるものなのでしょうか。
次回は、そのあたりのことについて考えてみることにしましょう。






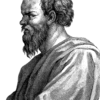




ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません